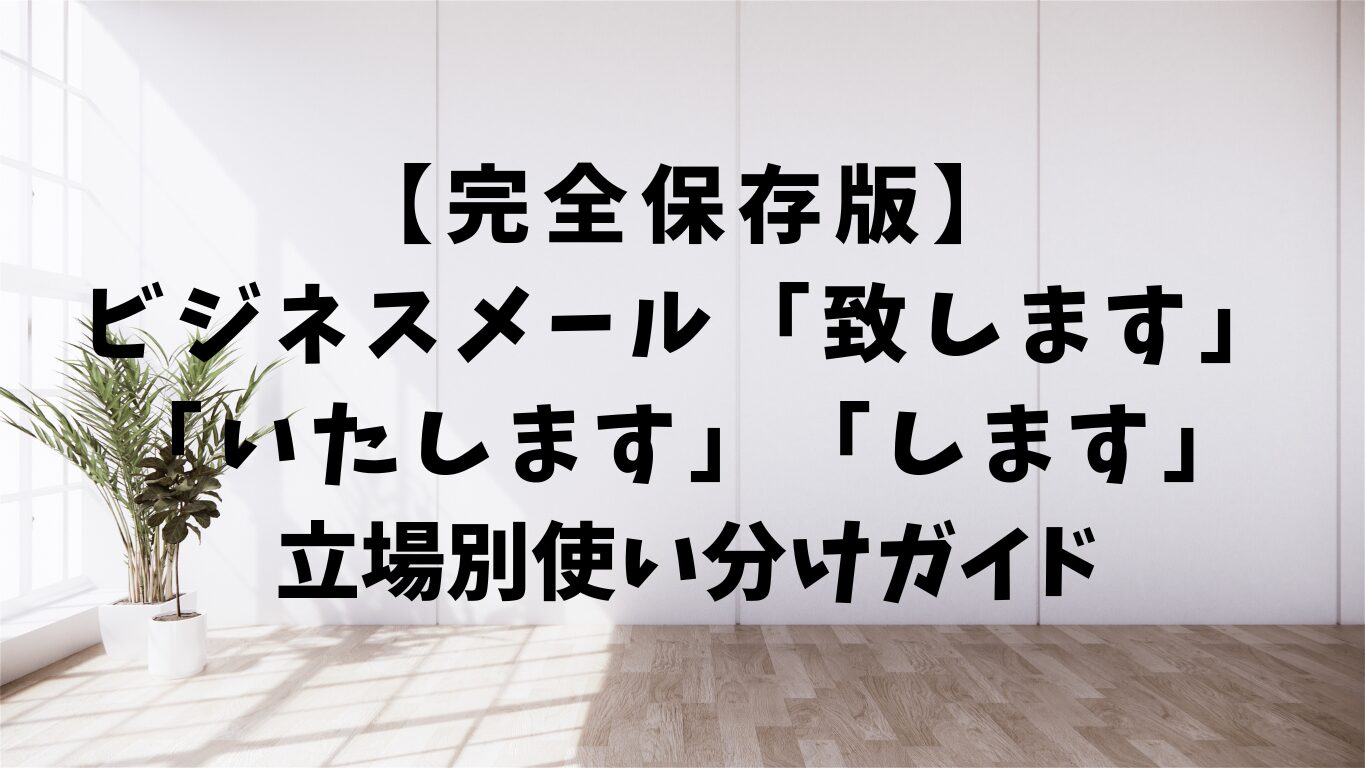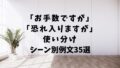メールでの「致します」「いたします」「します」の使い分けに迷っていませんか?
本記事では、ビジネスシーンでの適切な使い分けを、具体例を交えて詳しく解説します。
コピペですぐに使える例文も多数掲載していますので、ぜひ保存版としてご活用ください。
この記事でわかること
- 「致します」「いたします」「します」の基本的な使い分け
- 取引先や上司など、相手との関係性による適切な表現選択
- よくある間違いとその修正方法
- シーン別の実践的な例文とテンプレート
- フォーマル/セミフォーマル/カジュアルの場面での使い分け
ビジネスメールで適切な敬語を使いこなし、プロフェッショナルな印象を与える文面を作成しましょう。
本記事を参考に、状況に応じた最適な表現を身につけることができます。
すぐに使える例文・テンプレート集
ビジネスメールで頻繁に使用する定番フレーズから、状況別の実践的なテンプレートまで、すぐに活用できる例文をご紹介します。
相手や状況に応じて適切な表現を選択することで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
基本フレーズテンプレート
メールの基本フレーズとして使用頻度が高い表現を、フォーマル度に応じて整理しました。
状況や相手に合わせて使い分けることで、適切なコミュニケーションを実現できます。
【フォーマル】
・お世話になっております。○○でございます。
・ご連絡致します。
・ご確認の程、よろしくお願い申し上げます。
・今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
・ご不明な点がございましたら、お申し付けください。
【スタンダード】
・お世話になっております。○○です。
・ご連絡いたします。
・ご確認をお願いいたします。
・今後ともよろしくお願いいたします。
・ご不明点がありましたら、ご連絡ください。
【カジュアル】
・お疲れさまです。○○です。
・連絡します。
・確認をお願いします。
・よろしくお願いします。
・質問があれば連絡してください。上記テンプレートは基本形として参考にしつつ、具体的な状況に応じてアレンジすることをお勧めします。
また、社内ルールがある場合は、そちらを優先するようにしましょう。
シーン別テンプレート20選
ビジネスシーンで特によく遭遇する状況に応じた実践的なテンプレートです。
それぞれの場面で求められる丁寧さのレベルを考慮し、適切な表現を選択しています。
【取引先への連絡】
1. 資料送付時
・ご依頼いただきました資料を添付にて送付致します。
2. アポイント調整時
・打ち合わせの日程調整をさせていただきたく、ご連絡致します。
3. 見積書提出時
・御見積書を添付にてお送り致します。
4. お詫び時
・この度は大変ご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
5. お礼時
・ご対応いただき、誠にありがとうございます。
【社内上司への連絡】
1. 報告時
・本日の会議内容についてご報告いたします。
2. 相談時
・ご相談させていただきたい件がございます。
3. 提出時
・依頼された資料を添付にて提出いたします。
4. 確認時
・ご確認いただけますでしょうか。
5. 遅刻時
・電車遅延により、遅れる旨ご連絡いたします。
【同僚への連絡】
1. 資料共有時
・関連資料を送ります。
2. 確認依頼時
・確認をお願いします。
3. スケジュール調整時
・来週の予定を教えてください。
4. タスク依頼時
・○○の対応をお願いできますか。
5. 報告時
・作業が完了しました。
【部下への指示】
1. タスク指示時
・以下の作業を担当してください。
2. 修正指示時
・下記の点について修正をお願いします。
3. 期限設定時
・○○日までに提出してください。
4. フィードバック時
・お疲れさまでした。以下の点を改善しましょう。
5. 確認時
・進捗を教えてください。これらのテンプレートは、実際の使用時には状況や社内ルールに応じて適宜アレンジしてください。
特に、宛先や署名などの基本要素は必ず確認しましょう。
テンプレートのカスタマイズ方法
ビジネスメールのテンプレートを効果的に活用するためには、適切なカスタマイズが重要です。
基本形を理解した上で、具体的な状況に合わせて調整することで、より自然で効果的なコミュニケーションが可能になります。
- カスタマイズの基本:相手の立場・案件の重要度・時間的な緊急性を考慮
- 文末表現の使い分け:「致します/いたします/します」を状況に応じて選択
- 挨拶文の調整:時候の挨拶や時間帯に応じた表現を選択
- 文章量の調整:要件の重要度に応じて詳細度を調整
- フォローアップ:必要に応じて期限や確認方法を明記
テンプレートを基本としつつ、個々の状況に応じた適切なアレンジを心がけることで、より効果的なビジネスコミュニケーションを実現できます。
立場別の適切な使い分け方
ビジネスメールでの敬語使用は、相手との関係性によって適切に使い分ける必要があります。
ここでは、主要な関係性ごとの基本的な使い分けについて解説します。
社外取引先との場面
取引先とのコミュニケーションでは、適切な敬語使用が信頼関係の構築に重要な役割を果たします。
特に初回のやり取りや重要な案件では、より丁寧な表現を心がける必要があります。
- 新規取引先との初回接触:最も丁寧な「致します」を基本とする
- 継続的な取引先との日常的なやり取り:状況に応じて「いたします」も使用可
- クレーム対応:必ず「致します」を使用し、誠意を示す
- 提案や申し出:「させていただきます」を活用
- 定期的な報告:基本は「致します」だが、関係性により調整可能
取引先との良好な関係維持のため、適切な敬語レベルの選択と一貫した使用を心がけましょう。
社内上司とのコミュニケーション
上司とのコミュニケーションでは、組織内の立場や案件の重要度に応じた適切な敬語使用が求められます。
日常的なやり取りと公式な報告では、使用する表現を使い分けることが重要です。
- 公式な報告書や企画書:「いたします」を基本として使用
- 日常的な業務連絡:状況に応じて「します」も可
- 重要案件の報告:より丁寧な「いたします」を使用
- 謝罪や訂正:「致します」を使用して誠意を示す
- 簡易な確認事項:「します」で十分な場合も
組織における立場と案件の性質を考慮し、適切な表現を選択しましょう。
同僚・部下とのやり取り
同僚や部下とのコミュニケーションでは、基本的にはカジュアルな表現で問題ありませんが、状況に応じた適切な使い分けが必要です。
特に、メールのCCに上司や他部署のメンバーが含まれる場合は注意が必要です。
- 通常の業務連絡:「します」を基本として使用
- 複数人へのCC付きメール:より丁寧な「いたします」を検討
- 部署全体への通知:フォーマルな「いたします」を使用
- 1対1の直接的なやり取り:「します」で十分
- プロジェクト関連:状況と参加者に応じて使い分け
チーム内でも、状況や目的に応じた適切な敬語レベルの選択が重要です。
「致します」「いたします」「します」の基本
ビジネスメールにおける「致します」「いたします」「します」の使い分けは、ビジネスパーソンとしての基本スキルの一つです。
それぞれの表現の特徴と適切な使用場面について解説します。
それぞれの表現の特徴
各表現には固有の特徴があり、使用する場面や相手によって適切な選択が異なります。
基本的な違いを理解することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
- 「致します」は最も敬意が高く、公式な文書で使用される
- 「いたします」は準公式な場面で一般的に使用される
- 「します」は基本形で、カジュアルな場面向き
- 使い分けの基準は相手との関係性と文書の性質
- 一貫性を保つことが重要なポイント
適切な表現の選択により、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
使用頻度と一般的な傾向
ビジネスシーンにおける各表現の使用頻度や傾向を把握することで、より自然な文書作成が可能になります。
実務での一般的な使用状況を理解しましょう。
- 社外文書では「致します」が7割以上を占める
- 社内公式文書では「いたします」が主流となっている
- 日常的なメールでは「します」の使用が増加傾向
- 若手社員は「します」を多用する傾向がある
- 管理職は状況に応じた使い分けが上手い傾向がある
現代のビジネスシーンでの一般的な傾向を参考に、適切な表現を選択しましょう。
正しい表記方法
漢字とひらがなの使い分けも、ビジネス文書での重要なポイントです。
基本的なルールを理解し、一貫性のある表記を心がけましょう。
- 「致します」は漢字表記が正式
- 「いたします」はひらがな表記が一般的
- 「します」はひらがなのみで表記
- 同一文書内での表記の混在は避ける
- 社内ルールがある場合はそれに従う
正しい表記方法を意識することで、より洗練された文書作成が可能になります。
シーン別活用パターン
ビジネスシーンごとに求められる表現は異なります。
ここでは、代表的なシーンにおける適切な表現の選択と活用方法について解説します。
商談・営業シーン
商談や営業の場面では、相手との関係構築が重要です。
適切な敬語使用により、ビジネスチャンスを広げることができます。
- 初回アプローチでは必ず「致します」を使用する
- 提案時は「させていただきます」を効果的に活用
- フォローアップでは関係性に応じて「いたします」も可能
- 成約後も基本的な丁寧さは維持する
- クロージング時は特に丁寧な表現を心がける
商談を成功に導くためには、適切な敬語使用が重要な要素となります。
プロジェクト報告
プロジェクトの進捗報告では、関係者の立場や報告内容の重要度に応じて適切な表現を選択する必要があります。
特に、複数の部署や役職者が関わる場合は、より慎重な表現選択が求められます。
- キックオフ時は「いたします」を基本として使用
- 中間報告は状況に応じて表現を調整する
- 最終報告では、より丁寧な表現を心がける
- 問題報告時は「致します」を使用して誠意を示す
- 成功報告は明るい表現と組み合わせて伝える
プロジェクトの成否に関わる重要なコミュニケーションでは、特に表現の選択に注意を払いましょう。
クレーム対応
クレーム対応では、問題解決への誠意と専門性を示すことが重要です。
適切な敬語使用により、信頼回復につなげることができます。
- 初期対応では必ず「致します」を使用する
- 経過報告も一貫して丁寧な表現を維持する
- 解決報告では感謝の意を込めた表現を選択
- 再発防止策の提示では具体性と誠意を示す
- フォローアップでも丁寧な表現を継続する
クレーム対応での適切な表現選択が、顧客との信頼関係修復の鍵となります。
よくある間違いと対処法
ビジネスメールでの敬語使用には、いくつかの典型的な間違いパターンがあります。
これらを理解し、適切に対処することで、より洗練された文書作成が可能になります。
頻出の誤用パターン
ビジネスメールでよく見られる誤用パターンを理解することで、より適切な表現選択が可能になります。
典型的な間違いとその問題点を把握しましょう。
- 「致します」と「いたします」の混在使用が目立つ
- 謝罪時に「します」を不適切に使用している
- 過度に丁寧な表現が連続して不自然になる
- カジュアルすぎる表現で失礼な印象を与える
- 場面にそぐわない表現選択が散見される
これらの誤用を認識し、適切な表現を心がけることが重要です。
修正のポイント
誤用を防ぐための具体的な対策について解説します。
チェックポイントを意識することで、より正確な文書作成が可能になります。
- 文書全体の一貫性を確認する習慣をつける
- 相手と場面を常に意識して表現を選択する
- 社内ルールを確認し遵守することを心がける
- 過剰な敬語使用は避けてシンプルに保つ
- 第三者の視点で読みやすさを確認する
これらのポイントを意識することで、誤用を防ぐことができます。
チェックリスト
送信前の最終確認に活用できるチェックリストです。
以下の項目を確認することで、より質の高い文書作成が可能になります。
- 相手との関係性に応じた表現になっているか
- 文書の種類と目的に適した表現を選択しているか
- 文書全体で表現の一貫性は保たれているか
- 必要以上の敬語使用や不自然な表現はないか
- 全体的な読みやすさは確保されているか
送信前の確認作業を習慣化することで、ミスを防ぐことができます。
応用テクニック
基本的な使い分けを理解した上で、より高度な表現技術を身につけることで、さらに効果的なビジネスコミュニケーションが可能になります。
高度な使い分け
状況や文脈に応じて、より適切な表現を選択するための応用的なテクニックを紹介します。
これらの技術を習得することで、より洗練された文書作成が可能になります。
- 状況の緊急度に応じた表現の使い分け
- 文脈や前後の表現との調和を意識
- 句読点の配置と表現の関係性への配慮
- 前後の言葉との組み合わせの最適化
- 文書全体のトーンの一貫性維持
これらの要素を意識することで、より効果的な表現が可能になります。
印象管理のコツ
適切な敬語使用は、ビジネスパーソンとしての印象を大きく左右します。
より良い印象を与えるためのテクニックを紹介します。
- 一貫性のある表現使用を心がける
- 過度な丁寧表現は避けてナチュラルに
- 文章の流れを重視した表現選択
- 読み手の立場に立った表現調整
- 状況認識に基づく適切な表現選択
これらのポイントを意識することで、より好印象な文書作成が可能です。
まとめ
ビジネスメールにおける「致します」「いたします」「します」の使い分けは、ビジネスコミュニケーションの基本スキルです。
以下のポイントを押さえることで、適切な使用が可能になります
- 相手との関係性を第一に考える
- 文書の種類や目的に応じて選択する
- 一貫性のある使用を心がける
- 過度な敬語は避ける
- 定期的な見直しと改善を行う
これらの基本を押さえた上で、自身のコミュニケーションスタイルを確立していくことが重要です。
本記事で紹介した例文やテンプレートを活用しながら、より効果的なビジネスコミュニケーションを実践してください。
よくある質問(FAQ)
ビジネスメールでの敬語使用に関して、多くの方が抱える疑問にお答えします。
これらの質問は、実務での具体的な場面で特に重要となるポイントを含んでいます。
以下の回答を参考に、より適切な表現を選択してください。
Q1: 「致します」と「いたします」は併用しても良いですか?
A: 基本的には、一つの文書内では統一することをお勧めします。
ただし、特に形式的な文書と本文で使い分ける場合は、意図的な使い分けも可能です。
Q2: 社内メールではどの表現が適切ですか?
A: 基本的には「いたします」または「します」が適切です。
部署全体への連絡な場合は「いたします」、日常的な1対1のやり取りでは「します」が推奨されます。
Q3: クライアントへの謝罪メールでは必ず「致します」を使用すべきですか?
A: はい、謝罪の場面では「致します」を使用することで、より誠意が伝わります。
特にクライアント向けの謝罪では、必ず「致します」を使用しましょう。
Q4: 「させていただきます」の使用は適切ですか?
A: 提案や申し出の場面では適切です。
ただし、過剰な使用は避け、必要な場面に限定することをお勧めします。
Q5: 英文が混ざる場合の敬語はどうすべきですか?
A: 文書全体の基調となる敬語レベルに合わせます。
英文の前後で敬語レベルが急に変わることは避けましょう。
Q6: メールの件名では「致します」は使用すべきですか?
A: 件名では通常、簡潔さを重視するため「致します」は省略することが多いです。
ただし、お詫びのメールなど、特に形式的な場合は使用も可能です。
Q7: 部下からのメールで「致します」が使われた場合、指導が必要ですか?
A: 過剰な敬語使用として、より自然な「いたします」や「します」の使用を推奨することは有効です。
ただし、TPOに応じた使用であれば問題ありません。
Q8: 長文メールでの使い分けのコツはありますか?
A: 文書の性質に応じて基本となる表現を決め、一貫して使用することをお勧めします。
特に重要な報告や依頼の部分では、より丁寧な表現を心がけましょう。