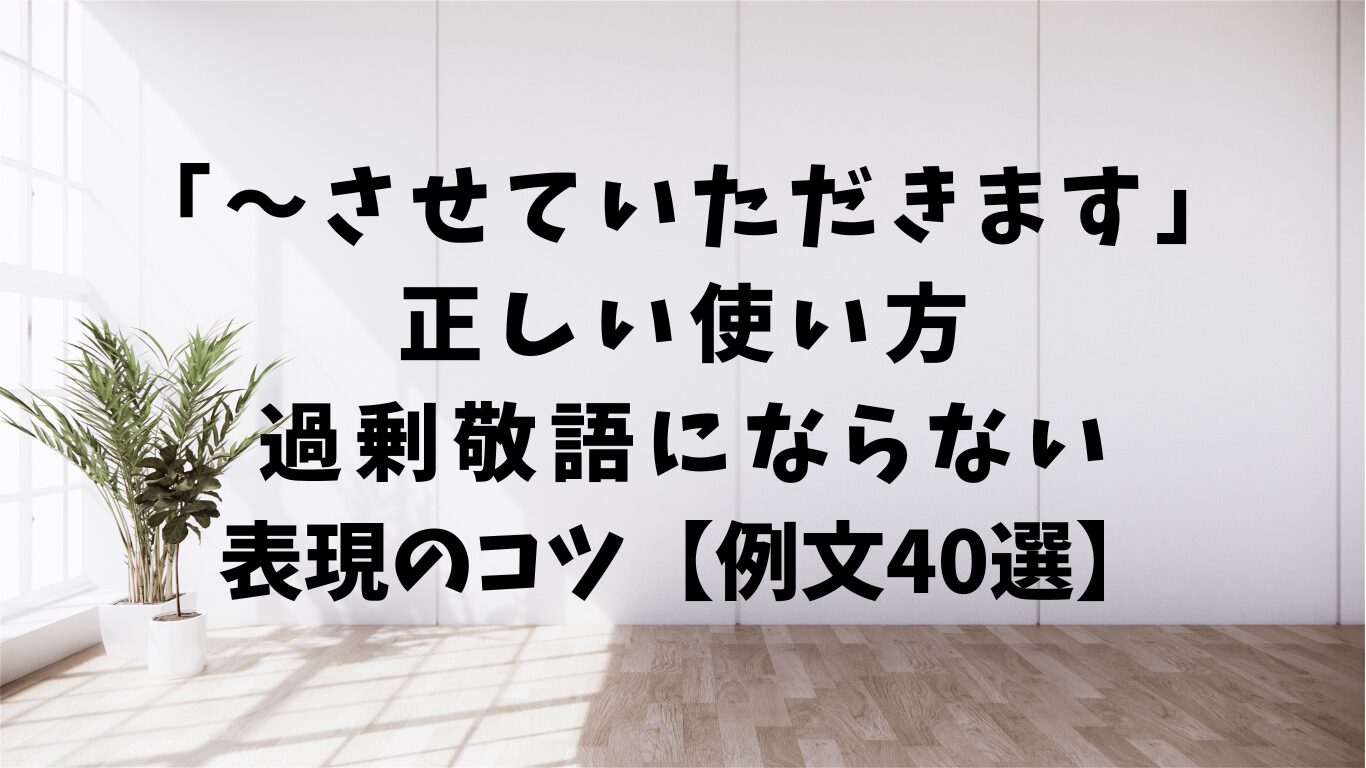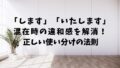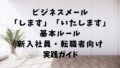ビジネスシーンで頻繁に使用される「させていただきます」。
適切に使用すれば丁寧さを表現できる便利な敬語ですが、使いすぎると過剰敬語となってしまいます。
特に新入社員や若手社会人は、丁寧すぎる表現を使ってしまい、かえって相手に違和感を与えてしまうケースが少なくありません。
本記事では、「させていただきます」の正しい使い方と、シーン別の具体的な例文を40個ご紹介します。
これらの例文を参考に、適切な敬語表現をマスターしましょう。
この記事でわかること
- 「させていただきます」が適切な場面と不適切な場面の違い
- 過剰敬語を避けるための具体的な言い換え方法
- シーン別の正しい「させていただきます」の使用例
- 上司や取引先との文章での効果的な使い分け方
- メールや文書での「させていただきます」の基本ルール
「させていただきます」の正しい使い方を40の実例で確認しながら、過剰敬語を避け、適切な敬語表現をマスターできます
- すぐに使える「させていただきます」例文集
- シーン別「させていただきます」の使い分け
- 「させていただきます」の基本的な使い方のポイント
- 状況別の適切な言い換え表現
- 過剰敬語を避けるためのテクニック
- よくある間違いと修正例
- まとめ:適切な「させていただきます」使用のために
- よくある質問(FAQ)
- Q1:メールの締めくくりで「よろしくお願いさせていただきます」は適切でしょうか?
- Q2:「確認させていただきました」は使っても良いのでしょうか?
- Q3:取引先へのメールでは全て「させていただきます」にした方が丁寧ですか?
- Q4:「ご説明させていただきます」は二重敬語になりますか?
- Q5:上司への報告では必ず「させていただきます」を使うべきですか?
- Q6:「お送りさせていただきます」は正しい表現ですか?
- Q7:社内文書ではどのレベルの敬語を使うべきですか?
- Q8:クレーム対応では「させていただきます」を多用しても良いですか?
- Q9:「検討させていただきます」は使わない方が良いですか?
- Q10:「ご連絡させていただきます」は避けるべきですか?
すぐに使える「させていただきます」例文集
ビジネスシーンでの「させていただきます」の具体的な使用例をご紹介します。
メール、社内文書、取引先との文書、謝罪文書など、様々な場面での適切な使い方を、実践的な例文とともに解説していきます。
これらの例文を参考に、状況に応じた効果的な敬語表現を身につけることができます。
ビジネスメールでの基本的な使用例
ビジネスメールにおける「させていただきます」は、特に依頼や報告の場面で頻繁に使用されます。
相手に配慮を示しながら、自分の行動を丁寧に伝える際に効果的です。
ただし、使用頻度が高くなりすぎないよう注意が必要です。
▽例文・テンプレートパート
■ アポイント依頼
「来週の水曜日15時にお伺いさせていただきたく存じます」
■ 資料送付の報告
「本日、ご依頼の資料をメールに添付させていただきました」
■ 提案・企画の提出
「新企画書を添付させていただきましたので、ご確認いただけますと幸いです」
■ 面談のお礼
「本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。議事録を送付させていただきます」
■ スケジュール調整
「打ち合わせの日程を、改めて調整させていただきたく存じます」
メールでは1通につき「させていただきます」の使用は1-2回までを目安とします。
特に重要な行動や相手の許可が必要な場面に限定して使用することで、丁寧さを保ちながら過剰な敬語を避けることができます。
社内文書での適切な使用例
社内文書では、部署間のコミュニケーションや会議資料など、フォーマルさが求められる場面で使用します。
ただし、日常的なやり取りでは使用を控え、必要な場面で効果的に活用することが重要です。
▽例文・テンプレートパート
■ 会議資料での使用
「第3四半期の営業報告をさせていただきます」
「新規プロジェクトの概要説明をさせていただきます」
■ 部署間の依頼文書
「システム改修に伴い、以下の日程で作業を実施させていただきます」
「貴部署のご協力をいただきたく、ご相談させていただきます」
■ 社内報告書
「部内異動について、下記の通りご報告させていただきます」
「研修結果を取りまとめ、ご報告させていただきます」
■ 稟議書
「新規設備の導入について、ご検討いただきたく申請させていただきます」
社内文書では、特に部署を超えたコミュニケーションや重要な報告の際に使用します。
ただし、同じ部署内での日常的なやり取りでは、より簡潔な表現を心がけましょう。
取引先との文書での使用例
取引先とのビジネス文書では、特に契約や重要な取り決めに関する場面で「させていただきます」を使用します。
相手企業への敬意を示しながら、確実な意思表示を行うことが重要です。
▽例文・テンプレートパート
■ 見積書送付時
「下記の通り、お見積りをさせていただきます」
「修正見積書を送付させていただきます」
■ 契約書関連
「契約書の最終案を送付させていただきます」
「契約条項の変更箇所を下記の通りまとめさせていただきました」
■ 納品通知
「本日、商品を納品させていただきました」
「検品結果報告書を添付させていただきます」
■ 提案書提出
「新サービスのご提案をさせていただきます」
「導入スケジュール案を提出させていただきます」
取引先との文書では、特に初回の取引や重要な意思決定に関わる場面で使用します。
ただし、日常的な進捗報告などでは、「いたします」など、より簡潔な敬語表現を適宜使用することをお勧めします。
謝罪・お詫び文書での使用例
謝罪文書では、深い反省の意を示しながら、今後の対応や改善策を丁寧に説明する必要があります。
「させていただきます」は、特に対応策や改善案を述べる際に効果的に使用できます。
▽例文・テンプレートパート
■ トラブル発生時の謝罪
「早急に原因究明と対策を実施させていただきます」
「代替品を本日中に発送させていただきます」
■ 納期遅延の謝罪
「納期を○月○日に変更させていただきたく、お願い申し上げます」
「進捗状況を毎日報告させていただきます」
■ 品質不具合の謝罪
「全品回収の対応をさせていただきます」
「検査体制の見直しをさせていただきます」
■ 対応の遅れへの謝罪
「本日中に詳細な報告書を提出させていただきます」
「改めて正式なご回答をさせていただきます」
謝罪文書での「させていただきます」は、主に今後の対応策を説明する際に使用します。
謝罪自体は「申し訳ございません」「お詫び申し上げます」などの表現を使用し、安易に「謝罪させていただきます」とはしないよう注意が必要です。
シーン別「させていただきます」の使い分け
「させていただきます」は、相手や状況によって使い方を適切に変える必要があります。
上司・先輩、取引先、謝罪時など、それぞれのシーンに応じた効果的な使用方法を具体的に説明します。
これにより、より自然で円滑なビジネスコミュニケーションが実現できます。
上司・先輩への使用シーン
上司や先輩に対する「させていただきます」の使用は、特に許可や承認を得る場面で重要です。
過度な使用は避けつつ、適切な場面で効果的に使うことで、礼儀正しさを示すことができます。
- 決裁申請時:「申請書を提出させていただきます」で適切な丁寧さを表現
- 業務報告時:「進捗をご報告させていただきます」で報告の意を丁寧に伝達
- 相談時:「ご相談させていただきたく存じます」で謙虚な姿勢を表現
- 休暇申請時:「来週休暇を取得させていただきたく」で許可を請う形を示す
- 修正依頼時:「再度確認させていただきます」で丁寧に確認意向を伝える
上司への報告や連絡では、日常的なやり取りでは「します」「いたします」を基本とし、重要な承認や許可が必要な場面に「させていただきます」を使用するのが効果的です。
社外の取引先への使用シーン
取引先との関係では、特に初回の商談や重要な提案時に「させていただきます」を使用します。
ビジネス上の信頼関係を構築しながら、適切な距離感を保つことが重要です。
- 初回訪問時:「お伺いさせていただきます」で訪問の意を丁寧に表現
- 提案説明時:「ご提案させていただきます」で提案内容を丁重に示す
- 見積提示時:「お見積りをさせていただきます」で料金提示を丁寧に実施
- 契約締結時:「契約書を送付させていただきます」で正式な手続きを表現
- 納品報告時:「納品させていただきます」で完了報告を確実に伝達
取引先との継続的なやり取りでは、状況に応じて「いたします」などの基本的な敬語表現も使い分けることで、自然な印象を与えることができます。
謝罪時の使用シーン
謝罪時の「させていただきます」は、主に今後の対応策や改善案を説明する場面で使用します。
謝罪の言葉自体には使用を避け、誠意ある対応を示す表現として活用します。
- 対応策提示:「至急対応させていただきます」で迅速な解決を約束
- 改善案説明:「改善策を実施させていただきます」で具体的な行動を提示
- 経過報告:「進捗を報告させていただきます」で継続的な対応を表明
- 代替案提示:「代替案をご提案させていただきます」で解決策を提示
- 再発防止:「再発防止策を講じさせていただきます」で今後の対策を説明
謝罪の場面では、「申し訳ございません」「お詫び申し上げます」などの明確な謝罪表現を使用し、その後の対応策を説明する際に「させていただきます」を適切に使用することで、誠意ある対応を示すことができます。
「させていただきます」の基本的な使い方のポイント
「させていただきます」を正しく使用するための基本的な考え方と原則を解説します。
本来の意味や用途を理解し、正しい敬語としての使用条件を把握することで、過剰敬語を避けた適切な表現が可能になります。
「させていただきます」の本来の意味と用途
「させていただきます」は、相手や第三者から許可や承認を得て行動する際に使用する敬語表現です。
相手に対する感謝や配慮を示しながら、自分の行動を謙虚に伝える機能を持っています。
- 許可の意味:相手の承諾を得ての行動であることを示す表現として使用
- 謙譲の意味:自分の行動を低めて述べる謙譲語としての機能を持つ
- 感謝の意味:相手の好意や配慮への感謝の気持ちを込めた表現として有効
- 丁寧さの程度:「いたします」より丁寧で、最も敬意度の高い表現の一つ
- 使用の基準:相手の利益や許可が関係する場面での使用が基本
本来の意味を理解することで、過剰な使用を避け、必要な場面で効果的に活用することができます。
特に、相手からの許可や承認が明確な場面での使用が望ましいです。
正しい敬語としての使用条件
「させていただきます」を正しく使用するには、特定の条件を満たす必要があります。
相手との関係性、状況の重要度、行動の性質などを考慮し、適切な使用場面を見極めることが重要です。
- 相手の許可:明示的または暗黙的な承認が必要な場面での使用
- 行動の影響:相手に影響を与える行動の説明時に適切
- フォーマル度:公式な文書や重要な場面での使用が効果的
- 権限関係:上位者や取引先など、承認を得る必要がある相手との対話
- 社会的文脈:ビジネスマナーとして認められた場面での使用
これらの条件を意識することで、適切な使用と不適切な使用を区別し、より効果的なコミュニケーションを実現することができます。
過剰敬語となるケースの見分け方
過剰な「させていただきます」の使用は、かえってコミュニケーションを不自然にする可能性があります。
以下のポイントを確認することで、過剰使用を防ぐことができます。
- 単純作業:日常的な業務や単純な作業への不必要な使用を避ける
- 重複使用:一つの文書内での過度な繰り返し使用に注意
- 自然な流れ:文脈上不自然な位置での使用を控える
- 主体性:自己判断で行える行動への不要な使用を避ける
- 必然性:相手の許可や承認が不要な場面での使用を控える
過剰使用を避けるためには、各場面で本当に「させていただきます」が必要かを判断し、必要に応じて「いたします」や「します」など、より適切な表現に置き換えることが重要です。
状況別の適切な言い換え表現
「させていただきます」の代わりに使える適切な表現のバリエーションを紹介します。
「いたします」「承ります」「します」など、状況に応じた言い換え方を学ぶことで、より自然で効果的な敬語表現を実現できます。
「いたします」での言い換えが適切な場面
「いたします」は、「させていただきます」より丁寧さの程度が一段階低い敬語表現です。
日常的なビジネスシーンでは、この表現で十分な敬意を示すことができ、より自然なコミュニケーションが可能です。
- 定例報告:「週次報告をいたします」で十分な丁寧さを表現
- 通常連絡:「本日中に納品いたします」で適切な敬意を示す
- 一般対応:「ただちに確認いたします」で迅速な対応を表現
- 業務連絡:「明日までに完了いたします」で期限を明確に伝達
- 基本案内:「ご案内いたします」で情報提供を丁寧に実施
特に社内での日常的なやり取りや、継続的な取引先とのコミュニケーションでは、「いたします」を基本とすることで、適度な丁寧さを保ちながら円滑な意思疎通が可能です。
「承ります」での言い換えが適切な場面
「承ります」は、相手からの依頼や要望を受ける際に使用する謙譲語です。
「させていただきます」の代わりに使用することで、簡潔かつ明確に受諾の意思を示すことができます。
- 依頼受付:「ご依頼承ります」でシンプルに受諾を表現
- 注文対応:「ご注文承ります」で明確に受注意思を示す
- 要望対応:「ご要望承ります」で相手の意向を受け入れる
- 相談受付:「ご相談承ります」で対応意思を示す
- 確認作業:「確認を承ります」で作業実施を伝える
特に顧客対応や受付業務など、相手からの要望を受ける場面では、「承ります」を使用することで、簡潔かつ プロフェッショナルな印象を与えることができます。
シンプルな「します」で十分な場面
社内の日常的なコミュニケーションや、親しい取引先との連絡では、「します」というシンプルな表現で十分な場合が多くあります。
過度な敬語使用を避け、明快な意思疎通を図ることが重要です。
- 部内連絡:「資料を作成します」で簡潔に意図を伝達
- 進捗報告:「明日までに完了します」で明確に期限を示す
- 日常業務:「確認して返信します」で素直に対応を伝える
- 一般連絡:「午後から参加します」で簡潔に予定を共有
- 作業報告:「すぐに対応します」で即時の行動を示す
特に同じ部署内でのやり取りや、日常的な業務連絡では、「します」を使うことで、より自然で効率的なコミュニケーションを実現できます。
過剰敬語を避けるためのテクニック
過剰な「させていただきます」の使用は、かえってコミュニケーションを不自然にしてしまいます。
簡潔な表現への書き換え方や自然な敬語表現のコツを理解することで、より効果的なビジネス文書の作成が可能になります。
簡潔な表現への書き換え方
過剰な「させていただきます」を避けるためには、文章を簡潔に書き換えることが効果的です。
特に、重複した敬語表現や複雑な言い回しを見直し、明確で分かりやすい表現にすることが重要です。
- 二重敬語:「ご確認させていただきます」→「確認いたします」へ簡素化
- 冗長表現:「検討させていただきます」→「検討します」でシンプルに
- 重複表現:「ご相談させていただきます」→「相談いたします」に統一
- 複雑表現:「実施させていただきます」→「実施します」へ単純化
- 長文表現:「送付させていただきます」→「送ります」で簡潔に
文章を簡潔にすることで、むしろ相手に対する誠意や真摯さが伝わりやすくなります。
必要以上に丁寧な表現を重ねないことが、かえってプロフェッショナルな印象を与えます。
自然な敬語表現のコツ
自然な敬語表現を実現するには、場面や状況に応じて適切な表現レベルを選択することが重要です。
相手との関係性、文書の目的、コミュニケーションの文脈を考慮し、最適な表現を選ぶことがポイントです。
- 状況判断:公式文書か日常連絡かで表現レベルを使い分ける
- 関係性重視:相手との距離感に応じて敬語レベルを調整する
- 一貫性保持:文書内で敬語レベルを統一して使用する
- 簡潔性重視:用件が明確に伝わる表現を優先する
- 自然な流れ:文脈に沿った自然な敬語表現を選択する
過度に丁寧な表現を避け、状況に応じた適切な敬語レベルを選択することで、より自然で効果的なコミュニケーションが実現できます。
よくある間違いと修正例
ビジネスシーンでよく見かける「させていただきます」の誤用パターンと、その適切な修正方法を解説します。
典型的な間違いを理解し、文脈に応じた適切な修正方法を身につけることで、より洗練された文章作成が可能になります。
典型的な過剰敬語のパターン
過剰敬語の多くは、「させていただきます」を不必要に使用するパターンで発生します。
特に、単純な行動や自己決定可能な事項に対して使用するケースが目立ちます。
これらを適切に修正することで、より自然な文章になります。
- 自発的行動:「退席させていただきます」→「退席いたします」が適切
- 単純作業:「コピーさせていただきます」→「コピーします」で十分
- 日常報告:「出勤させていただきます」→「出勤します」が自然
- 一般連絡:「電話させていただきます」→「お電話いたします」が適切
- 基本動作:「着席させていただきます」→「着席します」で十分
過剰敬語を避けることで、むしろ明確で誠実な印象を与えることができます。
必要以上に丁寧にする必要はありません。
文脈に応じた適切な修正方法
文脈や状況に応じて、最適な表現レベルは変化します。
特に重要なのは、相手との関係性、文書の目的、コミュニケーションの場面を総合的に判断することです。
適切な修正により、より効果的な伝達が可能になります。
- 社内文書:「提出させていただきます」→「提出します」へ簡素化
- 取引先連絡:「訪問させていただきます」→「お伺いいたします」が適切
- 上司への報告:「説明させていただきます」→「ご説明いたします」に
- 一般通知:「案内させていただきます」→「ご案内いたします」が自然
- 日常業務:「確認させていただきます」→「確認します」で十分
状況に応じた適切な表現レベルを選択することで、より自然で効果的なコミュニケーションが可能になります。
過剰な丁寧さは避け、相手に応じた適切な敬語使用を心がけましょう。
まとめ:適切な「させていただきます」使用のために
「させていただきます」の適切な使用は、ビジネスコミュニケーションの質を大きく左右します。
本記事で解説した内容を実践することで、過剰敬語を避けながら、適切な敬意を示すことができます。
以下に、最も重要なポイントをまとめます
■ 基本的な使い分けのルール
- 相手からの許可や承認が必要な場面で使用
- 重要な報告や提案時に限定して使用
- 日常的な業務連絡では「いたします」「します」を基本に
■ 効果的な使用のポイント
- 一つの文書で使用する回数を必要最小限に
- 文脈や相手との関係性に応じて適切な表現を選択
- 過剰な丁寧さよりも、明確で誠実な伝達を重視
■ 今後の実践に向けて
- 本記事の例文を参考に、自分の文章をチェック
- 必要に応じて適切な言い換えを実施
- 状況に応じた使い分けを意識的に練習
よくある質問(FAQ)
「させていただきます」の使用に関して、多くのビジネスパーソンが疑問を感じる点があります。
特に新入社員や若手社員から多く寄せられる質問について、具体的な回答と例文を交えて解説します。
これらの回答を参考に、適切な敬語使用を身につけていきましょう。
Q1:メールの締めくくりで「よろしくお願いさせていただきます」は適切でしょうか?
A:この表現は過剰敬語となります。
「よろしくお願い申し上げます」や「よろしくお願いいたします」が適切です。「お願い」という言葉自体に謙譲の意味が含まれているためです。
Q2:「確認させていただきました」は使っても良いのでしょうか?
A:単純な確認作業の場合は「確認いたしました」で十分です。
ただし、相手の許可を得て特別な確認を行った場合は「確認させていただきました」も適切です。
Q3:取引先へのメールでは全て「させていただきます」にした方が丁寧ですか?
A:過剰な使用は避けるべきです。
重要な提案や申請の場面に限定し、通常の業務連絡では「いたします」を基本とすることで、自然な印象を与えられます。
Q4:「ご説明させていただきます」は二重敬語になりますか?
A:「ご説明いたします」が正しい表現です。
「ご」という接頭語がある場合は、「いたします」を使用するのが基本的なルールです。
Q5:上司への報告では必ず「させていただきます」を使うべきですか?
A:日常的な報告では「報告いたします」で十分です。
特別な承認を得ての報告や重要案件の場合のみ「報告させていただきます」を使用しましょう。
Q6:「お送りさせていただきます」は正しい表現ですか?
A:「送付いたします」や「お送りいたします」が適切です。
「お」と「させていただく」を同時に使用すると過剰な敬語表現となります。
Q7:社内文書ではどのレベルの敬語を使うべきですか?
A:部署間の公式文書では「いたします」を基本とし、特に重要な申請や報告の場合のみ「させていただきます」を使用することをお勧めします。
Q8:クレーム対応では「させていただきます」を多用しても良いですか?
A:謝罪自体は「申し訳ございません」を使い、対応策を説明する際に必要に応じて「させていただきます」を使用するのが適切です。
ただし、過度な使用は避けましょう。
Q9:「検討させていただきます」は使わない方が良いですか?
A:通常は「検討いたします」で十分です。
ただし、特別な承認を得て検討する場合や、重要案件の場合は「検討させていただきます」も適切です。
Q10:「ご連絡させていただきます」は避けるべきですか?
A:「ご連絡いたします」で十分です。
ただし、特別な事情がある場合や重要な連絡の場合は「ご連絡させていただきます」も使用可能です。