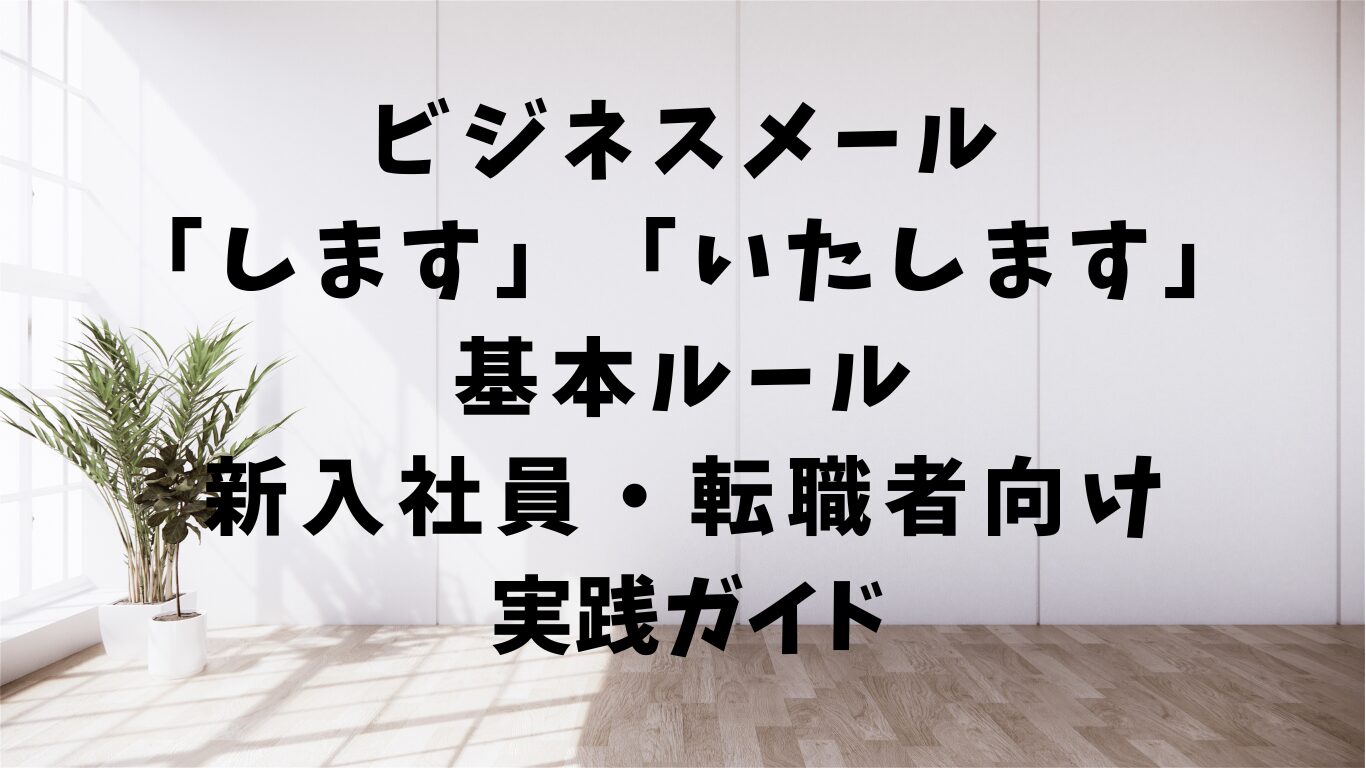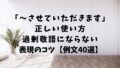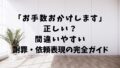ビジネスメールで「します」と「いたします」、どちらを使えばよいか迷った経験はありませんか?
特に新入社員や転職者にとって、この使い分けは悩ましい問題です。
使い方を間違えると失礼な印象を与えたり、逆に過剰な敬語として受け取られたりする可能性があります。
本記事では、「します」「いたします」の基本的な使い分けから、実践的なビジネスメールの書き方まで、具体例を交えて解説します。
これを読めば、状況に応じた適切な表現が自然に選べるようになります。
この記事でわかること
- 「します」「いたします」の基本的な違いと使い分けのルール
- ビジネスメールで使用する際の基本的なガイドライン
- 社内メールと社外メールそれぞれの適切な使用方法
- 役職や状況に応じた使い分けのポイント
- よくある間違いとその改善方法
新入社員・転職者向けに「します」「いたします」の使い分けを徹底解説。
実践的な例文とテンプレートで、すぐにビジネスメールに活用できます。
ビジネスメールにおける「します」「いたします」の基本
ビジネスメールにおける「します」と「いたします」の使い分けは、メールの印象を大きく左右します。
ここでは、基本的な違いから実践的な使用方法まで、具体例を交えて解説します。
この基本を押さえることで、適切な敬語使用の土台を築くことができます。
「します」「いたします」の基本的な違い
ビジネスメールにおいて、「します」は基本的な丁寧語、「いたします」は敬語表現として使用されます。
両者の違いは単なる丁寧さのレベルだけでなく、相手との関係性や状況に応じた適切な距離感を表現できる点にあります。
- 基本の使い分け:社内は「します」、社外は「いたします」を基本とする
- 上下関係の考慮:目上の人には「いたします」、同僚には「します」を使用
- フォーマリティ:公式文書は「いたします」、日常的な連絡は「します」を選択
- 一貫性の重要性:同じメール内での使い分けは統一感を持たせる
- 時と場合:緊急時や簡潔さが求められる場合は「します」を優先
ただし、これらは絶対的なルールではなく、社風や業界の特性によって異なる場合があります。
特に新入社員は最初の数ヶ月は周囲の使用傾向を観察することをお勧めします。
使い分けの3つの重要ポイント
「します」「いたします」の使い分けには、相手との関係性、メールの目的、文書の性質という3つの重要な判断基準があります。
これらの要素を適切に見極めることで、違和感のない自然な文章を作成できます。
- 相手との距離感:役職や親密度に応じて適切な表現を選択する
- メールの重要度:重要な案件ほど「いたします」を使用する傾向に
- 文書の正式性:社内規定や契約関連は「いたします」を基本とする
- コミュニケーション頻度:日常的なやり取りは「します」で十分
- 緊急性の考慮:即時性が求められる場合は「します」を優先的に使用
これらのポイントは状況によって優先順位が変わることがあります。
特に重要な案件の場合は、普段「します」を使用する相手でも「いたします」に切り替えるなど、柔軟な対応が必要です。
メールの種類による使い分けの基準
ビジネスメールは、依頼・報告・確認・お詫びなど、目的によって求められる丁寧さのレベルが異なります。
メールの種類を正しく見極め、適切な表現を選択することで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
- 依頼メール:原則として「いたします」を使用し、謙虚な姿勢を示す
- 報告メール:内容の重要度に応じて使い分ける判断が必要
- 確認メール:簡潔さを重視する場合は「します」を選択
- お詫びメール:「いたします」を基本とし、誠意を示す
- 定型連絡:部署や案件の慣習に従って統一的に使用
メールの種類による基準は、送信先や案件の重要度によって変更が必要な場合があります。
特に複数の要素が絡む場合は、より丁寧な表現を選択することで安全です。
「します」「いたします」の正しい使用手順
メールを作成する際の具体的な手順を理解することで、適切な表現選択がより確実になります。
ここでは、実際のメール作成時に意識すべきステップを、順を追って解説していきます。
これらの手順を意識することで、自然な敬語表現が身につきます。
宛先の確認と適切な敬語レベルの選択
メール作成の最初のステップは宛先の確認です。
宛先の役職、所属、関係性を正確に把握することで、適切な敬語レベルを選択できます。
特に複数の宛先がある場合は、最も地位の高い人に合わせた表現を使用します。
- 役職確認:相手の正確な役職名と立場を必ず確認する
- 所属部署:同じ会社でも部署が異なれば丁寧な表現を選ぶ
- CC確認:CCに上司や取引先が含まれる場合は格上げする
- 過去の例:過去のやり取りがある場合は表現レベルを参考に
- 社内規定:会社のメールマナー規定があれば必ず順守する
宛先が複数の場合、全員に適切な敬語レベルを維持することが重要です。
特に社外の人が含まれる場合は、原則として「いたします」を使用し、統一した丁寧さを保ちましょう。
文脈に応じた表現の選び方
メール本文の文脈に応じて、「します」「いたします」を適切に選択することが重要です。
特に、依頼・報告・お詫びなど、文章の意図によって求められる丁寧さのレベルが異なることを理解しましょう。
- 依頼時:相手の負担が大きいほど「いたします」を使用する
- 報告時:重要度や緊急性に応じて使い分ける
- 確認時:簡潔さを重視する場合は「します」を選択する
- 謝罪時:必ず「いたします」を使用し、誠意を示す
- 日常連絡:通常の業務連絡は「します」で十分
同じメール内でも、段落や文の内容によって適切な表現が変わることがあります。
ただし、過度な表現の混在は避け、全体的な統一感を保つことが重要です。
文末表現との組み合わせ方
「します」「いたします」は、文末表現と組み合わせることで、より適切な丁寧さのレベルを表現できます。
特に、「お願いします」「よろしくお願いいたします」などの定型句との整合性に注意が必要です。
- 基本パターン:文中と文末の丁寧さレベルを揃える
- 結びの表現:「よろしくお願いします」と「いたします」の使い分け
- 謝罪表現:「申し訳ございません」との組み合わせ方
- 感謝表現:「ありがとうございます」との調和
- 質問表現:「でしょうか」との適切な組み合わせ
文末表現は、メール全体の印象を大きく左右します。
特に結びの言葉は、相手との関係性や文書の性質を考慮し、適切な組み合わせを選択することが重要です。
社内・社外別の使い分けガイド
社内と社外では、「します」「いたします」の使用基準が大きく異なります。
それぞれの場面における適切な使い分けを理解することで、より効果的なビジネスコミュニケーションが実現できます。
社内メールでの基本ルール
社内メールでは、基本的に「します」を使用しますが、状況や相手によって「いたします」の使用も必要です。
特に役職や部署間の関係性を考慮し、適切な敬語レベルを選択することが重要です。
- 上司宛:原則として「いたします」を使用する
- 同僚間:基本的に「します」で統一する
- 部署間:相手部署の立場を考慮して選択する
- 全社向:公式性の高い内容は「いたします」を使用
- 緊急時:状況に応じて「します」を活用する
社内メールでも、案件の重要度や公式性によって使い分けが必要です。
特に新入社員は、最初は丁寧な表現を心がけ、徐々に周囲の様子を見ながら調整していきましょう。
社外メールでの注意点
社外メールでは、原則として「いたします」を使用します。
取引先との関係性構築や維持において、適切な敬語使用は特に重要です。
初回のコンタクトでは特に丁寧な表現を心がけましょう。
- 初回連絡:必ず「いたします」を使用する
- 継続取引:関係性が深まっても基本は維持する
- クレーム対応:より丁寧な表現を心がける
- 定期連絡:慣習的な表現レベルを保つ
- 緊急連絡:状況を考慮しつつ丁寧さを保つ
社外メールでは、過度なカジュアル化を避け、常に一定の距離感を保つことが重要です。
ただし、業界の特性や取引先の社風によっては、柔軟な対応が必要な場合もあります。
部署間コミュニケーションの留意点
部署間のコミュニケーションでは、組織内の位置づけや案件の性質によって適切な表現を選択する必要があります。
特に、権限や責任の所在を意識した表現選びが重要です。
- 管理部門:より丁寧な「いたします」を基本とする
- 同格部署:状況に応じて「します」を使用
- プロジェクト:案件の重要度で使い分ける
- 定例報告:部署間の慣習に従う
- 協力依頼:丁寧な表現を心がける
部署間のコミュニケーションでは、組織図上の関係性だけでなく、実際の業務フローや権限関係も考慮して表現を選択することが重要です。
シーン別例文・テンプレート集
実際のビジネスシーンで使用できる具体的な例文とテンプレートを紹介します。
これらを参考に、状況に応じた適切な表現を選択し、効果的なコミュニケーションを実現しましょう。
各シーンに合わせた具体的な例文とその使い分けのポイントを確認していきます。
依頼メールの書き方
依頼メールでは、相手への負担を考慮し、適切な敬語レベルを選択することが重要です。
特に初めての依頼や重要な案件の場合は、「いたします」を基本とし、謙虚な姿勢で依頼を行います。
- 重要依頼:「ご検討いただきますようお願いいたします」の使用
- 日常依頼:「確認をお願いします」など状況で使い分け
- 期限設定:「〇日までに送付いたします」の形式を統一
- 資料提供:「添付させていただきます」との組み合わせ
- フォロー:「お手数をおかけいたします」での締めくくり
依頼の内容や重要度によって、「いたします」と「します」を適切に使い分けることが重要です。
特に相手の負担が大きい依頼の場合は、より丁寧な表現を心がけましょう。
報告メールの書き方
報告メールでは、内容の重要度や報告先の役職に応じて、適切な敬語レベルを選択します。
特に重要な進捗報告や結果報告の場合は、「いたします」を使用し、正式な印象を与えましょう。
- 進捗報告:「以下のとおり報告いたします」を基本に
- 結果報告:「結果をご報告いたします」で統一感を
- 定期報告:「週次報告をさせていただきます」を活用
- 簡易報告:「ご連絡します」など状況で簡略化
- 遅延報告:「遅れて申し訳ございません」との組み合わせ
報告内容の重要度に応じて、表現レベルを調整することが重要です。
特に上位者への報告や複数の関係者が含まれる場合は、より丁寧な表現を選択しましょう。
確認メールの書き方
確認メールは、用件の性質や緊急性によって表現を使い分けます。
重要な確認事項の場合は「いたします」を使用し、日常的な確認では「します」を活用して、スムーズなコミュニケーションを図ります。
- 重要確認:「ご確認いただきますようお願いいたします」
- 簡易確認:「確認させていただきます」で十分な場合も
- 事実確認:「間違いがないか確認します」を活用
- 再確認:「再度確認させていただきます」の使用
- 期限確認:「期日の確認をさせていただきます」
確認メールは、用件の緊急性や重要度によって、適切な表現レベルを選択することが重要です。
特に複数の関係者に確認を行う場合は、より丁寧な表現を使用しましょう。
お詫びメールの書き方
お詫びメールでは、必ず「いたします」を使用し、誠意を示す必要があります。
謝罪の言葉と組み合わせることで、より丁寧な印象を与え、信頼関係の修復を図ることができます。
- 謝罪表明:「深くお詫び申し上げます」との組み合わせ
- 原因説明:「要因を説明させていただきます」を使用
- 対応報告:「早急に対応いたします」で誠意を示す
- 再発防止:「再発防止に努めさせていただきます」
- 今後の対応:「今後は細心の注意を払います」
お詫びメールでは、謝罪の真摯さを表現するため、終始丁寧な表現を維持することが重要です。
特に、今後の対応や改善策を説明する際も、丁寧な表現を保ちましょう。
役職・立場による使い分け実践例
役職や立場によって「します」「いたします」の使い分けは大きく異なります。
ここでは、具体的な役職・立場ごとの適切な使用例を紹介し、実践的な表現方法を身につけていきましょう。
上司・先輩への使用例
上司や先輩に対するメールでは、基本的に「いたします」を使用します。
ただし、日常的なコミュニケーションや緊急性の高い案件では、状況に応じて「します」を使用することも可能です。
- 公式報告:必ず「いたします」を使用し、礼儀正しさを示す
- 日常連絡:親密度に応じて「します」の使用も検討する
- 緊急報告:状況によっては「します」で簡潔に伝える
- CC対応:上司がCCの場合は「いたします」を選択する
- 定期報告:部署の慣習に従った表現を統一して使用
上司や先輩との関係性や、普段のコミュニケーションスタイルによって適切な表現は変わります。
最初は丁寧すぎる程度が適切で、徐々に相手に合わせて調整していきましょう。
同僚・部下への使用例
同僚や部下とのメールコミュニケーションでは、基本的に「します」を使用します。
ただし、公式な文書や重要な指示を出す際には、状況に応じて「いたします」を使用することで、適切な距離感を保ちます。
- 通常連絡:「します」を基本とし、親しみやすさを表現
- 全体通知:重要度に応じて「いたします」を使用する
- 指示発信:立場に応じた適切な表現レベルを選択
- 相談時:気軽さを示すため「します」を優先する
- 公式文書:案件の性質に応じて使い分けを検討
同僚や部下とのコミュニケーションでも、場面や状況によって適切な表現は変わります。
特に複数の宛先がある場合は、全体のバランスを考慮した表現を選びましょう。
取引先への使用例
取引先へのメールでは、原則として「いたします」を使用します。
特に新規取引先や重要な案件の場合は、より丁寧な表現を心がけ、誠実な印象を与えることが重要です。
- 初回連絡:必ず「いたします」を使用し、礼儀正しさを示す
- 定期連絡:関係性が構築されても基本は「いたします」
- 重要案件:より丁寧な表現との組み合わせを意識する
- クレーム対応:誠意を示すため「いたします」を徹底
- 緊急連絡:状況を考慮しつつ、基本は「いたします」
取引先との関係性が深まっても、基本的な敬語レベルは維持することが重要です。
ただし、業界の特性や取引先の社風によっては、より柔軟な対応が求められる場合もあります。
よくある間違いと改善のコツ
ビジネスメールにおける「します」「いたします」の使用では、経験の浅い社会人がつまずきやすいポイントがいくつかあります。
ここでは、典型的な間違いとその具体的な改善方法を解説し、より自然な敬語表現の習得を目指します。
過剰敬語になってしまう典型的なケース
「いたします」を使いすぎることで、かえって不自然な印象を与えてしまうケースが多々あります。
特に、同じ文章内で「させていただきます」などの表現と重複して使用すると、過剰な敬語表現となってしまいます。
- 重複使用:同じ文での「いたします」の複数回使用を避ける
- 混在問題:異なる敬語レベルの不自然な組み合わせに注意
- 過剰使用:簡潔な内容での不必要な「いたします」を削除
- 表現過多:一文における敬語表現の数を適切に制限
- 形式集中:内容より形式に気を取られすぎない意識
過剰な敬語使用を避けるには、文章全体のバランスを意識することが重要です。
特に、一つの文章の中で敬語表現が重なりすぎていないかを確認しましょう。
かえって失礼になるNG例
適切な場面で「いたします」を使用しないことで、かえって失礼な印象を与えてしまうケースがあります。
特に重要な案件や公式な文書では、適切な敬語レベルを維持することが必要です。
- 重要文書:公式文書での「します」の不適切な使用を避ける
- 謝罪文:お詫び時の「します」使用は印象が悪い
- 依頼文:重要な依頼での「します」は軽い印象となる
- 報告書:正式な報告での「します」は適切性に欠ける
- 契約関連:業務契約に関する文書は「いたします」を基本に
失礼にならない表現を選ぶには、文書の性質や目的を十分に理解することが重要です。
迷った場合は、より丁寧な表現を選択することで、失礼のリスクを回避できます。
混在使用による違和感の解消法
同じメール内で「します」と「いたします」が混在すると、読み手に違和感を与える可能性があります。
ここでは、自然な文章にするための具体的な改善方法を解説します。
- 統一基準:メール全体で一貫した表現レベルを維持する
- 段階調整:文脈に応じた適切な表現の切り替えを行う
- 文末調整:結びの言葉と本文の表現レベルを合わせる
- 全体確認:完成後に表現の統一性をチェックする
- 例外把握:意図的な使い分けが必要な場合の判断基準
表現の混在を避けるには、メール作成前に使用する表現レベルを決めておくことが効果的です。
特に長文の場合は、途中で表現レベルが変わっていないか注意深く確認しましょう。
新入社員・転職者のための実践チェックリスト
実際の業務で「します」「いたします」を適切に使用するには、具体的なチェック項目に基づいた確認が有効です。
ここでは、日常的な確認項目と重要メール作成時の最終確認項目を紹介します。
これらを活用することで、適切な敬語使用が習慣として身につきます。
日常的なメールチェックポイント
ビジネスメールを作成する際、いくつかの重要なチェックポイントがあります。
これらを日常的にチェックすることで、「します」「いたします」の適切な使用が自然と身につき、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
- 宛先確認:送信先に応じた適切な敬語レベルを選択する
- 文脈統一:メール全体で敬語レベルの一貫性を保つ
- 時間帯考慮:緊急時は簡潔な「します」を活用する
- CC対応:関係者の役職に応じて表現を調整する
- 慣習順守:部署や案件固有の表現ルールを守る
日々のメールでこれらの点をチェックすることで、適切な敬語使用が習慣化します。
特に最初の3ヶ月は意識的にチェックを行い、徐々に自然な判断ができるようになりましょう。
重要なメールの最終確認項目
特に重要なメールを送信する前には、より詳細なチェックが必要です。
ここでは、送信前の最終確認項目を具体的に解説し、ミスのない適切な敬語表現の実現を目指します。
- 全体確認:文書全体での敬語レベルの統一性を検証
- 重要度:案件の重要性に応じた表現レベルの適切性
- 関係性:全送信先との関係性に合わせた表現選択
- 文末統一:結びの言葉との調和がとれているか確認
- 再考察:時間を置いての最終チェックを実施
重要なメールは、可能であれば時間を置いて再確認することをお勧めします。
また、不安な場合は上司や先輩に確認を依頼することで、より確実な品質を確保できます。
まとめ:自然な敬語表現のために
ビジネスメールにおける「します」「いたします」の使い分けは、新入社員や転職者が最初に直面する重要な課題です。
本記事で解説した基本ルールと実践的なテクニックを意識することで、適切な敬語表現が自然と身につきます。
特に重要なのは、相手との関係性、メールの目的、状況に応じた柔軟な対応です。
最初は慎重に表現を選び、徐々に職場の慣習や相手のスタイルに合わせて調整していくことで、プロフェッショナルなビジネスコミュニケーションが実現できます。
よくある質問(FAQ)
ビジネスメールにおける「します」「いたします」の使い分けについて、新入社員や転職者からよく寄せられる質問にお答えします。
以下の回答を参考に、適切な表現を身につけていきましょう。
Q1:「します」と「いたします」、基本的にはどちらを使うべきですか?
A:基本的には、社内向けでは「します」、社外向けでは「いたします」を使用します。
ただし、相手の役職や案件の重要度によって使い分ける必要があります。
Q2:「させていただきます」との使い分けはどうすればよいですか?
A:「させていただきます」は許可や感謝の意を込める場合に使用します。
通常の業務連絡では「します」「いたします」を使用し、特別な配慮が必要な場合のみ「させていただきます」を使用しましょう。
Q3:社内の別部署の人にはどちらを使うべきですか?
A:基本的には「します」を使用しますが、役職や案件の重要度に応じて「いたします」を使用します。
特に部長級以上や初めての連絡の場合は、「いたします」の使用を検討しましょう。
Q4:複数の表現が混在するのは避けるべきですか?
A:基本的には一つのメール内で表現レベルを統一することをお勧めします。
ただし、文書の内容や目的によって意図的に使い分ける場合は、その理由を明確にしましょう。
Q5:取引先への初めてのメールではどちらを使うべきですか?
A:初めての取引先へのメールでは、必ず「いたします」を使用します。
信頼関係構築の第一歩として、丁寧な表現を心がけ、必要に応じて「させていただきます」も組み合わせましょう。
Q6:返信メールでは元のメールの表現に合わせるべきですか?
A:基本的には自社の基準や立場に応じた表現を選択します。
ただし、相手の表現レベルも参考にしながら、不自然にならない範囲で調整することをお勧めします。
Q7:チャットやメッセンジャーでも同じルールが適用されますか?
A:チャットは多少カジュアルな表現が許容されますが、基本的な敬語レベルは維持しましょう。
特に複数人が参加する場合は、メールと同様の配慮が必要です。
Q8:「いたします」を使いすぎるとどんな印象になりますか?
A:過剰な「いたします」の使用は、形式的で堅苦しい印象を与えたり、逆に不自然さを感じさせたりする可能性があります。
状況に応じた適切な使い分けを心がけましょう。
関連記事
- 「させていただきます」の正しい使い方|過剰敬語にならない表現のコツ
- ビジネスメールの結びの表現|シーン別例文集 ・新入社員のためのビジネスメール基本マニュアル