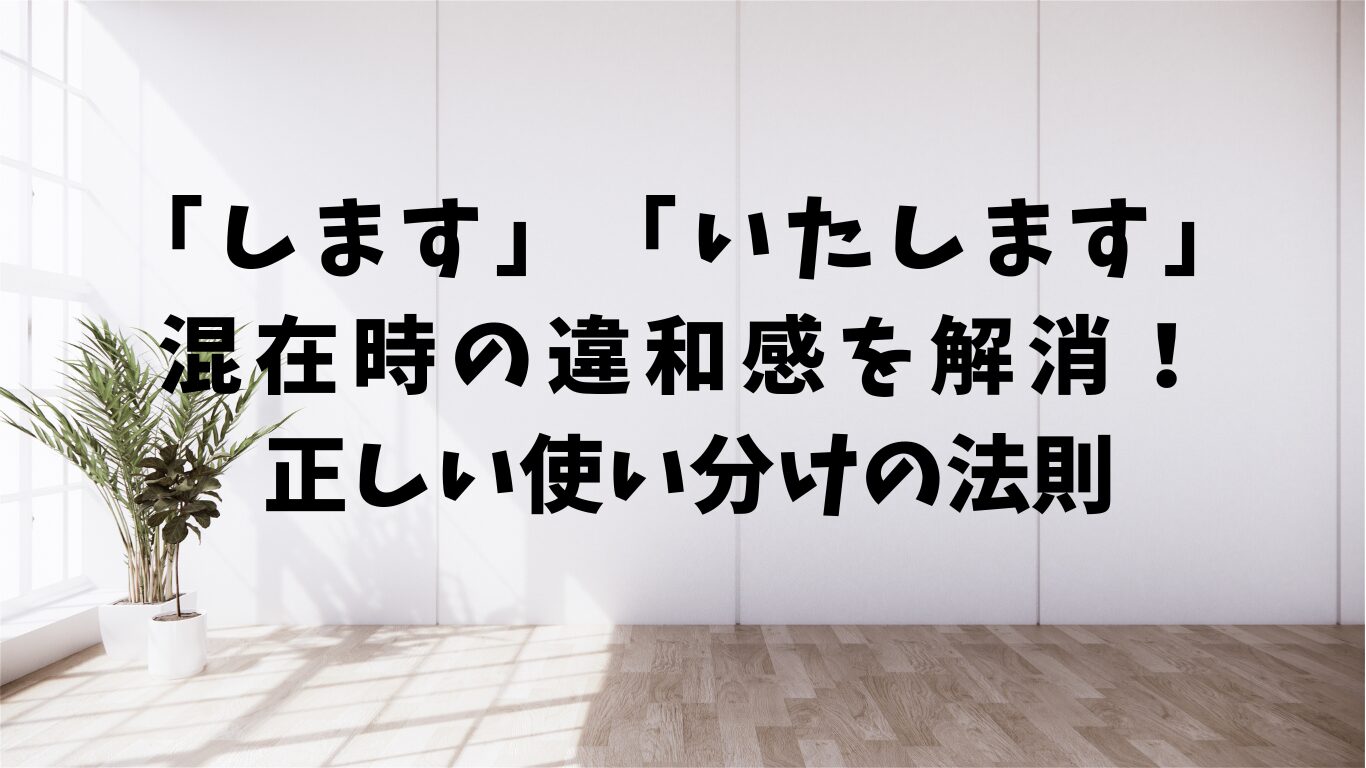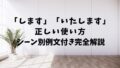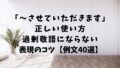ビジネスシーンで頻繁に使用する「します」と「いたします」。
同じ意味でありながら、使い分けを間違えると違和感のある文章になってしまいます。
特にメールや報告書で両者が混在すると、読み手に不快感を与えかねません。
本記事では、プロの視点から「します」「いたします」の正しい使い分け方を、具体例を交えて徹底解説します。
この記事でわかること
- 「します」と「いたします」の基本的な違いと使い分けの原則
- ビジネス文書での正しい使用方法とシーン別の選び方
- よくある混在パターンとその改善方法
- 実践で使える例文とテンプレート
- 上司や取引先への報告時の適切な使い分け方
「します」と「いたします」の使い分けに悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。
この記事を読めば、どんなビジネスシーンでも自信を持って適切な表現を選べるようになります。
「します」「いたします」の基本的な違い
敬語表現の基本となる「します」と「いたします」は、ビジネスコミュニケーションの要となる表現です。
場面や状況に応じた適切な使い分けが、文書の品質を大きく左右します。
まずは、この二つの表現の本質的な違いを理解しましょう。
敬語レベルによる使い分けの基本
敬語には基本形、丁寧語、謙譲語の3段階があり、「します」は丁寧語、「いたします」は謙譲語に位置づけられます。
この違いを理解することが、適切な使い分けの第一歩となります。
相手への敬意の度合いによって使い分けることで、円滑なコミュニケーションが実現できます。
- 「します」は基本の丁寧語で、一般的な敬意を示す場合に使用
- 「いたします」は謙譲の意を含み、より高い敬意を示す場合に適用
- 文書全体の統一感を保つため、敬語レベルを一貫させることが重要
- 相手との関係性によって、適切な敬語レベルを選択する必要がある
- 同一文書内での混在は、特別な意図がない限り避けるべき
ただし、機械的に使い分けるのではなく、状況や文脈に応じた柔軟な対応も必要です。
特に、長文の文書では、全体のトーンを考慮しながら適切なレベルを選択することが重要になります。
ビジネスシーンでの位置づけ
ビジネスシーンでは、文書の種類や目的によって「します」「いたします」の使い分けが明確に求められます。
社内文書と社外文書、報告書とメール、それぞれで求められる敬語レベルが異なることを理解し、適切な表現を選択する必要があります。
- 社内文書では「します」を基本とし、必要に応じて使い分ける
- 社外向け文書では原則として「いたします」を使用する
- 上位者への報告では「いたします」を基本とする
- 同僚間のメールでは「します」で統一する
- プレゼン資料は聴衆に応じてレベルを調整する
組織の文化や慣習によっても使い分けの基準は異なります。
自社の方針や業界の慣習を踏まえつつ、状況に応じた適切な判断が求められます。
正しい使い分けの3つの原則
ビジネス文書における「します」「いたします」の使い分けには、明確な原則が存在します。
これらの原則を理解し、意識的に活用することで、適切な敬語表現を実現できます。
以下、3つの重要な原則について詳しく解説していきます。
相手との関係性による原則
敬語の使い分けで最も重要なのは、コミュニケーションの相手との関係性です。
社内外の立場、役職、年齢などの要素を総合的に判断し、適切な敬語レベルを選択する必要があります。
この判断を誤ると、相手に不快感を与える可能性があります。
- 取引先や顧客には原則として「いたします」を使用する
- 社内の上司には状況に応じて「いたします」を選択する
- 同僚や部下には基本的に「します」を使用する
- 初対面の相手には安全を見て「いたします」を選択する
- 長期的な関係がある場合は状況に応じて調整可能
ただし、これらは基本的な指針であり、具体的な状況や案件の重要度によって変更が必要な場合もあります。
相手との関係性を常に意識しながら、柔軟な対応を心がけましょう。
文書の種類による原則
文書の種類によって求められる敬語レベルは異なります。
フォーマルな文書とカジュアルな文書では、適切な敬語レベルが異なることを理解し、文書の性質に応じた表現を選択する必要があります。
これにより、文書全体の一貫性と適切性が保たれます。
- 契約書関連は必ず「いたします」で統一する
- 社内の業務連絡は「します」を基本とする
- プレゼン資料は聴衆に合わせて選択する
- 議事録は会議の性質に応じて使い分ける
- 提案書は「いたします」を基本として使用する
文書の種類による原則は、組織や業界の慣習によっても異なる場合があります。
自社のガイドラインがある場合は、それに従うことを推奨します。
コンテキストの一貫性原則
同一文書内での敬語レベルの一貫性は、文書の品質を大きく左右します。
特に長文の文書では、文書全体を通じて一貫した敬語レベルを維持することが重要です。
この一貫性が崩れると、読み手に違和感を与えてしまいます。
- 文書の冒頭で使用した敬語レベルを維持する
- 段落ごとに敬語レベルを確認する
- 箇条書きでも統一された表現を使用する
- 引用部分は原文の敬語レベルを尊重する
- 結びの言葉は文書全体の基調に合わせる
ただし、意図的に敬語レベルを変更する場合もあります。
その場合は、変更の理由が読み手に明確に伝わるようにすることが重要です。
シーン別での適切な使用方法
ビジネスシーンには様々な状況があり、それぞれに適した「します」「いたします」の使い方が存在します。
ここでは、具体的なシーンごとの使い分け方について、実践的な視点から解説していきます。
メールでの使用方法
ビジネスメールは最も頻繁に使用される文書形式であり、受信者との関係性や用件の重要度によって適切な敬語レベルを選択する必要があります。
特に、CCの有無や送信先の数によっても表現を調整すべき場合があります。
- 社外向けの新規メールは「いたします」を基本とする
- 社内の定型連絡は「します」で統一する
- 複数の宛先がある場合は最上位者に合わせる
- 返信メールは相手の敬語レベルに合わせる
- CCに上司や取引先がある場合は「いたします」を選択
メールの件名と本文で敬語レベルを統一することも重要です。
特に定型文を使用する際は、文書全体の調和を確認しましょう。
会議・プレゼンでの使用方法
口頭でのコミュニケーションでは、聴衆の構成や会議の性質に応じて適切な敬語レベルを選択します。
特に、プレゼンテーションでは、資料と発話の敬語レベルの一致が重要になります。
- 役員会議では一貫して「いたします」を使用
- 部内会議は基本的に「します」で統一
- クライアントへの提案は「いたします」を基本
- 質疑応答は質問者に応じてレベルを調整
- 原稿がある場合は事前に表現を統一
急な質問への応答など、臨機応変な対応が必要な場合は、基本的により丁寧な「いたします」を選択すると安全です。
報告書・企画書での使用方法
文書による正式な報告や提案では、文書の格式と重要度に応じて適切な敬語レベルを選択します。
特に、複数の関係者が閲覧する可能性がある文書では、最も格式の高い表現を選択することが推奨されます。
- 経営層向け報告書は「いたします」で統一
- 部門内の報告書は「します」を基本とする
- 社外向け企画書は必ず「いたします」を使用
- 予算申請書は「いたします」を基本とする
- 社内提案書は上申先に応じてレベルを選択
文書のフォーマットが定められている場合は、そのフォーマットの敬語レベルに従うことが重要です。
具体例で学ぶ正しい使い分け
適切な敬語表現の選択には、具体的な例を通じた理解が効果的です。
ここでは、実際のビジネスシーンで頻出する表現について、「します」「いたします」の使い分けを詳しく解説していきます。
定型フレーズでの使い分け
ビジネス文書でよく使用される定型フレーズには、状況に応じた適切な敬語レベルが存在します。
これらの表現を正しく使い分けることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
不適切な使用は、文書の品質を大きく損なう原因となります。
- 「承知します」は社内向け、「承知いたしました」は社外向け
- 「検討します」は同僚間、「検討させていただきます」は上位者向け
- 「確認します」は部下向け、「確認いたします」は上司向け
- 「報告します」は日常業務、「ご報告いたします」は重要案件
- 「連絡します」は部内向け、「ご連絡いたします」は部外向け
これらの定型フレーズは、組織の文化や業界の慣習によって好ましい表現が異なる場合があります。
自社の方針を確認しておくことをお勧めします。
メール文例での使い分け
メールは最もよく使用される文書形式であり、適切な敬語表現の選択が特に重要です。
ここでは、典型的なビジネスメールの文例を通じて、「します」「いたします」の具体的な使い分けを見ていきましょう。
- 件名:「ご連絡いたします」(社外)vs「連絡します」(社内)
- 本文:「お送りいたします」(客先)vs「送付します」(同僚)
- 依頼:「お願いいたします」(上司)vs「お願いします」(部下)
- 確認:「確認いたしました」(重要案件)vs「確認しました」(定型業務)
- 返信:「返信いたします」(初対面)vs「返信します」(親しい関係)
メールの文例では、宛先や用件に応じて柔軟に表現を選択することが重要です。
基本形を理解した上で、状況に応じた調整を心がけましょう。
会議・提案での使い分け
会議や提案の場面では、参加者の構成や案件の重要度に応じて、適切な敬語レベルを選択する必要があります。
特に、口頭のプレゼンテーションと配布資料の表現の一貫性が重要になります。
- 挨拶:「説明します」(部内)vs「ご説明いたします」(役員会)
- 質疑:「回答します」(勉強会)vs「回答させていただきます」(講演)
- 提案:「提案します」(チーム内)vs「ご提案いたします」(顧客向け)
- 進行:「始めます」(内部会議)vs「始めさせていただきます」(公式会議)
- 締め:「終わります」(朝礼)vs「終わらせていただきます」(報告会)
会議や提案の場面では、開始から終了まで一貫した敬語レベルを維持することが重要です。
途中での不必要な切り替えは避けましょう。
よくある間違いと改善方法
「します」「いたします」の使い分けでは、気づかないうちに間違いを犯していることがあります。
ここでは、よくある間違いのパターンとその具体的な改善方法について解説します。
適切な修正により、文書の品質を大きく向上させることができます。
混在による違和感の解消
同一文書内での「します」「いたします」の不適切な混在は、最も多い間違いの一つです。
特に長文になるほど、無意識のうちに敬語レベルが揺れやすくなります。
この問題は文書全体の印象を大きく損ねる原因となります。
- 冒頭と結びで敬語レベルが異なる場合は全体を見直す
- 箇条書きの項目で表現が揺れていないかチェックする
- 引用部分と地の文で不自然な差が生じていないか確認
- 定型文と個別記述で敬語レベルの統一を図る
- 長文での途中変更を防ぐため中間でも確認する
文書を書き終えた後、必ず全体を通して敬語レベルの一貫性をチェックすることをお勧めします。
特に締切に追われる場合でも、この確認は怠らないようにしましょう。
過剰な敬語使用の修正
「いたします」を過剰に使用することで、かえって不自然な印象を与えてしまうケースがあります。
適切な敬語レベルは、必ずしも最も丁寧な表現を選ぶことではありません。
状況に応じた適切な選択が重要です。
- 社内の一般的な連絡で「いたします」の連発を避ける
- 同僚間のカジュアルな会話では「します」を基本とする
- 重要度の低い定型業務では簡潔な表現を心がける
- 複数の動詞が連続する場合は全てを敬語にしない
- 慣用句や一般的な表現は過度に丁寧にしない
過度な敬語使用は、コミュニケーションの自然さを損なう可能性があります。
相手との関係性や状況に応じて、適切なバランスを取ることが重要です。
文脈不適合の修正方法
文脈や状況に合わない敬語レベルの選択は、読み手に違和感を与えます。
特に、文書の性質や目的に反する敬語の使用は、プロフェッショナリズムを欠く印象を与える可能性があります。
- 緊急連絡での過度な丁寧表現を避ける
- マニュアルや手順書は簡潔な表現を心がける
- 社内規定文書は統一された表現を使用する
- クレーム対応は適切な敬意を示しつつ明確に
- 非公式な場面での過剰な形式張りを避ける
文脈に応じた適切な敬語レベルの選択は、効果的なコミュニケーションの基本です。
状況を正しく判断し、最適な表現を選択する習慣をつけましょう。
実践的な例文とテンプレート
ビジネスシーンで即座に活用できる例文とテンプレートをご紹介します。
状況に応じて適切な表現を選べるよう、具体的なシーンごとに使用例を分類しています。
これらの例文は、実際のビジネス現場での使用頻度が高いものを厳選しています。
メール文例集:シーン別の定型文
ビジネスメールでは、用件と相手に応じて適切な定型文を使用することで、効率的で正確なコミュニケーションが可能になります。
特に頻出する状況での定型文は、確実に使いこなせるようにしておく必要があります。
- 社外向け報告:「本日の会議内容につきまして、ご報告いたします」
- 社内連絡:「明日の会議について連絡します」
- 上司への確認:「ご指示いただいた件について確認いたします」
- 同僚への依頼:「データの確認をお願いします」
- 取引先への督促:「納品予定について確認させていただきます」
定型文であっても、相手や状況に応じて微調整が必要な場合があります。
基本形を押さえた上で、適切なアレンジを加えることをお勧めします。
報告書・企画書の文例
公式文書では、案件の重要度と読み手の立場に応じた敬語表現が求められます。
特に、複数の関係者が閲覧する文書では、最適な敬語レベルの選択が重要になります。
- 経営会議用:「第3四半期の実績についてご報告いたします」
- 部門報告:「今月の進捗状況を報告します」
- 提案書:「新規事業計画をご提案させていただきます」
- 予算申請:「来年度予算として計上させていただきます」
- 業務連絡:「新システムの導入スケジュールを共有します」
文書の格式や重要度に応じて、適切な敬語レベルを選択することで、文書の説得力と信頼性が高まります。
プレゼンテーションでの表現集
口頭発表では、聴衆の構成と発表内容に応じた敬語表現が必要です。
特に、資料と発話の敬語レベルを一致させることで、プレゼンテーションの一貫性が保たれます。
- 役員向け:「事業計画についてご説明させていただきます」
- 部内発表:「今期の施策について説明します」
- 顧客向け:「新商品のご提案をさせていただきます」
- 勉強会:「事例を基に解説します」
- 質疑応答:「ご質問にお答えいたします」
プレゼンテーションでは、原稿作成時に敬語レベルを統一し、リハーサルで確認することをお勧めします。
上級者のための応用テクニック
ビジネス文書の品質をさらに高めるための応用的なテクニックを解説します。
基本的な使い分けを習得した上で、より洗練された表現方法を身につけることで、プロフェッショナルとしての評価を高めることができます。
段階的な敬意表現の使用法
同一文書内でも、文脈や意図に応じて敬語レベルを段階的に変化させることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
ただし、この技法は高度な判断力が必要で、不適切な使用は逆効果となる可能性があります。
- 冒頭は「いたします」で始め、詳細説明は「します」に移行
- 重要事項の説明時は「いたします」に戻して強調する
- 結論部分は再度「いたします」で締めくくる
- 箇条書きでは項目の重要度に応じてレベルを変える
- 引用部分は文脈を維持しつつ適切なレベルに調整
段階的な敬意表現は、文書の構造を明確にする効果もあります。
ただし、過度な切り替えは避け、必要な場合のみ使用しましょう。
状況に応じた臨機応変な対応
予期せぬ状況や複雑な人間関係が絡む場面では、基本原則を踏まえつつも、状況に応じた柔軟な対応が必要になります。
特に、複数の関係者が関与する場面での適切な判断が重要です。
- 緊急時は簡潔な「します」を基本に状況を優先
- 複数の関係者がいる場合は最上位者に合わせる
- 長期プロジェクトでは関係性の変化に応じて調整
- クレーム対応では状況に応じて柔軟に切り替え
- 国際ビジネスでは文化的背景も考慮して選択
臨機応変な対応には豊富な経験が必要です。
日々の業務で意識的に実践し、スキルを磨いていくことが重要です。
文書の格調を高める表現技法
重要な文書では、「します」「いたします」の使い分けに加え、文書全体の格調を高める工夫が必要です。
適切な敬語表現と組み合わせることで、文書の説得力と品格を向上させることができます。
- 序文は丁寧に「ご説明させていただきます」を活用
- 本文では適度に「させていただく」を織り交ぜる
- 結論部分は「おかせていただきます」で締める
- 重要な提案には「ご提案申し上げます」を使用
- 謝意表現は「感謝申し上げます」で統一する
格調高い表現は、使用過多になると逆効果です。
重要なポイントで効果的に使用することを心がけましょう。
まとめ:確実に使いこなすためのポイント
これまでの内容を踏まえ、「します」「いたします」の適切な使い分けについて、実践的な観点から重要なポイントを整理します。
これらの要点を押さえることで、ビジネスシーンでの的確な敬語使用が可能になります。
最終チェックリストと注意点
文書作成時の最終確認では、特に重要なポイントを機械的にチェックする必要があります。
ここでは、文書の品質を確保するための具体的なチェック項目と、見落としやすい注意点について解説します。
- 文書全体の敬語レベルの一貫性を確認する
- 段落の開始と終了で表現の統一を確認する
- 複数の宛先がある場合は最上位者基準を確認
- 定型文と個別記述の敬語レベル統一を確認
- 文書の性質と敬語レベルの整合性を確認
チェックリストは形式的な確認に終わらせず、文書の目的と照らし合わせながら実施することが重要です。
よくある質問(FAQ)
ビジネス文書における「します」「いたします」の使い分けについて、実務の現場でよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
これらの質問は、多くのビジネスパーソンが直面する具体的な課題を反映しています。
Q1:社内メールで「いたします」を使うのは過剰でしょうか?
A:基本的に社内メールでは「します」で十分です。
ただし、役員への報告など、特に改まった場面では「いたします」の使用も適切です。
Q2:急ぎの連絡の場合は敬語レベルを下げてもよいですか?
A:緊急性が高い場合は「します」を使用し、簡潔に伝えることが推奨されます。
ただし、社外向けの場合は最低限の敬意は保つべきです。
Q3:プレゼン資料と口頭説明で敬語レベルを変えてもよいですか?
A:基本的には統一すべきですが、口頭では聴衆に応じて若干の調整が可能です。
資料は公式記録となるため、より丁寧な表現を維持することをお勧めします。
Q4:同じ文章内で「させていただきます」と「いたします」を混ぜて使うことは問題ありますか?
A:両者は同じ敬語レベルですが、過度な使用は冗長な印象を与えます。
特に「させていただきます」は、許可や感謝の意を含む場面で使用し、通常の報告や連絡では「いたします」を使用することをお勧めします。
Q5:英文が混ざるビジネスメールでは、どのように敬語を使い分ければよいですか?
A:日本語部分は受信者の属性に応じた敬語レベルを維持します。
英文の前後で敬語レベルが変わると違和感があるため、文書全体の基調を決めてから、一貫した表現を使用しましょう。
Q6:チャットやビジネスメッセンジャーでの会話では、どの程度の敬語を使うべきですか?
A:ツールの特性上、比較的カジュアルなコミュニケーションが許容されますが、基本的な敬意は必要です。
社内の同僚との会話では「します」を基本とし、上司や社外の方とのやり取りでは「いたします」を使用することをお勧めします。
Q7:謝罪の場面では、必ず「いたします」を使う必要がありますか?
A:謝罪の場面では、基本的に「いたします」を使用します。
特に「申し訳ございませんでした」と組み合わせる場合は、「対応いたします」「改善いたします」など、一貫して丁寧な表現を使用することが望ましいです。
Q8:新入社員なのですが、先輩や上司への報告はすべて「いたします」を使うべきでしょうか?
A:新入社員の場合、基本的には「します」で十分です。
ただし、公式な報告書や重要な案件の場合は「いたします」を使用しましょう。
過度に丁寧すぎる表現は、かえってコミュニケーションの障害となる可能性があります。
これらの質問と回答は、実際のビジネスシーンでよく直面する課題を反映しています。
状況に応じて適切な判断ができるよう、これらの例を参考にしながら、実践的なコミュニケーションスキルを磨いていくことをお勧めします。
また、不明な点がある場合は、以下の方法で確認することをお勧めします
- 社内のビジネス文書作成ガイドラインの確認
- 上司や先輩への相談
- 部署ごとの慣習の確認
- 取引先との過去のやり取りの確認
ビジネスマナーは、組織や状況によって求められる水準が異なることもあります。
本記事の内容を基本としつつ、実際の現場での適切な判断力を養っていくことが重要です。
適切な敬語使用は、ビジネスコミュニケーションの基本スキルとして、継続的な学習と実践が重要です。