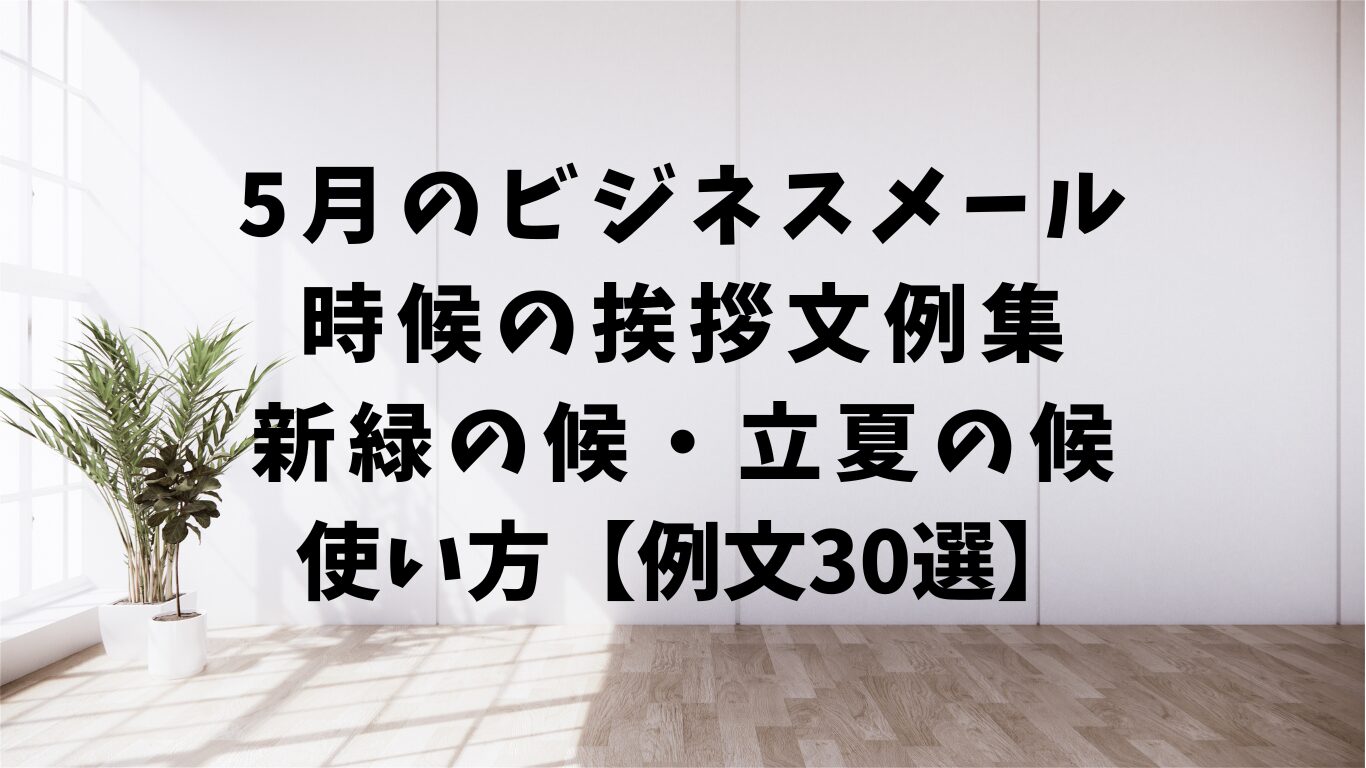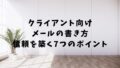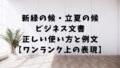新緑が美しい5月のビジネスメールには、季節感のある「時候の挨拶」を入れることで、相手に対する気配りと礼儀正しさを示せます。
しかし、「新緑の候」「立夏の候」など多くの表現があり、どれを選ぶべきか悩む方も多いでしょう。
本記事では、ビジネスシーンで使える5月の時候の挨拶を、シチュエーション別に30以上の例文とともに紹介します。
コピペでそのまま使える実用的な例文も多数掲載していますので、メール作成にお役立てください。
この記事でわかること
- 5月に使える時候の挨拶の基本表現とその意味
- 取引先・上司・同僚など相手別の適切な時候の挨拶文例
- GW明けやゴールデンウィーク中の適切な挨拶文
- 5月特有の季節感を表現するためのビジネス文例集
- 時候の挨拶を入れる際の注意点と間違いやすいポイント
それでは、5月のビジネスメールで使える時候の挨拶について詳しく見ていきましょう。
すぐに使える5月の時候の挨拶文例集
5月のビジネスメールですぐに使える時候の挨拶を紹介します。
状況に応じて使い分けられるよう、さまざまなパターンを用意しました。
一般的な5月の時候の挨拶例文
【フォーマルな表現】
- 「新緑の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
- 「薫風の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「初夏の候、皆様におかれましてはご健勝にてお過ごしのことと存じます。」
【やや砕けた表現】
- 「さわやかな季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。」
- 「若葉の美しい季節となりましたが、お元気にお過ごしでしょうか。」
- 「5月晴れの日が続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
「新緑の候」と「若葉の候」は意味が似ていますが、「新緑の候」の方がよりフォーマルな印象があります。
相手との関係性や文書の重要度に応じて選びましょう。
GW明けの時候の挨拶例文
GW(ゴールデンウィーク)明けには、連休の話題を入れると季節感が伝わります。
【取引先向け】
- 「新緑輝く5月、ゴールデンウィークも過ぎ、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「立夏の候、連休明けのお忙しい時期かとは存じますが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
【社内向け】
- 「さわやかな5月、連休明けのお忙しい中ではございますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
- 「若葉の鮮やかな季節となりました。連休明けのお忙しい時期とは存じますが、ご体調など崩されてはいないでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
連休の過ごし方を詳しく聞くのはプライバシーに踏み込む可能性があるため、「お忙しい時期」という表現にとどめておくのがマナーです。
5月特有の季節感を表す時候の挨拶
5月ならではの季節感を表現に取り入れると、より印象に残るメールになります。
【自然の様子】
- 「青葉若葉の美しい季節となりましたが、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」
- 「爽やかな風が心地よい季節となりましたが、皆様にはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
【行事や節句を含む】
- 「端午の節句も過ぎ、初夏の兆しを感じる季節となりましたが、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
- 「さわやかな五月晴れの日が続いておりますが、貴社におかれましてはますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
行事や節句を入れる場合は、その時期に適したものを選びましょう。
例えば、5月5日が過ぎた後に「端午の節句を前に」という表現は避けるべきです。
相手別・用途別の5月時候の挨拶例文
相手や用途に応じた時候の挨拶の例文を紹介します。適切な敬語レベルと表現で、相手に良い印象を与えましょう。
取引先へのメールでの時候の挨拶
取引先へは敬意を表す丁寧な表現を心がけましょう。
【初めての取引先】
- 「新緑の候、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。この度は弊社にお問い合わせいただき、誠にありがとうございます。」
- 「立夏の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。初めてのご連絡となりますが、当社の○○でございます。」
【継続的な取引先】
- 「爽やかな五月晴れの日が続いておりますが、○○様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」
- 「若葉の美しい季節となりましたが、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
取引先への時候の挨拶は、一般的に「〜の候」「〜のみぎり」といった格式高い表現を使用します。
「〜ですね」などのカジュアルな表現は避けましょう。
社内メールでの時候の挨拶
社内メールでは、相手との関係性に応じた適切な表現を選ぶことが重要です。
【上司へのメール】
- 「立夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素よりご指導いただき、誠にありがとうございます。」
- 「新緑輝く季節となりましたが、○○部長におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
【同僚へのメール】
- 「さわやかな季節となりましたが、お元気にお過ごしでしょうか。先日はプロジェクトへのご協力ありがとうございました。」
- 「GW明けの忙しい時期かと思いますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
【部下へのメール】
- 「新緑の美しい季節となりましたが、体調を崩されてはいないでしょうか。連休明けのお忙しい中ではございますが、報告事項がございます。」
- 「さわやかな初夏の気候となりましたが、皆さんお元気でしょうか。日頃の業務へのご尽力に感謝申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
社内メールでも、特に部署を越えた連絡や上司へのメールでは、ある程度の丁寧さを保つことが大切です。
ただし、頻繁にやり取りがある相手には、簡潔な表現を心がけましょう。
お詫びや依頼のメールでの時候の挨拶
お詫びや依頼の場合は、季節の挨拶と共に誠意を示す表現を加えましょう。
【お詫びのメール】
- 「新緑の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、先日のご納品に関しまして誠に申し訳ございません。」
- 「立夏の候、○○様におかれましてはご健勝にてお過ごしのことと存じます。この度は私どもの不手際により、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」
【依頼のメール】
- 「薫風の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、突然のお願いで恐縮ではございますが、下記の件についてご協力いただけますと幸いです。」
- 「若葉の美しい季節となりましたが、○○様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。大変恐れ入りますが、下記の件についてご検討いただけますと幸いです。」
【間違いやすいポイント】
お詫びや依頼の際は、時候の挨拶の後に「突然のお願いで恐縮ではございますが」「この度は誠に申し訳ございません」などの謙虚な表現を入れるとより丁寧な印象になります。
5月の時候の挨拶の基本と意味
5月に使われる時候の挨拶の基本表現とその意味を解説します。
適切な表現を選ぶために、それぞれの意味を理解しておきましょう。
5月によく使われる時候の挨拶とその意味
5月には、新緑や立夏に関連した表現が多く使われます。
それぞれの意味や由来を知ることで、より適切に使い分けられます。
【新緑の候(しんりょくのこう)】
- 意味:若葉が生い茂り、鮮やかな緑に彩られる時期
- 使用時期:5月上旬〜中旬頃
- 使用例:「新緑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。」
【立夏の候(りっかのこう)】
- 意味:二十四節気の「立夏」(5月5日頃)を指し、夏の始まりを告げる時期
- 使用時期:5月5日〜15日頃
- 使用例:「立夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」
【薫風の候(くんぷうのこう)】
- 意味:春から初夏にかけての香り高い風が吹く時期
- 使用時期:5月〜6月初旬
- 使用例:「薫風の候、貴社におかれましてはますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
【初夏の候(しょかのこう)】
- 意味:夏の始まりを感じさせる時期
- 使用時期:5月中旬〜下旬
- 使用例:「初夏の候、皆様におかれましてはご健勝にてお過ごしのことと存じます。」
【間違いやすいポイント】
「新緑の候」と「若葉の候」はよく混同されますが、「新緑の候」の方がより一般的に使われています。
「立夏の候」は5月5日以降に使うのが適切です。
時期による使い分け(5月上旬・中旬・下旬)
5月の時期によって、適切な時候の挨拶は変わります。月の上旬・中旬・下旬で使い分けましょう。
【5月上旬(1日〜10日頃)】
- 「新緑の候」「青葉の候」「風薫る候」
- 使用例:「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。」
【5月中旬(11日〜20日頃)】
- 「立夏の候」「薫風の候」「若葉の候」
- 使用例:「立夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
【5月下旬(21日〜31日)】
- 「初夏の候」「早夏の候」「夏近し」
- 使用例:「初夏の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
地域によって気候差があるため、実際の気候と合わない表現を使うと違和感を与えることがあります。
特に南北に長い日本では、北海道と沖縄では5月の気候が大きく異なることに注意しましょう。
5月の季節を表す単語・キーワード
時候の挨拶をアレンジする際に役立つ、5月に関連する季節感のある単語やキーワードを紹介します。
【自然に関する表現】
- 新緑、青葉、若葉、薫風、五月晴れ、さわやかな風
- 使用例:「新緑眩しい季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。」
【行事・暦に関する表現】
- 端午の節句、こどもの日、母の日、憲法記念日、八十八夜
- 使用例:「端午の節句も過ぎ、初夏の気配が感じられる頃となりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
【季節の花】
- つつじ、しゃくやく、藤、バラ、カーネーション
- 使用例:「つつじの花が鮮やかに咲き誇る季節となりましたが、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
季節感を出すために花の名前を使う場合は、その花が実際に咲いている時期に合わせましょう。
例えば、桜は4月中旬までに終わることが多いため、5月下旬のメールで「桜が咲き誇る季節」という表現は不自然です。
5月のビジネスメールにおける時候の挨拶の使い分け
状況や目的に応じた時候の挨拶の使い分け方を解説します。
適切な使い分けで、ビジネスマナーを守りつつ、相手に好印象を与えましょう。
ビジネスの関係性による使い分け
相手との関係性によって、使うべき時候の挨拶の表現レベルは変わります。
【取引先・目上の人】
- より格式高い表現を使う:「〜の候」「〜のみぎり」
- 使用例:「新緑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【社内の上司】
- 丁寧な表現を使う:「〜の候」「〜の折」
- 使用例:「立夏の候、部長におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
【同僚・部下】
- やや砕けた表現も可:「さわやかな季節となりましたが」
- 使用例:「さわやかな季節となりましたが、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。先日はご協力いただきありがとうございました。」
【間違いやすいポイント】
社内メールでも、部署を越えた連絡や、チーム全体へのメールでは、ある程度丁寧な表現を使うことが望ましいです。
相手との関係性を考慮し、適切な敬語レベルを選びましょう。
メールの目的による使い分け
メールの目的に応じて、時候の挨拶の後に続ける表現を変えることで、より効果的な文章になります。
【一般的な連絡】
- 基本的な時候の挨拶の後に用件を続ける
- 使用例:「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、先日お問い合わせいただいた件につきまして、ご連絡申し上げます。」
【お礼のメール】
- 時候の挨拶の後に感謝の言葉を加える
- 使用例:「立夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。先日は貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。」
【お詫びのメール】
- 時候の挨拶の後に謝罪の言葉を丁寧に
- 使用例:「薫風の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。この度は弊社の不手際により、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」
【依頼のメール】
- 時候の挨拶の後に謙虚な姿勢を示す
- 使用例:「初夏の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。突然のお願いで恐縮ではございますが、下記の件についてご協力いただけますと幸いです。」
【間違いやすいポイント】
特にお詫びや依頼のメールでは、時候の挨拶だけでは不十分です。
相手の立場に立った謙虚な表現を加えることで、より誠意が伝わります。
GW明けの特別な配慮
ゴールデンウィーク明けのメールには、特別な配慮を示す表現を取り入れると良いでしょう。
【GW明け初めての連絡】
- 連休明けの忙しさに配慮した表現を加える
- 使用例:「新緑の候、連休明けのお忙しい時期とは存じますが、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
【GW中に受けた対応へのお礼】
- 休暇中の対応に対する感謝を示す
- 使用例:「立夏の候、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。連休中にもかかわらずご対応いただき、誠にありがとうございました。」
【GW明けの挨拶メール】
- 季節の変化と共に再開の挨拶
- 使用例:「若葉の鮮やかな季節となりました。連休明けのお忙しい中ではございますが、お元気にお過ごしでしょうか。今後とも変わらぬお付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
「楽しい連休でしたか?」など、プライベートに踏み込んだ質問は避けるべきです。
また、連休明けは業務が立て込むことが多いため、急ぎでない用件は数日待つ配慮も大切です。
効果的な時候の挨拶の書き方とアレンジ
より印象に残る時候の挨拶を書くためのコツとアレンジ方法を紹介します。
相手に季節感と心遣いが伝わる文章を目指しましょう。
基本パターンと応用テクニック
時候の挨拶の基本パターンと、それをもとにしたアレンジ方法を解説します。
【基本パターン】
「〜の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
【具体的な季節感を加える】
「若葉が眩しい新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
【地域性を考慮する】
「関東地方も立夏を迎え、初夏の陽気となりましたが、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。」
【最近の天候に触れる】
「さわやかな五月晴れが続き、過ごしやすい季節となりましたが、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
天候に触れる場合は、長期的な天候傾向を使いましょう。
「今日は雨ですが」など一時的な天気は、メールが読まれるタイミングによっては不自然になることがあります。
オリジナリティを出す表現テクニック
ありきたりな表現から一歩進んで、オリジナリティのある時候の挨拶を作るテクニックを紹介します。
【季節の花や植物を具体的に】
「つつじの花が鮮やかに咲き誇る好季節となりましたが、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
【季節の行事に絡める】
「端午の節句も過ぎ、若葉の緑が深まる季節となりましたが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
【五感で感じる季節感】
「爽やかな風に若葉の香りが漂う季節となりましたが、貴社におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
オリジナリティを出そうとしすぎて、あまりに詩的な表現になりすぎると、ビジネスメールとしては不自然になることがあります。
適度なバランスを心がけましょう。
文化や地域性を考慮した表現
日本は南北に長く、地域によって気候差があります。
相手の地域を考慮した表現を使うと、より細やかな気配りが伝わります。
【北海道・東北地方向け】
「ようやく若葉の季節を迎え、爽やかな日が続いておりますが、貴地におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。」
【関東・中部地方向け】
「立夏を迎え、初夏の陽気となりましたが、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。」
【関西・中国・四国地方向け】
「薫風が心地よい季節となりましたが、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
【九州・沖縄地方向け】
「早くも夏の気配が感じられる季節となりましたが、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
地域性を考慮する際には、極端な表現は避けましょう。
例えば、「貴地は寒いでしょうが」などは失礼に当たる可能性があります。
あくまでも季節の移り変わりを表現する程度にとどめておくのが無難です。
5月の時候の挨拶を入れる際の注意点
時候の挨拶を使う際の注意点や間違いやすいポイントを解説します。
適切な使い方で、マナーを守ったメールを作成しましょう。
避けるべき表現と間違いやすいポイント
ビジネスメールでは避けるべき表現と、よくある間違いを紹介します。
【避けるべき表現】
- 「暑くなってきましたね」(5月上旬・中旬は「暑い」より「さわやか」「過ごしやすい」が適切)
- 「寒い日が続きますが」(季節感が合わない表現)
- 「お体に気をつけて」(相手を心配する表現は上から目線に感じられることも)
- 過度に砕けた表現:「GWは楽しめましたか?」(プライベートに踏み込みすぎ)
【間違いやすいポイント】
- 時期と表現のずれ:5月下旬に「新緑の候」は遅すぎる印象(この時期は「初夏の候」が適切)
- 二重の時候の挨拶:「新緑の候、爽やかな5月となりましたが」(表現が重複)
- 敬語の誤用:「新緑の候、貴社ますますご繁栄のことと思います」(「お慶び申し上げます」が正しい)
ビジネスメールで時候の挨拶を省略できるケース
全てのビジネスメールに時候の挨拶が必要というわけではありません。
省略可能なケースを紹介します。
【省略可能なケース】
- 社内の日常的なやり取り(特に同じ部署内)
- 返信メール(特に短期間のうちのやり取り)
- 緊急性の高い連絡
- 定型的な報告メール
- 短文での問い合わせ返答
【省略すべきではないケース】
- 初めての取引先へのメール
- 久しぶりの連絡
- 重要な案件に関するメール
- お詫びや依頼のメール
- 社外の人への丁寧な対応が求められるケース
【間違いやすいポイント】
社内メールでも、部署を越えた連絡や、幹部へのメールには時候の挨拶を入れる方が無難です。
相手との関係性や案件の重要度を考慮して判断しましょう。
メールの種類別・添削例
実際のメール例と添削ポイントを紹介します。
よくある間違いとその修正方法を確認しましょう。
【改善前:取引先への依頼メール】
株式会社〇〇
△△様
お世話になっております。
弊社の××です。
先日お願いした資料についてですが、明日までに送っていただけますか?
よろしくお願いいたします。
【改善後:取引先への依頼メール】
株式会社〇〇
△△様
新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
お世話になっております。弊社の××です。
突然のお願いで恐縮ではございますが、先日お願いした資料につきまして、
ご多用のところ誠に恐れ入りますが、明日までにご送付いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【添削ポイント】
- 時候の挨拶を加えて丁寧さを表現
- 「突然のお願いで恐縮」という謙虚な表現を追加
- 依頼の表現をより丁寧に
- 結びの言葉を「何卒よろしくお願い申し上げます」と格上げ
【改善前:GW明けの社内連絡】
皆様
お疲れ様です。
連休明けで大変かと思いますが、プロジェクトの進捗確認をさせてください。
5/15までに完了予定のタスクはどうなっていますか?
よろしくお願いします。
【改善後:GW明けの社内連絡】
皆様
さわやかな五月晴れの日が続いておりますが、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。
連休明けのお忙しい中ではございますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。
お疲れ様です。
連休明けでお忙しいところ恐縮ではございますが、プロジェクトの進捗確認をさせてください。
5/15までに完了予定のタスクの現状をご報告いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
【添削ポイント】
- 社内メールにも軽い時候の挨拶を追加
- 連休明けの忙しさへの配慮を表現
- 依頼の表現をより丁寧に
- 強い命令調を避けた表現に修正
まとめ:5月の時候の挨拶で季節感のあるビジネスメールを
5月のビジネスメールにおける時候の挨拶について、ポイントをまとめます。
5月は新緑や若葉が美しい季節であり、ビジネスメールでは「新緑の候」「立夏の候」「薫風の候」「初夏の候」などの表現を使うことで、季節感と相手への配慮を示すことができます。
時候の挨拶を使う際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 時期に合った表現を選ぶ:5月上旬は「新緑の候」、中旬は「立夏の候」、下旬は「初夏の候」など、時期に合わせて使い分ける
- 相手との関係性を考慮:取引先や目上の方には格式高い表現、社内の同僚にはやや砕けた表現を使うなど、関係性に応じて調整する
- メールの目的に合わせる:お詫びや依頼のメールでは、時候の挨拶の後に謙虚な表現を加えるなど、目的に合わせた文章構成を心がける
- オリジナリティを出す:季節の花や行事に触れるなど、ありきたりな表現から一歩踏み出すことで、印象に残るメールになる
- 地域性を考慮:相手の地域の気候を考慮した表現を選ぶことで、より細やかな気配りを示せる
時候の挨拶は、ビジネスマナーの一つであると同時に、相手への敬意と季節感を伝える重要な要素です。
本記事で紹介した例文やポイントを参考に、5月らしさが伝わる丁寧なビジネスメールを作成してください。
【関連記事】
よくある質問(FAQ)
Q1: 5月の時候の挨拶で最も無難なのはどれですか?
A1: 5月全般を通して最も無難な表現は「新緑の候」です。
特に5月上旬から中旬にかけて広く使われています。
時期をより細かく考慮したい場合は、上旬は「新緑の候」、中旬は「立夏の候」、下旬は「初夏の候」が適しています。
Q2: 社内メールでも時候の挨拶は必要ですか?
A2: 日常的な社内メール、特に同じ部署内でのやり取りでは省略しても問題ありません。
ただし、部署を越えた連絡や上司へのメール、重要な案件に関するメールでは、簡潔な時候の挨拶を入れるとより丁寧な印象になります。
Q3: GW明けのメールで気をつけるべきことはありますか?
A3: GW明けは業務が立て込みやすい時期のため、「連休明けのお忙しい中」という配慮の言葉を添えると良いでしょう。
また、急ぎでない用件は数日待つ配慮も大切です。
プライベートな連休の過ごし方を詳しく聞くのは避け、業務に関する内容に焦点を当てましょう。
Q4: 時候の挨拶と「お世話になっております」は両方必要ですか?
A4: 両方使っても問題ありませんが、重複感を避けるために工夫するとよいでしょう。
例えば、「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」の後に、「いつもお世話になっております。〇〇株式会社の△△です。」と続けると自然です。
Q5: メールの返信で毎回時候の挨拶を入れるべきですか?
A5: 短期間に何度もやり取りする場合は、2回目以降の返信では時候の挨拶を省略しても問題ありません。
ただし、数日以上間が空いた場合や、重要な内容の返信の場合は、簡潔な時候の挨拶を入れると丁寧さが伝わります。