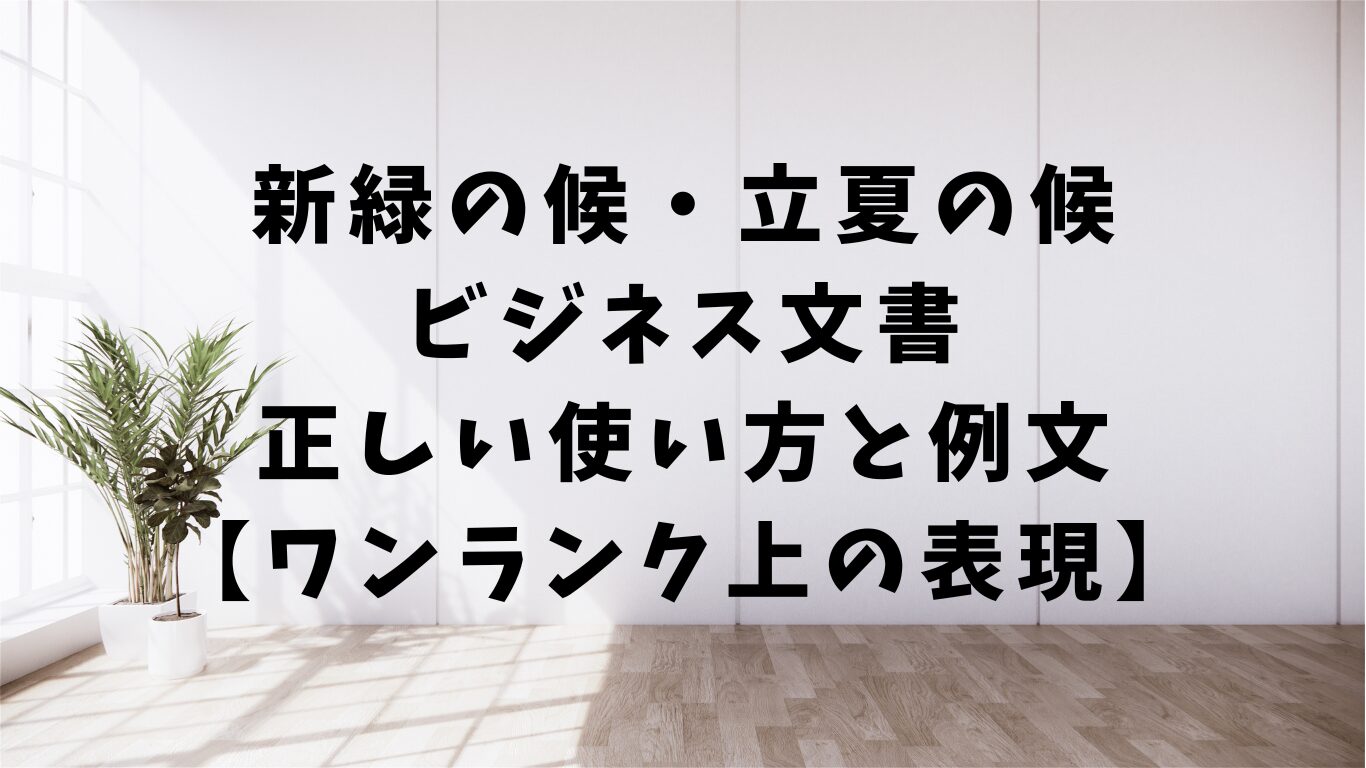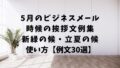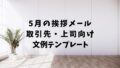ビジネス文書やメールで使われる「新緑の候」「立夏の候」などの時候の挨拶。5月に使うべき表現はどれか、正しい使い方は何か、迷うことはありませんか?
本記事では、5月に適した「新緑の候」「立夏の候」などの時候の挨拶について、ビジネスシーンでの正しい使い方と実用的な例文を紹介します。
これらの表現を適切に使いこなすことで、ビジネス文書の品格を高め、相手に好印象を与えることができるでしょう。
この記事でわかること
- 「新緑の候」「立夏の候」など5月の時候の挨拶の正確な意味と使用時期
- ビジネス文書で使える5月の時候の挨拶の正しい使い方と表現例
- 5月上旬・中旬・下旬における時候の挨拶の適切な使い分け方
- 「新緑の候」「立夏の候」を含む例文と使用シーン別テンプレート
- 時候の挨拶の誤用例と正しい書き方
それでは、5月のビジネス文書に相応しい時候の挨拶の正しい使い方について解説していきます。
すぐに使える「新緑の候」「立夏の候」の例文集
ビジネス文書ですぐに使える、5月の時候の挨拶の例文を紹介します。用途に応じて使い分けられるよう、バリエーション豊かに集めました。
「新緑の候」を使った例文
「新緑の候」は5月上旬から中旬にかけて最も一般的に使われる表現です。
若葉の鮮やかな緑が美しい時期を表します。
【フォーマルな文書・取引先向け】
- 「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「新緑の候、貴社におかれましてはますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
- 「新緑の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
- 「新緑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【やや砕けた表現・社内文書】
- 「新緑の候、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
- 「新緑の候、爽やかな日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
「新緑の候」は日本語として「新緑の時期」という意味ですが、ビジネス文書では単独で使うのではなく、「新緑の候、〜」と続けて使います。
「新緑の候です。」とだけ書くのは不自然です。
「立夏の候」を使った例文
「立夏の候」は二十四節気の一つで、5月5日頃(立夏)以降に使われる表現です。
夏の始まりを告げる時期を表します。
【フォーマルな文書・取引先向け】
- 「立夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」
- 「立夏の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。」
【やや砕けた表現・社内文書】
- 「立夏の候、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
- 「立夏の候、さわやかな日が続いておりますが、お元気にお過ごしでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
「立夏の候」は5月5日頃以降に使うもので、それより前に使うと季節感が合わなくなります。
4月下旬から5月初旬には「新緑の候」を使いましょう。
その他の5月に使える時候の挨拶例文
5月には「新緑の候」「立夏の候」以外にも、様々な時候の挨拶があります。
【「薫風の候」を使った例文】
- 「薫風の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「薫風の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。」
【「若葉の候」を使った例文】
- 「若葉の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。」
- 「若葉の候、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
【「初夏の候」を使った例文】
- 「初夏の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
- 「初夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。」
【間違いやすいポイント】
「初夏の候」は5月下旬以降に使うのが適切です。
5月上旬や中旬に使うと、実際の気候より先走った印象を与えることがあります。
5月の時候の挨拶の意味と正しい使用時期
5月に使われる代表的な時候の挨拶の意味と、それぞれの適切な使用時期について解説します。
正しい時期に適した表現を選ぶことで、季節感のある丁寧な文書が作成できます。
「新緑の候」の意味と使用時期
「新緑の候」は、若葉が生い茂り始め、鮮やかな緑に彩られる時期を表す表現です。
【意味】
「新緑」とは、春から初夏にかけて芽吹いた若々しい緑のことを指します。「候」は「時節」「季節」の意味で、合わせて「新緑の美しい季節」という意味になります。
【適切な使用時期】
- 主に5月上旬から中旬にかけて
- 地域によっては4月下旬から使用可能
- 立夏(5月5日頃)を過ぎても中旬頃までは使える
【例文】
「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
「新緑の候」は5月下旬になると少し遅い印象を与えることがあります。
下旬には「初夏の候」などの表現に移行するとよいでしょう。
「立夏の候」の意味と使用時期
「立夏の候」は、二十四節気の一つである「立夏」に由来する表現で、夏の始まりを告げる時期を指します。
【意味】
「立夏」は二十四節気の第7番目にあたり、「夏が始まる」という意味です。太陽の黄経が45度に達した日で、現在のカレンダーでは毎年5月5日頃にあたります。
【適切な使用時期】
- 立夏(5月5日頃)以降
- 主に5月中旬まで
- 地域によっては5月下旬まで使用可能
【例文】
「立夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
「立夏の候」は立夏(5月5日頃)より前に使うと季節感が合わず、違和感を与えることがあります。
5月初めには「新緑の候」を使うのが適切です。
「薫風の候」「若葉の候」「初夏の候」の意味と使用時期
5月には他にも様々な時候の挨拶があります。
それぞれの意味と適切な使用時期を理解しましょう。
【「薫風の候」】
- 意味:春から初夏にかけて吹く、芳しい香りを運ぶ風の吹く季節
- 使用時期:5月上旬から下旬
- 例文:「薫風の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
【「若葉の候」】
- 意味:若々しい葉が茂り始める季節
- 使用時期:5月上旬から中旬
- 例文:「若葉の候、皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。」
【「初夏の候」】
- 意味:夏の初めの季節
- 使用時期:5月中旬から下旬
- 例文:「初夏の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
これらの表現は、使用する時期がやや重複しています。
「新緑の候」と「若葉の候」は似た意味ですが、「新緑の候」の方がより一般的です。地域の気候や実際の季節感に合わせて選びましょう。
5月上旬・中旬・下旬の使い分け一覧
5月の時期ごとに適した時候の挨拶を一覧にして紹介します。
実際の気候に合わせて選びましょう。
【5月上旬(1日〜10日頃)】
- 「新緑の候」
- 「若葉の候」
- 「青葉の候」
- 「薫風の候」
- 「風薫る季節」
【5月中旬(11日〜20日頃)】
- 「立夏の候」(5月5日以降)
- 「薫風の候」
- 「さわやかな季節」
- 「新緑の候」(中旬前半まで)
- 「初夏の気配」
【5月下旬(21日〜31日)】
- 「初夏の候」
- 「早夏の候」
- 「夏近し」
- 「若葉茂る季節」
- 「清風の候」
【間違いやすいポイント】
地域によって気候差があるため、実際の気候と合わない表現を使うと違和感を与えることがあります。
北日本では「新緑の候」を5月下旬まで使うこともあり、南日本では「初夏の候」を5月中旬から使うこともあります。
ビジネス文書における「新緑の候」「立夏の候」の基本的な使い方
ビジネス文書で「新緑の候」「立夏の候」などの時候の挨拶を適切に使うための基本的なルールと構文を解説します。
時候の挨拶の基本的な文法と構文
時候の挨拶は一定の型に沿って使うことで、格式高い印象を与えることができます。
基本的な構文を習得しましょう。
【基本構文】
- 時候の挨拶+相手の安否や発展を祈る言葉 例:「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 時候の挨拶+実際の気候や季節感+相手の安否を尋ねる言葉 例:「立夏の候、さわやかな日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。」
【敬語表現のパターン】
- 「〜のこととお喜び/お慶び申し上げます」
- 「〜のこととお慶び申し上げます」
- 「〜のことと存じます」
- 「〜でしょうか」(やや砕けた表現)
【間違いやすいポイント】
時候の挨拶の後には、「、」(読点)を入れて、相手の安否や繁栄を祈る言葉を続けるのが基本です。
「新緑の候。」と句点で終わらせるのは不自然です。
ビジネス文書の種類による使い分け
ビジネス文書の種類や目的によって、時候の挨拶の使い方は変わってきます。
【フォーマルな文書(社外向け文書・取引先への文書)】
- 「新緑の候」「立夏の候」などの格式高い表現を使う
- 「貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」などの丁寧な表現を添える
- 例:「新緑の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【社内向け文書・メール】
- やや砕けた表現も可能
- 「お元気にお過ごしでしょうか」などの柔らかい表現を使う
- 例:「立夏の候、さわやかな季節となりましたが、皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。」
【契約書・公式文書】
- 最も格式高い表現を使用
- 例:「新緑の候、貴社におかれましてはますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。さて、下記の通り契約書を送付申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
社内メールでも、部署を越えた連絡や上司へのメールでは、ある程度丁寧な表現を使うことが望ましいです。
特に重要な案件や正式な依頼事項を伝える場合は、時候の挨拶を省略せずに入れるとより丁寧な印象になります。
「拝啓」「敬具」との組み合わせ方
フォーマルなビジネスレターでは、「拝啓」で始まり「敬具」で結ぶ形式がよく使われます。
時候の挨拶はこれらとどう組み合わせるかを解説します。
【基本的な形式】
拝啓
新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
(本文)
敬具
【「時下」を使った形式】
拝啓
時下新緑の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
(本文)
敬具
【略式の形式(メールなど)】
新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
(本文)
何卒よろしくお願い申し上げます。
【間違いやすいポイント】
「拝啓」の後は改行してから時候の挨拶を書きます。
「拝啓 新緑の候」と続けて書くのは誤りです。
また、「拝啓」を使った場合は、文末に必ず「敬具」を入れるようにしましょう。
シーン別・相手別の5月時候の挨拶の使い分け
ビジネスシーンや相手によって、時候の挨拶の使い方や表現レベルは変わってきます。
適切な使い分けで、より効果的なコミュニケーションを図りましょう。
取引先・上司・同僚への使い分け
相手との関係性によって、使うべき時候の挨拶の表現レベルは変わります。
【取引先向け(最も丁寧な表現)】
- 「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」
- 「立夏の候、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【上司向け(丁寧な表現)】
- 「新緑の候、部長におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃よりご指導いただき、誠にありがとうございます。」
- 「立夏の候、ご多忙の折とは存じますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。平素よりご指導ご鞭撻を賜り、誠にありがとうございます。」
【同僚向け(やや砕けた表現)】
- 「新緑の候、さわやかな季節となりましたが、お元気にお過ごしでしょうか。」
- 「立夏の候、爽やかな日が続いておりますが、お変わりなくお過ごしでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
社内メールでも、初めての連絡や重要な案件の場合は、より丁寧な表現を選ぶべきです。
逆に、頻繁にやり取りがある取引先でも、長年の付き合いによっては、やや砕けた表現を使うことも可能です。
状況と関係性を考慮して判断しましょう。
文書の目的別の使い分け
メールや文書の目的に応じて、時候の挨拶の後に続ける表現を変えることで、より効果的な文章になります。
【依頼・お願いの文書】
- 「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、突然のお願いで恐縮ではございますが、下記の件についてご協力いただけますと幸いです。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。大変恐れ入りますが、下記の件についてご検討いただけますと幸いです。」
【お詫びの文書】
- 「新緑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、先日のご納品に関しまして誠に申し訳ございません。」
- 「立夏の候、○○様におかれましてはご健勝にてお過ごしのことと存じます。この度は私どもの不手際により、多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。」
【報告・連絡の文書】
- 「新緑の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、先日ご依頼いただいた件につきまして、下記の通りご報告申し上げます。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。プロジェクトの進捗状況につきまして、ご報告申し上げます。」
【挨拶状・お礼状】
- 「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。さて、先日は貴重なお時間を頂戴し、誠にありがとうございました。」
- 「立夏の候、爽やかな季節となりましたが、○○様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。先日はご丁寧なご対応を賜り、心より感謝申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
時候の挨拶の後には、文書の目的に応じた「つなぎの言葉」を入れるとスムーズです。
例えば、依頼の場合は「突然のお願いで恐縮ではございますが」、お詫びの場合は「この度は誠に申し訳ございません」などの言葉を添えるとより丁寧な印象になります。
GW明けの特別な配慮
ゴールデンウィーク(GW)明けのビジネス文書には、特別な配慮を示す表現を取り入れると良いでしょう。
【GW明け初めての連絡】
- 「新緑の候、連休明けのお忙しい時期とは存じますが、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「立夏の候、連休明けのお忙しい中、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」
【GW中に受けた対応へのお礼】
- 「新緑の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。連休中にもかかわらずご対応いただき、誠にありがとうございました。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。連休中のご対応に心より感謝申し上げます。」
【GW明けの挨拶状】
- 「新緑の候、連休明けのお忙しい時期かとは存じますが、貴社におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。」
- 「立夏の候、爽やかな季節となりましたが、連休明けのお忙しい中、皆様お元気にお過ごしでしょうか。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
GW明けは業務が立て込む時期のため、「連休明けのお忙しい中」という配慮の言葉を添えるとより丁寧です。
また、急ぎでない用件は数日待つ配慮も大切です。
プライベートな連休の過ごし方を詳しく聞くのは避け、業務に関する内容に焦点を当てましょう。
「新緑の候」「立夏の候」を使った文例のアレンジ方法
基本的な時候の挨拶をもとに、より印象に残るアレンジ方法を紹介します。
オリジナリティのある表現で、相手に好印象を与えましょう。
季節感をより強調する表現テクニック
基本的な時候の挨拶に、季節の特徴や自然の様子を加えることで、より季節感のある表現になります。
【自然の様子を加える】
- 「若葉萌える新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「爽やかな風薫る立夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
- 「青葉若葉が鮮やかな新緑の候、貴社におかれましてはますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
【季節の花や植物に触れる】
- 「つつじ咲き誇る新緑の候、貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。」
- 「藤の花香る立夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。」
- 「バラの花開く初夏の候、貴社ますますご繁栄のこととお喜び申し上げます。」
【行事や節句を絡める】
- 「端午の節句も過ぎ、新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「こどもの日を迎え立夏の候となりましたが、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
- 「青葉若葉の美しい五月晴れの季節、貴社におかれましてはますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
季節感を強調する表現を使う場合は、実際の気候や開花時期と合っていることを確認しましょう。
例えば、桜は4月中旬には散ってしまうことが多いため、5月の挨拶で「桜咲く季節」という表現は不自然です。
地域性を考慮した表現
日本は南北に長く、地域によって気候や季節感に差があります。
相手の地域を考慮した表現を使うと、より細やかな気配りが伝わります。
【北日本向け】
- 「ようやく芽吹きの季節を迎え、新緑の候となりましたが、貴地におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。」
- 「若葉の美しい季節となりましたが、貴地はまだ肌寒い日もあるかと存じます。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。」
【関東・中部地方向け】
- 「立夏を迎え、新緑も深まる好季節となりましたが、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
- 「さわやかな五月晴れの日が続く立夏の候、皆様におかれましてはお健やかにお過ごしのことと存じます。」
【西日本・南日本向け】
- 「早くも初夏の陽気を感じる立夏の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
- 「薫風爽やかな初夏の候、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。」
【間違いやすいポイント】
地域差を考慮する場合でも、極端な表現は避けましょう。
「貴地はまだ寒いでしょうが」などの表現は、相手に違和感を与える可能性があります。
あくまでも季節の移り変わりを表現する程度にとどめておくのが無難です。
フォーマル度に応じた表現のバリエーション
相手との関係性や文書の重要度に応じて、時候の挨拶のフォーマル度を調整することができます。
【最もフォーマルな表現(重要な取引先・公式文書)】
- 「時下新緑の候、貴社におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、衷心より御礼申し上げます。」
- 「新緑の候、貴社ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。日頃より一方ならぬご厚誼を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【標準的なフォーマル表現(一般的な取引先)】
- 「新緑の候、貴社ますますご発展のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。」
- 「立夏の候、皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素よりご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。」
【やや砕けた表現(親しい取引先・社内上司)】
- 「新緑眩しい季節となりましたが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。平素よりお世話になり、ありがとうございます。」
- 「立夏を迎え、さわやかな日が続いておりますが、お元気にお過ごしでしょうか。日頃よりご指導いただき、誠にありがとうございます。」
【カジュアルな表現(同僚・部下)】
- 「新緑の美しい季節となりましたが、いかがお過ごしですか。」
- 「立夏を迎え、過ごしやすい日が続いていますね。お変わりありませんか。」
【間違いやすいポイント】
文書の重要度と相手との関係性の両方を考慮して、適切なフォーマル度を選びましょう。
例えば、親しい間柄でも重要な契約に関する文書では、標準的なフォーマル表現を使うのが適切です。
逆に、上司に対してでも日常的な連絡事項であれば、やや砕けた表現を使うこともあります。
時候の挨拶の誤用例と正しい表現
ビジネス文書における時候の挨拶の誤用例と、その正しい表現を紹介します。
よくある間違いを避け、適切な表現を心がけましょう。
よくある誤用パターンと修正例
時候の挨拶でよく見られる誤用パターンと、その修正例を紹介します。
【誤用1:時期と表現のずれ】
- 誤:「桜咲く新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」(5月に桜はすでに散っている)
- 正:「若葉萌える新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
【誤用2:二重の時候表現】
- 誤:「新緑の候、立夏の好季節、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。」(時候表現が重複)
- 正:「新緑の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
【誤用3:敬語の誤用】
- 誤:「新緑の候、貴社ますますご繁栄のことと思います。」(「思います」は丁寧語としては不十分)
- 正:「新緑の候、貴社ますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。」
【誤用4:候の誤用】
- 誤:「新緑の時期、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」(「候」を使っていない)
- 正:「新緑の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」
【誤用5:句読点の誤り】
- 誤:「新緑の候。貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。」(句点で区切っている)
- 正:「新緑の候、貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
【間違いやすいポイント】
時候の挨拶は「〜の候、」と読点で続け、その後に相手の安否や繁栄を祈る言葉を続けるのが基本形です。
また、時候の挨拶と安否を尋ねる言葉は一文で書くのが一般的です。
時候の挨拶を使う際の注意点
時候の挨拶を使う際に気をつけるべきポイントを解説します。
【適切な時期を選ぶ】
- 「新緑の候」は5月上旬〜中旬、「立夏の候」は5月5日以降、「初夏の候」は5月下旬〜というように、実際の季節感に合った表現を選びましょう。
- 「残暑の候」や「晩秋の候」など、他の季節の表現を誤って使わないよう注意しましょう。
【地域性を考慮する】
- 北海道と沖縄では5月の気候が大きく異なります。相手の地域を考慮した表現を心がけましょう。
- 極端な地域差への言及は避け、一般的な季節感を表現するのが無難です。
【重複表現を避ける】
- 「新緑の候、若葉の季節」のように、似た意味の季節表現を重ねて使うのは避けましょう。
- 「新緑の候」と「立夏の候」など、異なる時期を示す表現を同時に使うのも誤りです。
【適切な敬語表現を使う】
- 「お慶び申し上げます」「存じます」などの謙譲語・丁寧語を正しく使いましょう。
- 「思います」「考えます」などの一般的な丁寧語ではなく、より格式高い表現を使うのがビジネス文書では適切です。
【省略可能なケース】
- 社内の日常的なメールなど、親しい間柄での連絡では時候の挨拶を省略することもあります。
- ただし、重要な案件や初めての連絡、上司への連絡などでは、時候の挨拶を含めるのが無難です。
【間違いやすいポイント】
時候の挨拶は、文化や習慣に基づく表現であるため、正確さと適切さが求められます。
不自然な表現は相手に違和感を与えるため、一般的な型に沿った表現を使うのが基本です。
オリジナリティを出す場合も、基本形をベースにした範囲で行うとよいでしょう。
修正例と添削ポイント
実際のビジネス文書の例と、添削ポイントを紹介します。
よくある誤りとその修正方法を確認しましょう。
【例1:取引先への依頼メール】
- 修正前:
株式会社〇〇
△△様
立夏の季節となりました。貴社の皆様は元気ですか?
いつもお世話になっています。
資料を送っていただきたいので、よろしくお願いします。
- 修正後:
株式会社〇〇
△△様
立夏の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、突然のお願いで恐縮ではございますが、下記資料をご送付いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
- 添削ポイント:
- 「立夏の季節」→「立夏の候」と正しい表現に修正
- 「貴社の皆様は元気ですか?」→「貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます」とビジネス文書に適した表現に修正
- 「いつもお世話になっています」→「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます」とより丁寧な表現に修正
- 依頼の前に「突然のお願いで恐縮ではございますが」という謙虚な表現を追加
- 結びの言葉を「何卒よろしくお願い申し上げます」と格上げ
【例2:GW明けの社内連絡】
- 修正前:
各位
暑くなってきましたね。GWは楽しかったですか?
連休明けで大変だと思いますが、プロジェクトの進捗確認したいので、報告お願いします。
では
- 修正後:
各位
新緑の候、連休明けのお忙しい中ではございますが、皆様におかれましてはお元気にお過ごしでしょうか。平素より格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、プロジェクトの進捗確認をさせていただきたく存じます。ご多用のところ恐縮ではございますが、現在の状況をご報告いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
- 添削ポイント:
- 「暑くなってきましたね」→「新緑の候」と5月に適した表現に修正
- 「GWは楽しかったですか?」→プライベートに踏み込む表現を削除
- 「連休明けで大変だと思いますが」→「連休明けのお忙しい中ではございますが」とより丁寧な表現に修正
- 「報告お願いします」→「ご報告いただけますと幸いです」と依頼表現を柔らかく修正
- 「では」→「何卒よろしくお願い申し上げます」と丁寧な結びの言葉に修正
【間違いやすいポイント】
ビジネス文書では、カジュアルな表現や命令調は避け、丁寧な表現を心がけましょう。
特に取引先や上司へのメールでは、時候の挨拶と共に敬意を示す表現を使うことで、より良い印象を与えることができます。
まとめ:5月の時候の挨拶を適切に使いこなす
5月のビジネス文書における「新緑の候」「立夏の候」などの時候の挨拶について、ポイントをまとめます。
5月は新緑や若葉が美しい季節であり、ビジネス文書では時期に応じて「新緑の候」「立夏の候」「薫風の候」「初夏の候」などの表現を使い分けることが重要です。
これらの表現を適切に使うことで、季節感と共に相手への敬意や気配りを示すことができます。
時候の挨拶を使う際は、以下のポイントを意識しましょう。
- 時期に合った表現を選ぶ:5月上旬は「新緑の候」、中旬(特に5月5日以降)は「立夏の候」、下旬は「初夏の候」など、時期に合わせて使い分ける
- 基本的な構文を守る:「〜の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」という基本形を守り、読点で区切る
- 相手との関係性を考慮:取引先や目上の方には格式高い表現、社内の同僚にはやや砕けた表現を使うなど、関係性に応じて調整する
- 文書の目的に合わせる:お詫びや依頼のメールでは、時候の挨拶の後に謙虚な表現を加えるなど、目的に合わせた文章構成を心がける
- 季節感をより強調:「若葉萌える新緑の候」「爽やかな風薫る立夏の候」など、季節の特徴を加えることで、より印象的な表現にする
時候の挨拶は、日本のビジネス文化に根ざした伝統的な表現であり、適切に使うことでビジネスマナーを守り、相手への敬意を示すことができます。
本記事で紹介した例文やポイントを参考に、5月のビジネス文書に相応しい時候の挨拶を使いこなしてください。
【関連記事】
よくある質問(FAQ)
Q1: 「新緑の候」と「立夏の候」は同時に使用できますか?
A1: 「新緑の候」と「立夏の候」は同時に使用するべきではありません。
それぞれが異なる時期を表しており、「新緑の候」は主に5月上旬から中旬、「立夏の候」は5月5日頃(立夏)以降に使います。
文書を作成する時期に合わせて、どちらか適切な方を選びましょう。
Q2: 5月下旬のビジネス文書では、どのような時候の挨拶が適切ですか?
A2: 5月下旬のビジネス文書では、「初夏の候」「早夏の候」「夏近し」などの表現が適切です。この時期は新緑から初夏への移行期であり、「新緑の候」よりも夏の訪れを感じさせる表現の方が季節感に合います。ただし、北日本など地域によっては「立夏の候」「薫風の候」が5月下旬でも違和感なく使える場合があります。
Q3: 英語のビジネスメールにも時候の挨拶に相当する表現はありますか?
A3: 英語のビジネスメールには、日本語の時候の挨拶のような定型表現はありません。
ただし、季節や天候に触れる軽い言及として、”I hope this email finds you well during this beautiful spring season.”(この美しい春の季節に、お元気でお過ごしのことと存じます)のような表現を使うことはあります。
英語圏のビジネスメールはより直接的で簡潔な傾向があり、本題に早く入る方が好まれます。
Q4: 社内メールでも毎回時候の挨拶を入れるべきですか?
A4: 社内メールでは、状況に応じて時候の挨拶を省略することもあります。
日常的なやり取りや簡潔なメールでは省略しても問題ありませんが、以下のような場合は時候の挨拶を入れることをお勧めします。
- 重要な案件や正式な依頼事項を伝える場合
- 部署を越えた連絡や上司へのメールの場合
- 久しぶりの連絡の場合
- お詫びや特別な依頼の場合 時候の挨拶を入れることで、より丁寧な印象を与えることができます。
Q5: 「新緑の候」の後に続く言葉のバリエーションを教えてください。
A5: 「新緑の候」の後に続く言葉には、以下のようなバリエーションがあります。
- 「貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。」(最も一般的)
- 「貴社におかれましてはますますご発展のこととお喜び申し上げます。」
- 「皆様におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。」
- 「ますますご活躍のこととお慶び申し上げます。」
- 「お元気にお過ごしでしょうか。」(やや砕けた表現)
- 「皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。」(やや砕けた表現)
相手との関係性や文書の重要度に応じて、適切な表現を選ぶとよいでしょう。