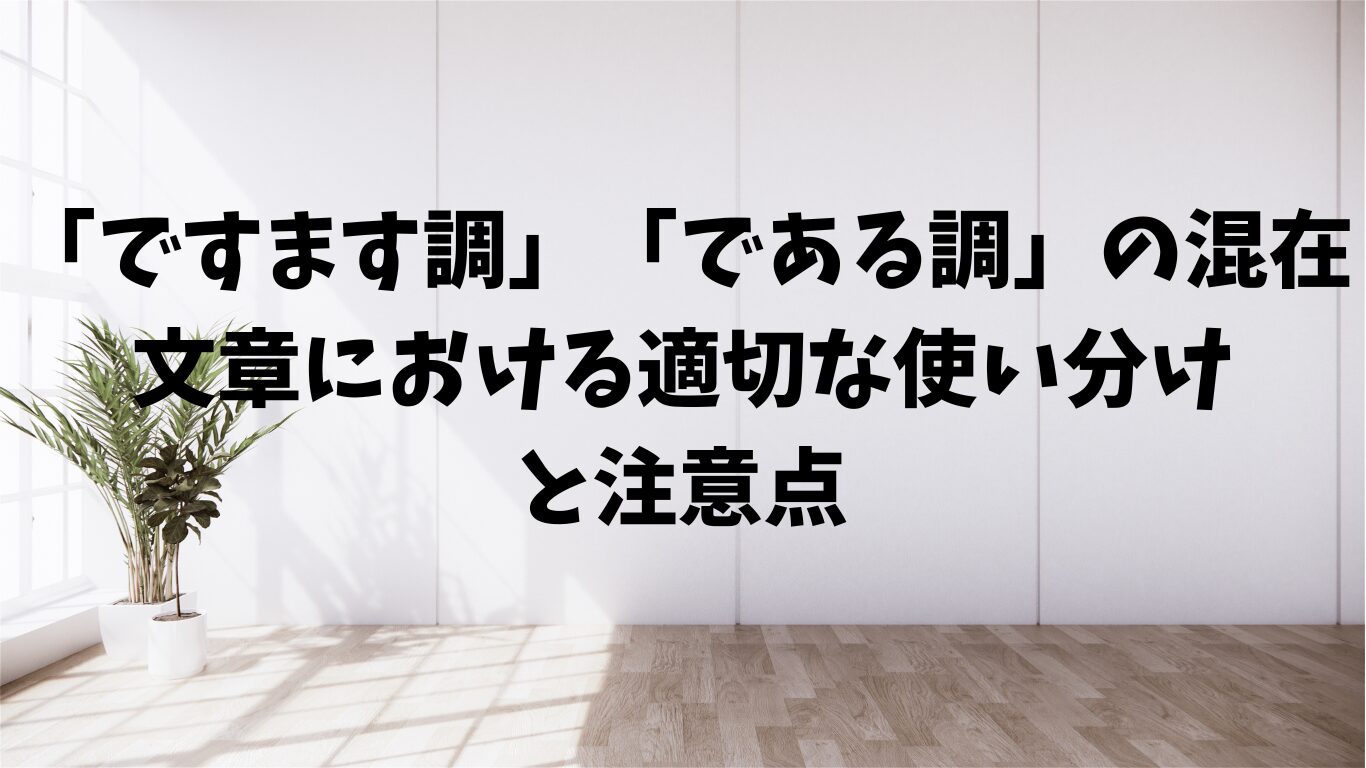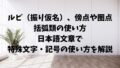文章を書くとき、「ですます調」と「である調」の使い分けに迷うことがよくありますよね。
特に両方の文体が混在しても良いのか、それともNGなのか、判断に困ることがあるのではないでしょうか。
適切な文体選択は、読み手に与える印象を大きく左右します。
特にビジネス文書やレポート、プレゼン資料など、プロフェッショナルな印象を与えたい場面では重要なポイントです。
本記事では、「ですます調」と「である調」の混在は本当にNGなのかという疑問に答えながら、それぞれの文体の特徴や適切な使用場面まで徹底解説します。
さらに、実践的な例文やよくある間違いの修正例も多数紹介しますので、すぐに実務で活用できる知識が身につきます。
この記事でわかること
- 「ですます調」と「である調」の混在はNGなのか、許容されるのかという基本ルール
- それぞれの文体の正式名称と基本的な違い
- 状況に応じた文体の適切な使い分け方と具体的な使用例
- 文体の混在がもたらすメリットとデメリット
- ビジネスシーンで使える実践的な文例とテンプレート
さあ、これから「である調」と「ですます調」の正しい使い分け方をマスターして、あなたの文章力を一段階上へ引き上げましょう。
「ですます調」と「である調」の基本
日本語の文章表現において、「ですます調」と「である調」の使い分けは多くの書き手を悩ませる重要な問題です。
特に両者の混在が許されるのかどうかという点は、文章作成において頻繁に直面する課題です。
この章では、それぞれの文体の基本的な特徴と違いについて解説します。
文体の定義と基本的な違い
「である調」と「ですます調」は、文末表現の違いによって区別される文体です。
- である調: 文末が「だ」「である」などで終わる文体
- ですます調: 文末が「です」「ます」などで終わる文体
この違いは単なる語尾の問題ではなく、文章全体の印象や伝わり方に大きな影響を与えます。
間違いやすいポイント
初心者によくある誤解として、「である調」は単に「だ」で終わる文体だと思われがちですが、実際には「である」「だ」「である」の省略形など、様々なバリエーションがあります。
例えば、以下のような表現はすべて「である調」に含まれます。
これは本である。
これは本だ。
これは本。(「である」の省略)
文体が与える印象の違い
「である調」と「ですます調」は、読み手に異なる印象を与えます。
| 文体 | 与える印象 | 距離感 |
|---|---|---|
| である調 | 客観的、断定的、格調高い | 距離がある |
| ですます調 | 丁寧、柔らかい、親しみやすい | 距離が近い |
具体例
である調の例: 「この研究は日本語表現の進化に関して考察するものである。」
ですます調の例: 「この研究は日本語表現の進化に関して考察するものです。」
同じ内容でも、文体によって読み手が受ける印象が変わることがわかります。
「である調」の正式名称と特徴
「である調」について深く理解するために、その正式名称と言語学的な位置づけを確認しましょう。
多くの人が「である調」という呼び名は知っていても、その正式名称や言語学的背景を知らないことがあります。
常体(じょうたい)としての「である調」
「である調」の正式名称は「常体(じょうたい)」です。
「常体」とは、特に敬語を用いない普通の言い方を指す文法用語です。
具体例
以下に「常体(である調)」の例を示します。
研究の結果、新たな発見があった。
この現象は自然界に広く見られる。
彼の理論は従来の常識を覆すものである。
間違いやすいポイント
常体は「普通体」と呼ばれることもありますが、「だ体」という言い方は正式な文法用語ではありません。
また、常体は敬語を含まないという特徴がありますが、それは必ずしも尊敬や丁寧さを欠くという意味ではありません。
文語体と口語体の違い
「である調」を理解する上で、「文語体」と「口語体」の違いも重要です。
- 文語体: 古典的な文章で用いられる文体(例:なり、たり)
- 口語体: 日常会話で用いられる文体
「である調」は、文語的な雰囲気を持ちながらも、現代の口語として使用される特殊な位置にあります。
具体例
文語体: 「春来たりて草木芽吹くなり」
口語体(である調): 「春が来て草木が芽吹くのである」
口語体(ですます調): 「春が来て草木が芽吹くのです」
「である調」の特徴と効果
「である調」には、以下のような特徴があります。
- 客観性: 事実や意見を淡々と述べる調子
- 格調高さ: 文語的な響きにより文章に厳かさや重みを与える
- 簡潔さ: 余計な装飾を省いた端的な表現
具体例
「この計画は失敗した。原因は準備不足である。」
このような表現は、感情を排した客観的な分析を伝える際に効果的です。
「ですます調」の特徴と使用場面
「ですます調」は、文末に「です」「ます」を使用する丁寧な文体です。
この章では、「ですます調」の特徴と適切な使用場面について詳しく解説します。
丁寧体としての「ですます調」
「ですます調」の正式名称は「丁寧体(ていねいたい)」です。
丁寧体は、話し手や書き手が相手に対して敬意を示す文体です。
具体例
以下に「丁寧体(ですます調)」の例を示します。
今回の調査では、顧客満足度が向上しました。
新商品は来週発売されます。
ご質問がありましたら、お知らせください。
間違いやすいポイント
「ですます調」と敬語は混同されがちですが、必ずしも同じではありません。
「ですます調」は文末の丁寧さを表す基本的な形式であり、敬語はさらに尊敬語や謙譲語を含む広い概念です。
「ですます調」が適している場面
「ですます調」は以下のような場面で特に適しています。
- 対外的なコミュニケーション
- 取引先や顧客とのやり取り
- 公式な案内や説明文
- 読者との親密さを作りたい場合
- ブログやウェブサイトの記事
- マニュアルや説明書
- 初対面の相手とのコミュニケーション
- 新規の問い合わせへの返信
- 初めての打ち合わせでの資料
具体例(ビジネスシーン)
顧客向けのメール:「お問い合わせいただきありがとうございます。ご質問の件につきまして、以下にご説明いたします。」
ウェブサイトの説明文:「当社のサービスは、お客様のニーズに応じてカスタマイズできます。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。」
「ですます調」のメリットと注意点
「ですます調」にはいくつかの明確なメリットがありますが、使用する際の注意点も存在します。
メリット
- 読み手に対する敬意や配慮を示せる
- 親しみやすく、読みやすい印象を与える
- ビジネス文書の標準的な文体として広く受け入れられている
注意点
- 長文では単調になりやすい(語尾のバリエーションが限られる)
- 過度に丁寧すぎると距離感が生まれすぎることがある
- 強い主張や断定的な内容を伝える際には力不足に感じられることがある
文体の混在はNG?その是非を徹底解説
「ですます調」と「である調」を同じ文章内で混在させることは本当にNGなのでしょうか?
この疑問は多くの書き手を悩ませます。結論から言うと、文体の混在が適切かどうかは、文章のジャンルや目的によって異なります。
この章では、混在のルールと効果的な使い分けについて詳しく解説します。
文体の混在はいつNGで、いつOK?
多くの人が「文体の混在はNG」と考えがちですが、実際には状況によって判断が分かれます。
文体の混在が適切か不適切かは、文章のジャンルや目的によって大きく異なるのです。
適切な混在の例
- 異なる視点や役割を区別する場合
- 客観的な説明(である調)と読者への呼びかけ(ですます調)を区別
- 例:「研究結果によれば、この現象は自然界に広く見られる。この点について、詳しく見ていきましょう。」
- 文書の性質が変わる部分
- 報告部分(である調)と提案部分(ですます調)の区別
- 例:「前期の売上は前年比10%増であった。次期はさらなる成長を目指しましょう。」
不適切な混在の例
- 同一段落内での無計画な混在
- 例:「この商品は高性能である。お客様のニーズに応えます。価格も手頃だ。」
- 一貫性のない切り替え
- 例:「研究の結果、新たな発見がありました。これは従来の理論を覆すものである。詳細は以下で説明します。」
間違いやすいポイント
文体の混在で最も避けるべきは、同一の文脈や同一の機能を持つ文章部分での無計画な混在です。
特に、同じ段落内や同じ論点を述べている箇所では、一貫した文体を保つことが重要です。
混在のメリットとデメリット
文体の混在には、意図的に行う場合のメリットと、無計画に行った場合のデメリットがあります。
メリット
- 表現の幅を広げる
- 文体の切り替えにより、文章に変化をつけられる
- 例:「データによれば、この手法は効果的である。それでは、実際に試してみましょう。」
- 読み手との距離感の調整
- 客観的な情報提供と親しみやすい呼びかけを使い分けられる
- 例:「市場は今後も拡大すると予測される。当社もこの流れに乗り、新サービスを展開してまいります。」
- 強調や印象付けの効果
- 重要な部分で文体を変えることで、読者の注意を引ける
- 例:「通常、こうした状況では回復が難しい。しかし、我々は新たな方法を見出しました。」
デメリット
- 文章の一貫性の欠如
- 無計画な混在は読者に混乱を与える
- 例:「この戦略は成功した。しかし課題も残されています。次の一手が重要だ。」
- プロフェッショナリズムへの影響
- 特にビジネス文書では、不適切な混在が専門性の低さを印象づける
- 例:「本報告書は第3四半期の業績をまとめたものです。売上は前年比20%増であった。」
ビジネスシーン別の実践例
ビジネスシーンでは、文体の選択が重要です。
この章では、代表的なビジネスシーンごとに「である調」と「ですます調」の適切な使い分け方と実践例を紹介します。
社内文書での使い分け
社内文書でも、文書の種類や目的によって適切な文体が異なります。
報告書・議事録
報告書や議事録は、事実を客観的に記録する性質上、「である調」が適していることが多いです。
具体例(である調)
第3四半期の売上は前年比15%増であった。特に新規顧客からの受注が好調で、前年比30%増となった。一方、既存顧客からの受注は横ばいであった。
ただし、社内の文化や慣習によっては「ですます調」が標準の場合もあります。
具体例(ですます調)
第3四半期の売上は前年比15%増でした。特に新規顧客からの受注が好調で、前年比30%増となりました。一方、既存顧客からの受注は横ばいでした。
企画書・提案書
企画書や提案書は、読み手を説得し行動を促す性質があるため、親しみやすい「ですます調」が適していることが多いです。
具体例(ですます調)
本企画では、新たな顧客層を開拓するためのマーケティング戦略を提案します。従来のアプローチに加え、SNSを活用した施策を展開することで、若年層へのリーチを強化します。
間違いやすいポイント
同じ文書内でも、報告部分と提案部分で文体を意図的に変えることは可能ですが、その場合は明確な区切り(見出しや段落)で分けることが重要です。
無計画な混在は避けましょう。
対外文書での使い分け
対外文書では、相手との関係性や文書の目的に応じた文体選択が重要です。
取引先・顧客向け文書
基本的には「ですます調」が標準です。丁寧さと親しみやすさを示すことで、良好な関係構築に役立ちます。
具体例(ですます調)
お見積りをご確認くださいますようお願い申し上げます。ご不明な点がございましたら、担当者までお問い合わせください。今後とも変わらぬお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
プレスリリース・公式発表
公式性が求められるプレスリリースでは、両方の文体が使われますが、最近は「ですます調」が増えています。
具体例(ですます調)
当社は本日、新サービス「ビジネスプロ」の提供を開始いたしました。このサービスは、中小企業のDX推進を支援するもので、初期費用無料でご利用いただけます。
具体例(である調)
当社は本日、新サービス「ビジネスプロ」の提供を開始した。このサービスは、中小企業のDX推進を支援するもので、初期費用無料で利用可能である。
敬語表現のテンプレート
対外文書で使える敬語表現のテンプレートを紹介します。
依頼の表現
・〜していただけますようお願い申し上げます。
・〜くださいますと幸いです。
・〜のほど、よろしくお願いいたします。
お詫びの表現
・ご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。
・心よりお詫び申し上げます。
・今後このようなことがないよう、改善いたします。
ウェブコンテンツでの使い分け
ウェブコンテンツでは、サイトの性質や対象読者に応じた文体選択が重要です。
ブログ・コラム
親しみやすさを重視する場合は「ですます調」、専門性や客観性を重視する場合は「である調」が適しています。
具体例(ですます調)
今回は効果的なプレゼンテーション方法についてご紹介します。緊張しがちなプレゼンでも、事前の準備を十分に行うことで自信を持って臨めますよ。
具体例(である調)
効果的なプレゼンテーションには3つの要素が必要である。第一に明確なメッセージ、第二に論理的な構成、第三に適切な視覚資料である。これらを適切に組み合わせることで、説得力のあるプレゼンテーションが実現できる。
商品・サービス説明
一般消費者向けの説明は「ですます調」が親しみやすく効果的です。
具体例(ですます調)
このサービスでは、最新のAI技術を活用して業務効率化をサポートします。導入後すぐに効果を実感いただけるよう、専任のサポートスタッフがお手伝いいたします。
ビジネスシーン別文体の選択ガイド
| シーン・文書種類 | 推奨文体 | 理由 |
|---|---|---|
| 社内報告書 | である調/ですます調 | 社内慣習による |
| 企画・提案書 | ですます調 | 説得力と親しみやすさ |
| 取引先への連絡 | ですます調 | 丁寧さの表現 |
| プレスリリース | 両方可(近年はですます調増加) | 公式性と親しみやすさのバランス |
| 技術文書・マニュアル | である調/ですます調 | 対象読者による |
| ブログ・コラム | ですます調(専門的内容はである調も) | 読者との距離感による |
適切な文体選択のガイドライン
文体選択に迷った際に役立つガイドラインを紹介します。
この章では、文章の目的や対象読者に応じた適切な文体の選び方について解説します。
文章の目的から選ぶ
文章の目的によって、適切な文体は異なります。ここでは目的別に推奨される文体を紹介します。
情報提供・説明を目的とする場合
客観的な情報提供や説明が目的の場合は、「である調」が適していることが多いです。
具体例(である調)
地球温暖化の主な原因は、人間活動による温室効果ガスの排出である。特に二酸化炭素の排出量は産業革命以降急増しており、気候変動の要因となっている。
ただし、一般向けの親しみやすい説明が必要な場合は「ですます調」も効果的です。
具体例(ですます調)
地球温暖化の主な原因は、人間活動による温室効果ガスの排出です。特に二酸化炭素の排出量は産業革命以降急増しており、気候変動の要因となっています。
説得・提案を目的とする場合
相手の行動を促したり意見を変えたりする目的がある場合は、「ですます調」が適していることが多いです。
具体例(ですます調)
この新システムを導入することで、業務効率が30%向上します。初期投資は必要ですが、1年以内に十分な投資回収が見込めます。ぜひご検討ください。
間違いやすいポイント
客観的な情報を提供しながら説得も行うような複合的な目的を持つ文章では、無計画に文体を混在させるのではなく、内容のブロックごとに文体を統一するのが効果的です。
対象読者から選ぶ
対象読者の特性や関係性によっても、適切な文体は変わります。
専門家向け
専門家向けの文章では、客観性や論理性を重視した「である調」が適していることが多いです。
具体例(である調)
本研究では、新たな分析手法を用いてデータを検証した。その結果、従来の手法では見られなかった相関関係が明らかになった。この発見は、今後の研究方向性に大きな影響を与える可能性がある。
一般向け
一般読者向けの文章では、親しみやすさを重視した「ですます調」が適していることが多いです。
具体例(ですます調)
今回の調査結果をわかりやすく解説します。データからは、興味深い傾向が見えてきました。具体的には、20代の利用者が最も多く、次いで30代が続いています。
関係性による使い分け
読者との関係性によっても適切な文体は変わります。
| 関係性 | 推奨文体 | 理由 |
|---|---|---|
| 初対面・公式 | ですます調 | 丁寧さを示す |
| 親しい・非公式 | 状況に応じて | 自然な対話感 |
| 上司・取引先 | ですます調 | 敬意を示す |
| 部下・後輩 | 状況に応じて | 指導と親しみのバランス |
文章のジャンル別ガイド
文章のジャンルごとに一般的に適している文体を紹介します。
| ジャンル | 推奨文体 | 備考 |
|---|---|---|
| 学術論文 | である調 | 客観性・論理性重視 |
| ビジネスレポート | 社内慣習による | 多くの企業ではですます調 |
| マニュアル | ですます調 | 読者への直接的な説明 |
| 小説(地の文) | である調 | 語りの基本文体 |
| エッセイ | 両方可 | 書き手の個性による |
| ブログ | ですます調が多い | 読者との対話感 |
| ニュース記事 | である調が多い | 客観報道の原則 |
効果的な段落・章での文体統一
文体を混在させる場合は、段落や章ごとに文体を統一することで読みやすさを保つことができます。
具体例(段落ごとの統一)
【第1段落:である調】
本研究の目的は、新たな教育方法の効果を検証することである。従来の方法と比較し、学習効果に有意な差があるかを調査した。
【第2段落:ですます調】
では、具体的な研究方法を見ていきましょう。今回の実験では、100名の学生を対象に2つのグループに分け、それぞれ異なる教育方法を適用しました。
よくある間違いと修正例
文体の使用や混在に関するよくある間違いと、その修正例を紹介します。
この章では、実際の文章例を用いて、どのように改善すべきかを解説します。
同一文中での混在
最も基本的な間違いの一つが、同じ文の中で「である調」と「ですます調」を混在させることです。
不適切な例
この製品は高性能である。お客様のニーズに応えます。
修正例
【である調で統一】
この製品は高性能である。お客様のニーズに応える。
【ですます調で統一】
この製品は高性能です。お客様のニーズに応えます。
不自然な切り替え
文脈に合わない突然の文体の切り替えも、読者に違和感を与えます。
不適切な例
本研究の目的は、新たな治療法の開発である。被験者の皆様にはご協力いただき、ありがとうございました。結果は以下の通りである。
修正例
【である調で統一】
本研究の目的は、新たな治療法の開発である。被験者の協力を得て実施した。結果は以下の通りである。
【ですます調で統一】
本研究の目的は、新たな治療法の開発です。被験者の皆様にはご協力いただき、ありがとうございました。結果は以下の通りです。
文書の種類に合わない文体
文書の性質や目的に合わない文体の使用も、プロフェッショナリズムに欠ける印象を与えます。
不適切な例(学術論文)
以上の結果から、本仮説が支持されたと言えます。今後の研究に期待しましょう。
修正例
以上の結果から、本仮説が支持されたと言える。今後の研究の発展が期待される。
間違いやすいポイント
文体選択の際には、文書の種類だけでなく、想定される読者層や発表の場も考慮することが重要です。
例えば、学術的な内容でも一般向けの講演では「ですます調」が適していることもあります。
不適切な敬語との組み合わせ
「ですます調」を使用する際に敬語を不適切に組み合わせるケースも見られます。
不適切な例
本日はご来店していただき、誠にありがとうございます。当店の商品を説明する。
修正例
本日はご来店いただき、誠にありがとうございます。当店の商品をご説明いたします。
プロの書き手による実例分析
プロの書き手は、文体をどのように使い分けているのでしょうか。
この章では、さまざまなジャンルにおけるプロの文体使用例を分析します。
文学作品での使用例
文学作品では、「である調」と「ですます調」を効果的に使い分ける例が多く見られます。
村上春樹作品の例
村上春樹の『ノルウェイの森』では、地の文に「である調」を用い、登場人物の会話には「ですます調」を使用することで、視点の切り替えを明確にしています。
僕はそのとき初めて彼女の部屋を訪れたのだった。(地の文:である調)
「ここに住んでいるんです。一人で」と彼女は言った。(会話:ですます調)
効果的な使い分けのポイント
小説では、語りの視点と会話を区別するために文体を使い分けることが一般的です。
また、同じ作品内でも場面によって文体を変えることで、雰囲気の変化を表現することもあります。
ビジネス文書での使用例
ビジネス文書においても、効果的な文体の使い分けが見られます。
年次報告書の例
企業の年次報告書では、業績の説明を「である調」で客観的に記述しつつ、ステークホルダーへのメッセージを「ですます調」で親しみやすく伝える例があります。
【財務データ部分:である調】
売上高は前年比15%増の1,200億円となった。経常利益は320億円で、過去最高を記録した。
【社長メッセージ部分:ですます調】
株主の皆様には、日頃より当社事業へのご理解とご支援を賜り、心より感謝申し上げます。今期は新規事業が順調に成長し、好調な業績を収めることができました。
ウェブコンテンツでの使用例
ウェブサイトやブログでは、読者との対話感を意識した文体選択が行われています。
料理レシピサイトの例
料理レシピサイトでは、手順説明を「ですます調」で親しみやすく記述し、材料や栄養成分情報を「である調」で簡潔に提示する例が見られます。
【レシピ手順:ですます調】
1. 玉ねぎをみじん切りにします。
2. フライパンで油を熱し、玉ねぎを炒めます。
【栄養成分情報:である調】
1人分のカロリー: 350kcal
タンパク質: 15g
食物繊維: 3g
効果的な使い分けのポイント
ウェブコンテンツでは、読者との対話的な部分を「ですます調」で、情報提供部分を「である調」で記述することで、親しみやすさと信頼性のバランスを取ることができます。
まとめ:効果的な文体使用のポイント
本記事では、「ですます調」と「である調」の特徴、適切な使用場面、文体の混在についての考え方を詳しく解説してきました。
ここでは、効果的な文体使用のポイントをまとめます。
文体選択の基本原則
- 文章の目的を明確にする
- 客観的な情報提供が目的なら「である調」
- 読者との対話感や親しみやすさが重要なら「ですます調」
- 読者との関係性を考慮する
- 公式・初対面の関係では「ですます調」が基本
- 専門家同士の対話では「である調」も自然
- 文章のジャンルや慣習に従う
- 学術論文は「である調」、ビジネス文書は「ですます調」が一般的
- ただし、組織や業界の慣習も考慮する
文体の混在を成功させるコツ
意図的に文体を混在させる場合は、以下のポイントを意識しましょう。
- 段落や章ごとに統一する
- 同じ文脈内では一貫した文体を使用
- 視点や役割が変わる場合に切り替える
- 切り替えのタイミングを明確にする
- 見出しや段落の区切りで文体を変える
- 読者が混乱しないよう配慮する
- 効果を意識して使い分ける
- 重要な部分で文体を変えることで注目を集める
- 客観的な情報と主観的な提案を区別する
文体使用の最終チェックリスト
効果的な文体使用のために、以下のチェックリストを活用してください。
✅ 文章全体の目的と対象読者に適した文体を選択している
✅ 同じ段落内で文体が統一されている
✅ 文体の切り替えには明確な意図がある
✅ 同じ文中では文体が混在していない
✅ 文書の種類や目的に適した文体を選択している
✅ 組織や業界の慣習を考慮している
文体の選択と使い分けは、効果的なコミュニケーションの重要な要素です。
本記事の内容を参考に、状況に応じた適切な文体選択を心がけましょう。
よくある質問(FAQ)
ここでは、「である調」と「ですます調」に関するよくある質問に答えます。
Q1:「である調」と「だ調」は同じものですか?
A1:厳密には異なります。
「である調」は「である」で終わる文体を指しますが、広義には「だ」で終わる文も含めて「である調(常体)」と呼ぶことがあります。
「だ調」は口語的な表現が多く、「である調」はより文語的で格調高い印象を与えます。
Q2:ビジネスメールはどちらの文体が適していますか?
A2:ビジネスメールは基本的に「ですます調」が適しています。
丁寧さと親しみやすさのバランスが取れた文体として、ビジネスコミュニケーションの標準となっています。
ただし、社内の慣習によっては異なる場合もあります。
Q3:学術論文で「ですます調」を使うことはあるのですか?
A3:伝統的に日本の学術論文は「である調」が主流ですが、分野や雑誌によっては「ですます調」を推奨するケースもあります。
特に教育学や心理学など、読者との対話感を重視する分野では「ですます調」が用いられることもあります。
投稿前に対象雑誌のスタイルガイドを確認するとよいでしょう。
Q4:ブログでは「である調」と「ですます調」のどちらがいいですか?
A4:ブログでは一般的に「ですます調」が多く使われています。
読者との親近感を生み出し、対話的な印象を与えるためです。
ただし、専門的な内容や客観的な情報提供が目的の場合は「である調」も効果的に使用できます。
最終的には、ブログの目的や対象読者、自分の書きやすさなどを考慮して選びましょう。
Q5:「ですます調」と「である調」の混在は絶対にNGですか?
A5:すべての混在がNGというわけではありません。
無計画な混在は避けるべきですが、意図的な混在は効果的な場合があります。
例えば、客観的な情報提供部分は「である調」で、読者への呼びかけは「ですます調」で書くなど、目的に応じた使い分けは効果的です。
重要なのは、同じ段落や同じ文脈の中では一貫した文体を保つことです。
混在させる場合は、読者が違和感を覚えないよう、意図を持って切り替えるようにしましょう。
Q6:論文やレポートで「ですます調」を使うと減点されますか?
A6:学校や大学のレポート課題では、指定がない場合は「である調」が無難です。
ただし、教員によって好みが異なるため、事前に確認することをお勧めします。
一般的に、論理的思考力や客観性を評価する場合は「である調」が適していることが多いです。
Q7:SNS投稿はどちらの文体が良いですか?
A7:SNSでは基本的にカジュアルな「ですます調」や、さらにくだけた表現が一般的です。
ただし、企業アカウントなど公式性を持つ場合は、ブランドイメージに合わせた文体選択が重要です。
親しみやすさを重視するなら「ですます調」、権威性や信頼性を重視するなら「である調」が適しています。
Q8:「ですます調」と「である調」が混在している文章を見かけますが、これは間違いですか?
A8: 文体の混在そのものが必ずしも間違いとは言えません。
プロの書き手でも意図的に文体を混在させることがあります。
重要なのは、混在に明確な意図があるかどうかです。
例えば、客観的な事実説明と主観的な意見表明を区別するために使い分けるなど、効果的な混在もあります。
ただし、同じ文脈内で無計画に切り替えると、文章の一貫性や専門性に疑問を持たれる可能性があるので注意が必要です。