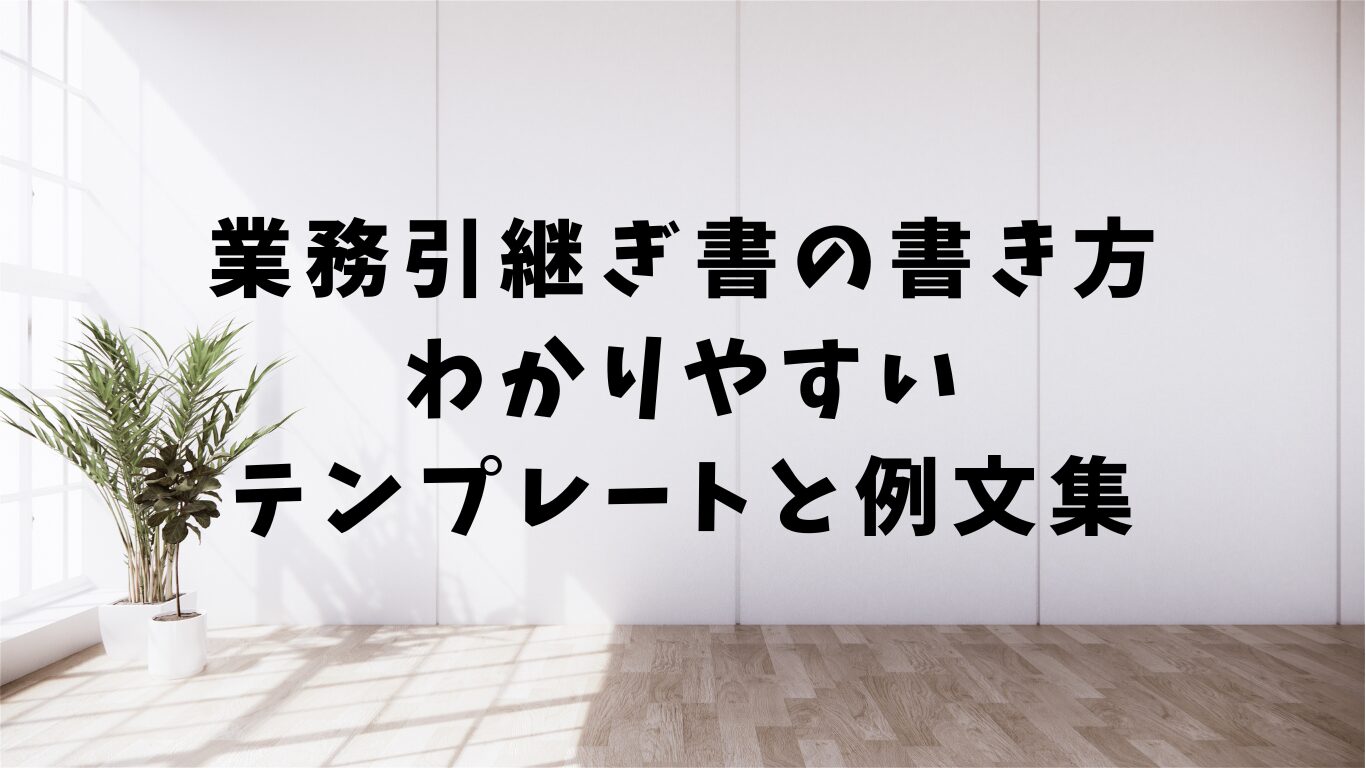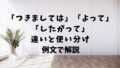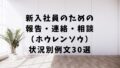業務引継ぎ書は、担当者の交代や異動の際に必要不可欠な文書です。
しかし、「何を書けばいいのか分からない」「情報が抜け落ちていた」という失敗例は少なくありません。
本記事では、業務引継ぎ書の基本から実践的なテンプレート、状況別の例文まで詳しく解説します。
これから引継ぎ書を作成する方も、受け取る側の方も参考になる内容を揃えました。
この記事でわかること
- 業務引継ぎ書の基本的な書き方と構成要素
- すぐに使えるテンプレートと例文
- 職種や状況に応じた引継ぎ書のカスタマイズ方法
- 効果的な引継ぎ書作成のコツと注意点
- よくある失敗例と対処法
さっそく、効率的な業務引継ぎのポイントを学んでいきましょう。
すぐに使える業務引継ぎ書テンプレート
業務引継ぎをスムーズに行うには、適切なテンプレートの活用が効果的です。
ここでは、すぐに使える基本テンプレートと応用例を紹介します。
基本テンプレート
【業務引継ぎ書】
作成日:YYYY年MM月DD日
作成者:〇〇部 〇〇課 氏名
引継ぎ先:〇〇部 〇〇課 氏名
1. 業務概要
• 担当業務の名称と目的
• 業務の全体像と位置づけ
• 主な業務内容
2. 定例業務
• 日次業務(毎日行うこと)
• 週次業務(週に一度行うこと)
• 月次業務(月に一度行うこと)
• 年次業務(年に一度行うこと)
3. 業務手順
• 手順1:○○の方法
• 手順2:○○の方法
• 手順3:○○の方法
4. 関連資料・データの保存場所
• ファイルサーバー:○○フォルダ
• 共有ドライブ:○○フォルダ
• 紙資料:○○キャビネット
5. 関係者連絡先
• 社内:○○部 ○○さん(内線:○○○○)
• 取引先:○○社 ○○さん(TEL:○○○-○○○○-○○○○)
6. 進行中の案件
• 案件名:○○プロジェクト
• 現在の状況:○○の段階
• 今後の予定:○○までに○○を完了予定
7. 注意点・引継ぎ事項
• トラブル発生時の対応
• よくある問い合わせとその回答
• 過去のトラブル事例
8. その他補足事項
• 業務改善提案
• 申し送り事項
シーン別テンプレート例(営業職向け)
【営業担当業務引継ぎ書】
作成日:YYYY年MM月DD日
作成者:営業部 第一営業課 山田太郎
引継ぎ先:営業部 第一営業課 佐藤花子
1. 担当顧客リスト
• A社:主要取引先、月間発注額約100万円
• B社:新規開拓中、提案書提出済み
• C社:契約更新時期(9月末)
2. 営業進捗状況
• A社:新商品導入の提案中(決裁者:A社部長 田中様)
• B社:価格交渉中(20%値引きまで検討可)
• C社:契約更新の打診済み(返答待ち)
3. 顧客別対応のポイント
• A社:毎月10日までに訪問が望ましい、担当者は〇〇さん
• B社:メールよりも電話でのコミュニケーションを好む
• C社:決裁に時間がかかるため、余裕を持った提案が必要
4. 営業資料の保存場所
• 提案書テンプレート:サーバー「営業資料>テンプレート」フォルダ
• 過去の提案書:サーバー「営業資料>顧客別>各社名」フォルダ
• 価格表:サーバー「営業資料>価格情報」フォルダ
5. 販売管理システムの操作方法
• 受注入力:「受注管理>新規受注」から登録
• 顧客情報更新:「顧客管理>編集」から変更可能
• レポート出力:月末に「レポート>月次実績」を出力し上長へ提出
6. 緊急時の対応
• 納期遅延の場合:生産管理部(内線1234)に確認後、顧客へ連絡
• クレーム発生時:上長と品質管理部(内線5678)に報告後、対応
7. 年間イベント
• 4月:新商品説明会
• 9月:展示会出展
• 12月:年末挨拶回り
8. その他申し送り事項
• D社との取引再開の可能性あり(前回断られた理由は価格面)
• 来期の営業戦略会議の資料作成が必要(例年2月実施)
業務引継ぎ書の基本と重要性
業務引継ぎ書は単なる事務手続きではなく、組織の知識を継承し業務の継続性を確保するための重要なツールです。
ここでは業務引継ぎ書の基本と重要性について解説します。
業務引継ぎ書とは
業務引継ぎ書は、担当者が変わる際に必要な業務知識や手順、注意点などを文書化したものです。
口頭だけの引継ぎでは記憶に頼ることになり、情報の漏れや誤解が生じやすくなります。
引継ぎ書には以下のような役割があります:
- 業務の継続性を保つ
- 暗黙知の形式知化
- トラブル発生時の対応策の共有
- 新担当者の早期戦力化
効果的な引継ぎ書の特徴
良い引継ぎ書には以下のような特徴があります:
- 網羅性: 業務全体を漏れなく記載している
- 具体性: 抽象的な説明ではなく具体的な手順や例を含む
- 明確性: 専門用語や略語に説明を付け、誰が読んでも理解できる
- 構造化: 論理的な構成で必要な情報にすぐにアクセスできる
- 最新性: 古い情報ではなく最新の状況を反映している
業務引継ぎに失敗した事例
【具体例】
営業部のAさんが退職する際、主要顧客との商談状況のみを引継ぎ書に記載し、日常的な小さな業務(請求書の確認方法など)については記載しませんでした。
その結果、後任者は基本的な業務フローで躓き、顧客対応が滞る事態となりました。
【間違いやすいポイント】
当たり前すぎて記載を省略してしまう業務こそ、実は引継ぎ書に記載すべき重要情報です。
自分にとって「当然」と思える情報ほど、文書化する意識を持ちましょう。
業務引継ぎ書の作成手順
効果的な業務引継ぎ書を作成するには、体系的なアプローチが必要です。
ここでは、実践的な作成手順を段階的に解説します。
STEP1:業務の棚卸し
まず自分の業務を全て書き出しましょう。この段階では漏れがないように意識することが重要です。
- 日常業務(定期的に行うこと)
- 非定期業務(特定の時期や状況で行うこと)
- 例外的な対応(トラブル時の対応など)
【具体例】
経理担当者の場合:
- 日次業務:入金確認、支払処理
- 月次業務:月次決算処理、税金納付
- 年次業務:年度決算処理、税務申告準備
- 例外対応:支払遅延時の対応、監査対応
【間違いやすいポイント】
「自分しかやっていない業務」や「年に一度しかない業務」は忘れやすいので、年間カレンダーを見ながら確認するとよいでしょう。
STEP2:優先順位づけと構成決め
洗い出した業務に優先順位をつけ、引継ぎ書の構成を決めます。
- 業務の重要度(影響の大きさ)
- 業務の難易度(専門知識や経験が必要か)
- 発生頻度(日常的か稀か)
これらを考慮して、まず何を伝えるべきかの構成を決めましょう。
【具体例】
営業事務の場合の優先順位例:
- 受注処理(毎日・重要)
- 納品管理(週次・重要)
- 売上集計(月次・重要)
- クレーム対応(不定期・重要)
- 各種資料作成(不定期・中程度)
【間違いやすいポイント】
自分が得意な業務や好きな業務を詳しく書きがちですが、引継ぎ相手が最も必要としている情報は何かを考えて優先順位をつけましょう。
STEP3:詳細な手順の文書化
各業務について、具体的な手順を記載します。この際、以下のポイントを押さえましょう。
- 目的(なぜその業務を行うのか)
- 具体的な手順(何をどのように行うのか)
- 使用するツールやシステム(どのシステムで行うのか)
- 完了基準(いつ完了したと判断するのか)
- 関連する資料や参考情報
【具体例】
「月次売上レポート作成」の手順例:
【月次売上レポート作成手順】
目的:部門の売上状況を経営層に報告するため
手順:
1. 販売管理システム「Sales Manager」にログイン
- URL: http://sales.example.com
- ID・パスワードは共有フォルダの「アクセス情報」ファイルを参照
2. 「レポート」→「月次集計」を選択
- 対象月を選択
- 「詳細表示」にチェック
- 「CSV出力」をクリック
3. エクセルテンプレート「月次売上分析.xlsx」を開く
- 保存場所:共有フォルダ→「テンプレート」→「売上分析」
4. CSVデータをテンプレートの「データ」シートにコピー
- グラフやピボットテーブルは自動更新される
5. 「サマリー」シートに前月比・目標達成率など重要指標のコメントを記入
6. 「年月_月次売上報告.pdf」として保存
- 例: 202X年4月_月次売上報告.pdf
7. 経営会議用資料フォルダにアップロード
- 保存場所:共有フォルダ→「経営会議」→「月次報告」→「売上」
8. 経営企画部と各部長にメールで共有
- 宛先:経営企画部(keiei@example.com)、部長メーリングリスト
- 件名:【月次報告】202X年X月売上状況
- 本文テンプレートは「メールテンプレート」フォルダにあり
【間違いやすいポイント】
「〇〇システムを使って売上データを出力する」のような抽象的な表現ではなく、具体的な操作手順(クリックする場所、入力する項目など)まで記載すると理解しやすくなります。
職種別・状況別の業務引継ぎポイント
業務引継ぎ書は職種や状況によって重点を置くべきポイントが異なります。
ここでは、代表的な職種と特殊な状況における引継ぎポイントを解説します。
営業職の業務引継ぎ
営業職では顧客との関係性が重要なため、以下のポイントを詳細に記載します。
- 顧客情報
- 企業情報(規模、業種、特徴)
- 主要担当者(役職、性格、好み)
- 過去の商談履歴や提案内容
- 案件状況
- 進行中の案件と進捗状況
- 過去の成約・不成約事例と理由
- 季節的な受注傾向
- 顧客対応のコツ
- 連絡頻度や好まれる連絡手段
- 決裁プロセスと影響力のあるキーパーソン
- 相手先の課題や興味のあるトピック
【具体例】
【A社対応のポイント】
・決裁者:購買部長の田中様(最終決裁)、実務担当は佐藤様
・佐藤様との連絡は午前中が望ましい(午後は会議が多い)
・コスト削減に非常に関心があるため、投資対効果を明確に示す
・契約更新は毎年3月(2月初旬から交渉開始が望ましい)
・過去の提案資料:共有フォルダ→「顧客別」→「A社」→「提案履歴」
【間違いやすいポイント】
顧客との個人的な関係性や非公式な情報も業務を円滑に進める上で重要ですが、プライバシーや企業倫理に配慮した記載を心がけましょう。
経理・財務職の業務引継ぎ
経理・財務職では正確性と期限が重要なため、以下のポイントを詳細に記載します。
- 業務スケジュール
- 日次・週次・月次・年次の処理と期限
- 税金納付や決算のスケジュール
- 監査対応の時期と準備事項
- 各種手続きの方法
- 仕訳入力のルールや勘定科目の判断基準
- 請求書発行・支払処理の手順
- 現金・預金管理の方法
- 関連部署・外部機関との連携
- 税理士・会計士との連絡方法
- 各部署への依頼事項と期限
- 銀行担当者の連絡先
【具体例】
【月次決算処理手順】
1. 月末締め(毎月最終営業日)
・売上・仕入計上漏れがないか確認
・未払費用・前払費用の計上
・固定資産の減価償却処理
2. 合計残高試算表の作成(翌月5営業日まで)
・会計システム「財務Pro」で「月次→試算表出力」を実行
・勘定科目別残高の妥当性チェック
・前月比で±20%以上の科目は理由を明記
3. 経営報告資料の作成(翌月8営業日まで)
・テンプレート:共有フォルダ→「経理」→「レポート」→「月次」
・重要指標:売上総利益率、営業利益率、販管費率
・特記事項:特別な要因による変動の説明
【間違いやすいポイント】
経理業務では例外的な処理(決算時の特別な仕訳など)が多いため、通常の処理だけでなく特殊なケースについても記載しておくと良いでしょう。
長期不在時の一時的引継ぎ
長期休暇や育児・介護休業などで一時的に業務を引き継ぐ場合は、以下のポイントを重視します。
- 期間中に発生する重要業務
- 締め日・支払日などの固定業務
- 不在期間中に予定されているイベントや案件
- 定期的な報告業務
- 判断基準と権限
- 代行者が判断できる範囲
- 判断を仰ぐべき事項と連絡方法
- 緊急時の対応フロー
- 復帰時の引継ぎ方法
- 記録しておくべき事項
- 報告の仕方や形式
- 保管しておくべき資料
【具体例】
【育休中の引継ぎ事項】
・毎月10日:取引先A社への月次レポート提出
→テンプレートに沿って作成し、上長の確認後に送付
・2月中旬:年間契約更新の準備
→見積書は前年同様で作成可。大幅な変更が必要な場合は要連絡
・クレーム対応:
→軽微なものは社内ルールに従って対応
→重大なものは部長と相談の上、私にもメールで状況共有
・復帰時の引継ぎ:
→対応した案件は「引継ぎ記録表.xlsx」に記入
→重要な決定事項や変更点は「申し送り事項」シートに記録
【間違いやすいポイント】
「必要なら連絡してください」という曖昧な指示ではなく、「どのような場合に」「どのような方法で」連絡すべきかを明確にしておくことが重要です。
業務引継ぎ書作成のコツと実践テクニック
効果的な業務引継ぎ書を作成するためのコツや実践的なテクニックを紹介します。
これらを活用することで、より分かりやすく実用的な引継ぎ書が作成できます。
視覚化と構造化のテクニック
文章だけでなく、視覚的な要素を取り入れることで理解しやすい引継ぎ書になります。
- フローチャートの活用
- 複雑な判断が必要な業務プロセスを図示
- 条件分岐を明確に表現
- チェックリストの作成
- 定期業務の実施項目を一覧化
- 完了確認がしやすい形式で提供
- スクリーンショットの活用
- システム操作手順を画像で示す
- 重要な入力項目や注意点を強調
【具体例】
受注処理のフローチャート:
受注メール受信
↓
在庫確認 → 在庫なし → 仕入先に確認 → 納期回答
↓ 在庫あり
受注システム入力
↓
出荷指示書発行
↓
顧客へ受注確認メール送信
【間違いやすいポイント】
視覚化は効果的ですが、図や表だけでは伝わらない場合もあります。
重要な判断基準や例外事項は文章でも補足説明するとよいでしょう。
引継ぎ書の検証と改善方法
作成した引継ぎ書が実際に機能するかを検証し、改善するプロセスも重要です。
- 第三者レビュー
- 業務に詳しくない人に読んでもらう
- 分かりにくい部分や疑問点を指摘してもらう
- 模擬引継ぎ実施
- 引継ぎ相手に実際の業務を引継ぎ書に沿って実施してもらう
- つまずいた箇所を記録し、内容を補足する
- 定期的な更新計画
- 引継ぎ後も定期的に内容を更新する仕組みを作る
- 変更点を記録する専用のログを設ける
【具体例】
検証チェックリスト:
□ 業務未経験者が読んで理解できるか
□ 専門用語や略語に説明が付いているか
□ 実際の業務を遂行できる具体性があるか
□ トラブル時の対応方法が記載されているか
□ 最新の情報や変更点が反映されているか
□ 参照すべき資料の保存場所が明確か
□ 連絡先情報が最新のものになっているか
【間違いやすいポイント】
自分は理解していることでも、他者には伝わらないことがあります。
「当たり前」と思わずに、基本的なことも丁寧に説明する姿勢が重要です。
デジタルツールの活用
紙の引継ぎ書だけでなく、デジタルツールを活用することで効率的な引継ぎが可能になります。
- クラウドツールの活用
- Google DocsやNotionなどで共同編集
- 情報の更新や検索が容易
- ナレッジベースの構築
- 社内Wikiなどで知識を体系的に整理
- 複数人で維持・更新できる形式
- 動画マニュアルの作成
- 複雑な操作手順を画面録画で説明
- 音声解説を付けて理解を促進
【具体例】
【デジタル引継ぎ資料の構成例】
1. Google Drive
・共有フォルダ「業務引継ぎ」を作成
・文書はGoogle Docsで作成し、共同編集可能に設定
・表計算はGoogle Sheetsで管理し、自動更新されるダッシュボードを作成
2. 画面録画マニュアル
・複雑なシステム操作は「Loom」で録画
・各動画のリンクをメインの引継ぎ文書に埋め込み
・重要ポイントのタイムスタンプを記載
3. チャットツール連携
・Slackに専用チャンネル「#引継ぎ質問」を作成
・よくある質問と回答をピン留めで保存
【間違いやすいポイント】
デジタルツールに過度に依存すると、システムトラブル時に対応できなくなる可能性があります。
重要な情報は紙の文書としても残しておくことをお勧めします。
業務引継ぎ時の注意点と失敗例
業務引継ぎでよくある失敗パターンとその対策について解説します。
これらの注意点を踏まえることで、スムーズな引継ぎを実現できます。
情報セキュリティに関する注意点
業務引継ぎでは機密情報の扱いに注意が必要です。
- 個人情報の取り扱い
- 顧客・社員の個人情報は最小限に留める
- 必要な場合は適切な権限管理を行う
- アクセス権限の引継ぎ
- システムのID・パスワードの安全な引継ぎ方法
- 退職時のアクセス権限削除の確認
- 機密情報の管理
- 機密レベルに応じた情報共有の範囲
- 文書の保管・廃棄ルールの徹底
【具体例】
【セキュリティ関連の引継ぎ事項】
・顧客リストはマスキング版を引継ぎ書に添付
・完全版は情報セキュリティ管理者の承認後に共有
・システムパスワードは引継ぎ完了後に変更する
・機密文書は引継ぎ専用PCでのみ閲覧可能(USBやクラウドへの保存禁止)
・紙の機密資料は引継ぎ完了後にシュレッダー処理
【間違いやすいポイント】
円滑な引継ぎのためとはいえ、セキュリティルールを無視した情報共有は避けましょう。
会社のセキュリティポリシーに沿った方法で情報を共有することが重要です。
失敗しやすいケースと対策
典型的な引継ぎ失敗パターンとその対策を紹介します。
- 情報の粒度が不適切
- 失敗例:専門用語だけで説明し、基本知識がない人には理解できない
- 対策:読み手のレベルを想定し、必要に応じて基礎から説明する
- 重要度の判断ミス
- 失敗例:稀にしか発生しない重大案件の対応方法を省略してしまう
- 対策:発生頻度と影響度のマトリクスで優先度を判断する
- 暗黙知の見落とし
- 失敗例:「当然知っているはず」と思い、基本的な判断基準を記載しない
- 対策:第三者に読んでもらい、不明点を洗い出す
【具体例】
【よくある失敗例と対策】
失敗例1:「在庫管理システムで処理する」だけで具体的な操作手順がない
対策:「システム名→メニュー名→操作ボタン」の順で具体的に記載
失敗例2:「特別対応が必要な顧客」と書くだけで、その理由や対応方法の記載がない
対策:「なぜ特別対応が必要か」「どのような対応をすべきか」を明記
失敗例3:繁忙期の特殊処理について記載がなく、その時期になって混乱が生じた
対策:年間カレンダーを作成し、特別な対応が必要な時期と内容を明記
【間違いやすいポイント】
「この程度は説明不要だろう」という判断が引継ぎ失敗の原因になることが多いです。
自分の立場ではなく、初めてその業務に触れる人の視点で必要な情報を考えることが重要です。
トラブル発生時の対応方法の明確化
業務遂行中に発生するトラブルへの対応方法も引継ぎ書に含めることが重要です。
- よくあるトラブルリスト
- 過去に発生した問題とその解決方法
- 予兆や前触れの見分け方
- エスカレーションルート
- 自分で判断できない場合の相談先
- 緊急時の連絡先と連絡順序
- トラブル対応の権限範囲
- 担当者が独自判断できる範囲
- 上長の承認が必要な事項
【具体例】
【システム障害発生時の対応フロー】
1. 症状の切り分け
□ エラーメッセージを記録(スクリーンショット推奨)
□ 再現性の確認(一時的か継続的か)
□ 影響範囲の特定(自分だけか全社的か)
2. 初期対応
□ システム再起動で復旧するか確認
□ 代替手段で業務継続可能か検討
□ 関係者への一次報告
3. 専門部署への連絡
□ IT部門ヘルプデスク(内線:1234)へ連絡
□ 障害票発行番号を記録
□ 復旧見込み時間の確認
4. 顧客対応
□ 影響のある顧客へのアナウンス
□ 納期遅延の可能性がある場合は営業部門と協議
【間違いやすいポイント】
「このようなトラブルは二度と起きないだろう」と考えて記載を省くと、同様の問題が発生した際に新担当者が対応できません。
過去のトラブル事例は貴重な教訓として必ず記録しておきましょう。
円滑な引継ぎ面談の進め方
業務引継ぎ書の作成だけでなく、実際の引継ぎ面談も重要です。
効果的な引継ぎ面談の進め方について解説します。
引継ぎ面談の準備と進行
- 事前準備
- 引継ぎ書を事前に共有し、目を通してもらう
- 質問事項をリストアップしてもらう
- 必要な資料やアクセス権を準備
- 面談の進め方
- 業務の全体像から説明を始める
- 重要度の高いものから優先的に説明
- 実際の業務を一緒に行う機会を設ける
- フォローアップ計画
- 引継ぎ後の質問対応方法
- 一定期間後のレビュー実施
- 継続的な支援体制
【具体例】
【引継ぎ面談スケジュール例】
Day 1: 業務概要説明(2時間)
• 業務の全体像と位置づけ
• 関連部署との連携
• 主要な業務フロー
Day 2-3: 主要業務の実地研修(各半日)
• システム操作の実演
• 実際のケースで作業実施
• よくある問題とその対処法
Day 4: 特殊ケース対応(2時間)
• 例外的な処理の説明
• トラブル対応シミュレーション
• 判断に迷うケースの相談先
Day 5: 質疑応答とまとめ(2時間)
• 不明点の質疑応答
• 確認テストの実施
• フォローアップ計画の共有
【間違いやすいポイント】
一度にすべてを説明しようとすると情報過多になります。
重要な項目から順に説明し、理解度を確認しながら進めることが効果的です。
引継ぎ後のフォローアップ
引継ぎ完了後も一定期間はフォローアップが必要です。
- 定期的な確認
- 週次や月次での進捗確認
- 課題や不明点の解消
- 段階的な自立支援
- 最初は全面サポート
- 徐々に自己解決を促す
- 最終的には相談役に
- 引継ぎ書の更新
- フォローアップで判明した不足情報を追記
- 業務変更があれば随時更新
【具体例】
【フォローアップ計画】
引継ぎ1週間後:
• 日常業務で困っていることはないか確認
• 引継ぎ書の不明点を補足説明
引継ぎ1ヶ月後:
• 月次業務の実施状況を確認
• 必要に応じて追加サポート
引継ぎ3ヶ月後:
• 業務の自立度を評価
• 引継ぎ書の改善点をフィードバック
引継ぎ6ヶ月後:
• 最終確認
• 引継ぎ書の更新・改善
【間違いやすいポイント】
引継ぎが完了したと思っても、実際に業務を行う中で新たな疑問が生じることが多いです。
「いつでも質問してください」という姿勢を示しつつも、定期的に確認する機会を設けることが重要です。
まとめ
業務引継ぎ書は、単なる書類ではなく組織の知識と経験を継承するための重要なツールです。
効果的な引継ぎ書を作成するポイントをまとめます。
- 基本構成を押さえる
- 業務の全体像から具体的な手順まで階層的に整理
- 定例業務と例外対応の両方を網羅
- 関連資料や連絡先などの情報も忘れずに記載
- 分かりやすさを重視
- 具体的な手順と例を豊富に含める
- 視覚的な要素(図表やスクリーンショット)を活用
- 第三者の視点で読みやすさを確認
- 継続的な改善
- 引継ぎ後のフィードバックを反映
- 業務変更に応じて定期的に更新
- 組織のナレッジベースとして発展させる
本記事で紹介したテンプレートや例文を活用し、自社の状況に合わせてカスタマイズすることで、より効果的な業務引継ぎが実現できます。
業務の継続性を確保し、新担当者の早期戦力化を支援する質の高い引継ぎ書を作成しましょう。
FAQ(よくある質問)
Q1: 業務引継ぎ書はどのくらい前から準備すべきですか?
A1: 理想的には異動や退職が決まってから最低1ヶ月前から準備を始めるのが良いでしょう。
複雑な業務や多岐にわたる責任がある場合は、さらに余裕を持って2〜3ヶ月前から準備することをお勧めします。
日々の業務をこなしながら作成することになるため、十分な時間を確保することが重要です。
Q2: 短期間で引継ぎを行わなければならない場合、何を優先すべきですか?
A2: 限られた時間では、「業務の継続に必要不可欠な情報」を最優先に伝えましょう。
具体的には、日常的な定例業務の手順、近日中に対応が必要な案件、主要な連絡先、トラブル発生時の対応方法などです。
その後、時間の許す限り詳細情報を追加していきます。
Q3: 細かすぎる引継ぎ書はかえって読みにくくなりませんか?
A3: 確かに情報過多になると重要なポイントが埋もれてしまう可能性があります。
対策として、まず全体像を示す概要ページを作成し、詳細は別の章やファイルに分けるといった構造化が効果的です。
また、「最低限これだけは押さえておくべき」というポイントを明示することも有効です。
Q4: 引継ぎ相手がなかなか理解してくれない場合はどうすれば良いですか?
A4: 人によって学習スタイルや理解のペースは異なります。
口頭説明だけでなく、実際に一緒に作業する「ショウ・アンド・テル」方式を取り入れたり、視覚的な資料を増やしたりするなど、複数のアプローチを試みましょう。
また、一度にすべてを伝えようとせず、優先度の高いものから段階的に進めることも効果的です。
Q5: 社外秘の情報を含む業務の引継ぎはどうすれば良いですか?
A5: 会社の情報セキュリティポリシーに従いつつ、業務遂行に必要な情報は適切に共有する必要があります。
具体的には、機密情報へのアクセス権限の申請を正式に行う、閲覧できる環境を限定する、引継ぎ書の機密レベルを明示するなどの対策が考えられます。
不明な点は情報セキュリティ担当部署に相談することをお勧めします。