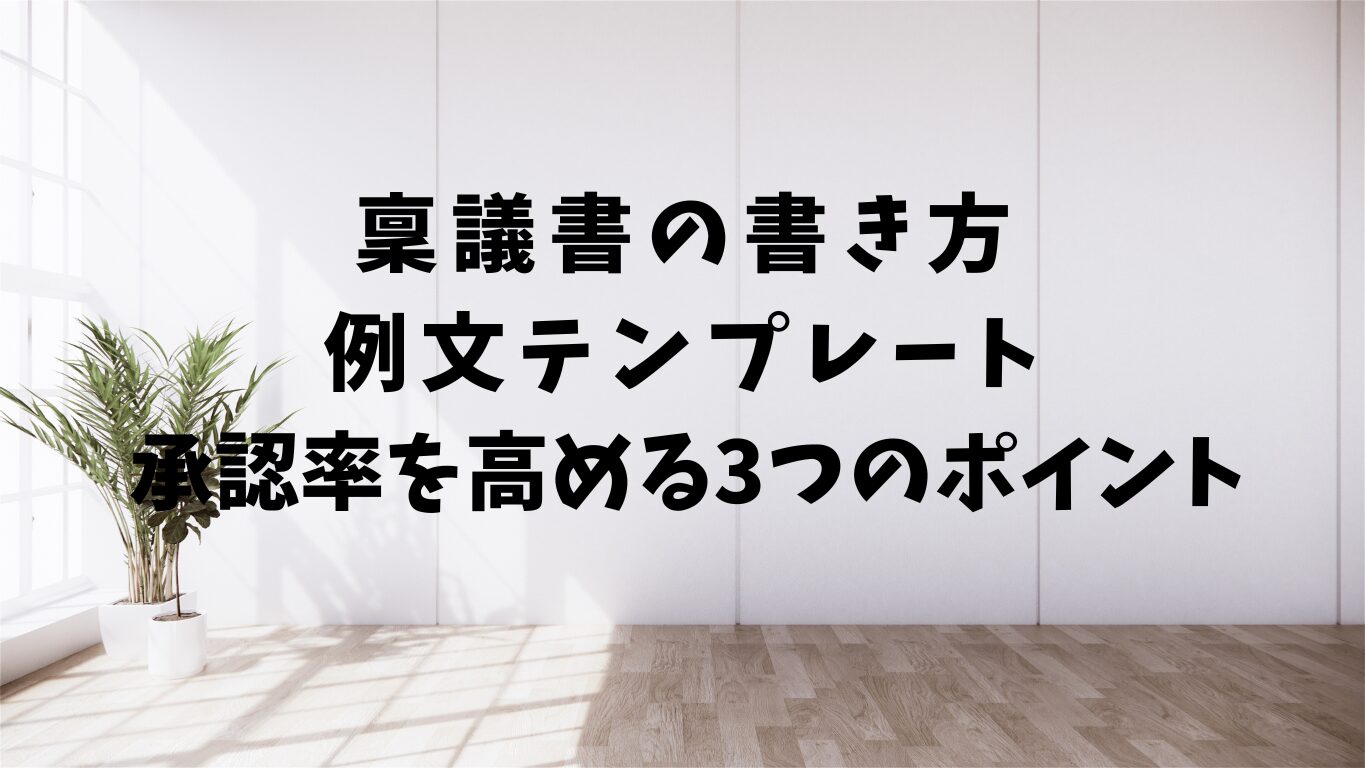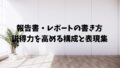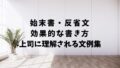ビジネスシーンで避けて通れない「稟議書」。
正しく作成できるかどうかが、あなたのプロジェクトや提案の成否を分けます。
稟議書の書き方に悩んでいませんか?
本記事では、承認率を高める稟議書の書き方のポイントと、すぐに使える例文・テンプレートを紹介します。
これを読めば、上司や決裁者を納得させる稟議書が作成できるようになります。
この記事でわかること
- 稟議書作成の基本的な流れと構成要素
- すぐに使える稟議書のテンプレートと例文
- 承認率を高める3つの重要ポイント
- 部署・目的別の稟議書の書き方の違い
- 稟議書作成でよくあるミスと対処法
稟議書作成にお悩みの方は、ぜひ最後までお読みください。
実践的なテンプレートと例文で、あなたの稟議書作成をサポートします。
すぐに使える稟議書テンプレートと例文
稟議書作成でまず必要なのは、基本的なフォーマットです。
ここでは、すぐに使える汎用テンプレートと、目的別の例文を紹介します。
稟議書テンプレートはシンプルに作成することが重要です。
必要な情報を過不足なく含めることで、読み手にとって理解しやすいものになります。
汎用稟議書テンプレート
稟議書
申請日:20XX年XX月XX日
部署名:○○部
申請者:○○○○(印)
件名:○○○○○○○○について
1. 目的
(目的を簡潔に記載)
2. 概要
(提案内容の概要を記載)
3. 実施内容
(詳細な実施内容を記載)
4. 予算
項目 金額 備考
○○○○ ○○○円 ○○○○
○○○○ ○○○円 ○○○○
合計 ○○○円
5. スケジュール
(実施予定のスケジュールを記載)
6. 効果
(期待される効果を具体的に記載)
7. リスクと対策
(想定されるリスクとその対策を記載)
8. 添付資料
(添付資料がある場合はここに記載)
決裁欄
課長 部長 役員 社長
□ □ □ □
備品購入の稟議書例文
ビジネスシーンでよくある備品購入の稟議書例です。
具体的な数値と効果を明記することがポイントです。
稟議書
申請日:2023年10月15日
部署名:営業部
申請者:山田太郎(印)
件名:営業部ノートパソコン5台の購入について
1. 目的
営業部員の業務効率向上および顧客先でのプレゼン品質向上のため、新規ノートパソコンの購入を申請いたします。
2. 概要
現在使用している営業部のノートパソコン5台は導入から5年が経過し、処理速度の低下やバッテリー持続時間の短縮により業務効率が低下しています。最新モデルへの更新により、約30%の業務時間短縮が見込まれます。
3. 実施内容
・メーカー・機種:Dell XPS 13(モデル番号:XXX)
・購入台数:5台
・購入先:株式会社○○○○
・保証:3年間延長保証付き
4. 予算
項目 金額 備考
ノートパソコン5台 825,000円 165,000円×5台
延長保証 75,000円 15,000円×5台
セットアップ費用 50,000円 10,000円×5台
合計 950,000円
5. スケジュール
承認後2週間以内に発注
納品後1週間以内にキッティング作業完了
11月末までに全台入れ替え完了予定
6. 効果
・顧客先でのプレゼン準備時間が約35%短縮
・バッテリー持続時間が2倍になり、外出先での作業効率が向上
・処理速度向上により、月間レポート作成時間が約3時間短縮
・年間約560時間の業務時間短縮効果(金額換算:約1,120,000円)
7. リスクと対策
・データ移行時のトラブル→事前にバックアップを取得し、IT部門と連携して実施
・新機種への操作習熟期間→マニュアルを整備し、導入時に簡易研修を実施
8. 添付資料
・見積書(株式会社○○○○)
・現行パソコンの使用状況調査結果
・新機種スペック比較表
敬語表現での稟議書例文(人事異動)
上位者への敬語表現を適切に使用した人事異動の稟議書例です。
丁寧かつ簡潔な表現を心がけましょう。
稟議書
申請日:2023年11月10日
部署名:人事部
申請者:佐藤誠(印)
件名:マーケティング部人員増強のための異動について
1. 目的
来期の事業計画達成に向けて、マーケティング部の人員体制強化のため、営業部から2名の人員異動をご提案申し上げます。
2. 概要
現在、マーケティング部では新規デジタルマーケティング施策の拡大に伴い、担当者の業務負荷が増加しております。営業部から経験値の高い2名を異動させることで、施策の質を維持しながら業務拡大に対応したいと存じます。
3. 実施内容
・異動対象者:営業部 鈴木一郎(入社5年目)、営業部 高橋花子(入社3年目)
・異動先:マーケティング部 デジタルマーケティングチーム
・異動日:2024年1月1日付
・両名のWebマーケティング知識:Google Analytics認定資格保有
4. 予算
項目 金額 備考
引継ぎ期間の残業代 60,000円 2名×15時間
研修費用 120,000円 オンライン講座受講料
合計 180,000円
5. スケジュール
11月中:本人および両部署への説明
12月中:引継ぎ作業および必要な研修実施
1月1日:正式異動
6. 効果
・マーケティング部の業務遅延リスクを解消(現在の遅延率15%→目標5%以下)
・営業とマーケティングの連携強化(顧客インサイト共有による施策精度向上)
・年間で約600万円の広告費用対効果改善を見込む
7. リスクと対策
・営業部の人員不足→営業プロセスの効率化および来期新卒2名を営業部に配属
・異動対象者のスキル不足→12月中に集中研修を実施し、基礎スキルを習得
・異動に伴うモチベーション低下→キャリアパス提示および評価制度の明確化
8. 添付資料
・対象者の業務経歴書
・マーケティング部の業務負荷分析資料
・異動後の組織体制図
決裁欄
人事課長 人事部長 役員 社長
□ □ □ □
間違いやすいポイント
- 目的と概要が重複している
- 効果が抽象的で具体的な数値がない
- リスク対策が不十分である
稟議書の基本的な書き方と構成
稟議書は企業内で意思決定を行うための重要な文書です。
基本的な構成と書き方を理解することで、スムーズな承認につながります。
稟議書の基本構成
稟議書は一般的に以下の項目で構成されます。
各社によって多少の違いはありますが、基本的な要素は共通しています。
- 件名(タイトル):簡潔かつ内容を的確に表現する
- 目的:なぜこの申請が必要なのかを明確に
- 概要:提案内容の全体像を簡潔に説明
- 実施内容:具体的な実施事項の詳細
- 予算:必要な費用の詳細と内訳
- スケジュール:実施時期や期間
- 効果:期待される効果(可能な限り数値化)
- リスクと対策:想定されるリスクとその対応策
- 添付資料:補足説明のための資料
稟議書作成の基本ステップ
稟議書を作成する際の基本的な流れは以下の通りです。
- 情報収集:必要な情報やデータを集める
- 構成検討:稟議書の構成を決める
- 下書き作成:各項目の内容を記入
- 数値確認:予算や効果の数値を精査
- 校正:誤字脱字や論理の矛盾がないか確認
- レビュー依頼:上司や関係者に内容を確認してもらう
- 修正:フィードバックに基づいて修正
- 最終確認:最終的な内容確認
- 提出:正式に稟議書を提出
各項目の書き方のポイント
各項目を書く際のポイントを詳しく説明します。
件名(タイトル)
- 内容が一目でわかる簡潔な表現を心がける
- 「〜について」という形式が一般的
- 具体的な数字を含めるとより明確になる
具体例
- 「営業部ノートパソコン5台の購入について」
- 「東京支社オフィス移転計画について」
- 「2024年度新卒採用活動予算申請について」
間違いやすいポイント
- 内容が抽象的すぎる(「設備投資について」)
- 長すぎる件名(簡潔さを心がける)
目的
- なぜこの提案が必要なのかを簡潔に説明
- 会社全体の目標や方針との関連性を示す
- 1〜2文で簡潔に表現する
具体例
「営業活動の効率化および顧客満足度向上のため、営業部のノートパソコンを最新機種に更新したく申請いたします。」
間違いやすいポイント
- 目的が不明確
- 会社の方針との関連性が示されていない
承認率を高める3つのポイント
稟議書が承認されるかどうかは、内容だけでなく書き方にも大きく影響されます。
ここでは、承認率を高めるための3つの重要なポイントを解説します。
ポイント1:数値化と具体性
決裁者を納得させるためには、抽象的な表現ではなく、具体的な数値や事実に基づいた記述が不可欠です。
数値化すべき項目
- 予算・コスト
- 期待される効果(売上増加率、コスト削減額など)
- 実施期間
- 人員リソース
具体例
具体性の低い記述(悪い例)
「新システム導入により業務効率が向上します」
具体性の高い記述(良い例)
「新システム導入により、現在1件あたり30分かかっている受注処理が平均12分に短縮され、月間約120時間(金額換算:約24万円)の業務効率化が見込まれます」
間違いやすいポイント
- 根拠のない楽観的な数値予測
- 具体的な数値がない抽象的な表現
ポイント2:費用対効果の明確化
投資に対するリターンを明確に示すことで、決裁者は判断しやすくなります。
費用対効果を示す方法
- ROI(投資利益率)の算出
- 投資回収期間の明示
- 定量的効果と定性的効果の両面から説明
具体例
効果が不明確な記述(悪い例)
「研修費用として50万円が必要ですが、社員のスキルアップにつながります」
効果が明確な記述(良い例)
「研修費用として50万円が必要ですが、この研修により営業チームの商談成約率が現在の15%から20%に向上すると予測され、年間約600万円の売上増加が見込まれます。投資回収期間は約1か月です」
間違いやすいポイント
- 定性的効果のみの記載
- 費用と効果の時間軸が不明確
ポイント3:リスク対策の提示
提案にはリスクがつきものです。
事前にリスクを想定し、対策を示すことで信頼性が高まります。
リスク対策の書き方
- 想定されるリスクを箇条書きで列挙
- 各リスクに対する具体的な対策を記載
- 責任者や対応フローを明確にする
具体例
リスク対策が不十分な記述(悪い例)
「システム導入に伴う業務停止のリスクがありますが、対応します」
リスク対策が充実した記述(良い例)
「システム導入に伴うリスク:
- データ移行中の業務停止リスク→休日を利用した移行作業実施、バックアップ体制の構築
- 操作習熟期間中の業務効率低下→段階的導入と部門ごとの研修実施
- 既存システムとの連携不具合→事前検証環境での十分なテスト実施と即時対応チームの編成」
間違いやすいポイント
- リスクの過小評価
- 対策が抽象的
- 重大なリスクの記載漏れ
部署・目的別の稟議書の書き方
部署や申請目的によって、稟議書の書き方には微妙な違いがあります。
それぞれのケースに応じた書き方のポイントを解説します。
部署や目的に合わせた稟議書を作成することで、その部門特有の課題や目標に対応した提案ができます。
営業部門の稟議書
営業部門からの申請では、売上や顧客満足度への影響を強調することが重要です。
営業部門の主な申請内容
- 営業ツール導入
- 販促キャンペーン実施
- 展示会・イベント出展
営業部門特有のポイント
- 売上・利益への貢献度を数値で示す
- 顧客満足度への影響に言及
- 競合他社との比較分析を含める
具体例(営業支援ツール導入の場合)
効果:
1. 商談管理の効率化により、営業担当者1人あたりの月間商談数が15件から22件に増加(約47%向上)
2. 商談成約率が現在の18%から予測25%へ向上
3. 上記1、2による年間売上増加効果:約1億2,000万円
4. 顧客情報の一元管理により、クロスセル機会が20%増加
間違いやすいポイント
- 効果の過大評価
- 現場の営業担当者の意見や実態を反映していない
人事部門の稟議書
人事部門からの申請では、社員満足度や生産性への影響、コンプライアンスの観点を重視します。
人事部門の主な申請内容
- 採用活動予算
- 研修プログラム実施
- 人事制度変更
- 福利厚生制度導入
人事部門特有のポイント
- 法令順守の観点を含める
- 社員満足度への影響を示す
- 離職率や採用コストへの影響を数値化
具体例(新研修プログラム導入の場合)
効果:
1. 業務スキル向上による生産性20%向上(1人あたり年間約40万円の価値創出)
2. 同業他社比較で10%低い離職率の達成(採用コスト年間約500万円削減)
3. 社員満足度調査スコアの15%向上
4. マネージャー育成による組織マネジメント品質の向上
間違いやすいポイント
- 定性的な効果のみを記載
- 社内状況(離職率、満足度等)の現状分析が不足
IT部門の稟議書
IT部門からの申請では、業務効率化やセキュリティ強化など、技術的な側面と業務への影響の両方を説明することが重要です。
IT部門の主な申請内容
- システム導入・更新
- インフラ整備
- セキュリティ対策
- ライセンス契約
IT部門特有のポイント
- 技術的内容を非IT部門の決裁者にもわかりやすく説明
- コスト削減効果や業務効率化を数値で示す
- セキュリティリスクへの対応を明確に
具体例(新システム導入の場合)
概要:
現在、各部門で個別に管理されている顧客データを統合管理するCRMシステムを導入します。これにより、データ入力の重複作業が解消され、リアルタイムの情報共有が可能になります。
効果:
1. データ入力工数の削減:全社で月間約80時間の工数削減(年間約192万円相当)
2. 情報共有の即時化による営業機会損失の防止:年間約2,000万円の機会損失回避
3. データ分析による顧客インサイトの獲得:マーケティング施策の精度向上
4. システム運用コストの削減:現行の複数システム維持費と比較し、年間約300万円削減
間違いやすいポイント
- 技術的な説明が難解で決裁者が理解できない
- 運用体制やメンテナンスコストへの言及がない
稟議書作成時の注意点
稟議書作成時には、いくつかの重要な注意点があります。
これらに気をつけることで、スムーズな承認プロセスにつながります。
よくある不備と対策
稟議書でよく見られる不備と、その対策を解説します。
1. 情報の不足
問題点
必要な情報が不足していると、決裁者が判断できず、差し戻しの原因になります。
対策
- チェックリストを作成し、必要情報を網羅しているか確認
- 第三者に内容を確認してもらう
- 「5W1H」の観点で情報の過不足をチェック
具体例(情報不足の例)
「新システムを導入したいので承認お願いします」
具体例(改善例)
「現在のシステムの課題(処理速度の低下、保守期限切れ)を解決するため、新システムの導入を提案します。導入費用は500万円、運用コストは年間50万円で、現行比30%の削減となります…」
間違いやすいポイント
- 決裁者が既に情報を持っていると思い込む
- 技術的な詳細に偏り、ビジネス的な効果の説明が不足
2. 文章の冗長さ
問題点
文章が長すぎたり、重要点が埋もれていたりすると、決裁者に要点が伝わりません。
対策
- 1つの段落に1つの要点を心がける
- 箇条書きや表を効果的に使用
- 重要なポイントは太字や下線で強調
具体例(冗長な文章の例)
「当部署では昨年度から業務効率化を推進しており、その一環として様々な施策を検討してきましたが、特に注力すべき点として顧客対応の迅速化があり、それを実現するためには…」
具体例(改善例)
「目的: 顧客対応時間の30%削減による顧客満足度向上
背景: 現在の対応時間は業界平均より15%長く、顧客満足度調査でも改善要望が最多
提案内容: 顧客対応システムの更新により、応対時間を平均8分から5.5分に短縮」
間違いやすいポイント
- 背景説明が長すぎる
- 1つの文章に複数の内容を詰め込む
3. スケジュールの不明確さ
問題点
実施スケジュールが不明確だと、リソース配分や他のプロジェクトとの調整ができません。
対策
- 明確な開始日・終了日を設定
- マイルストーンを明示
- 依存関係のあるタスクを明確にする
具体例(不明確なスケジュールの例)
「承認後、速やかに実施します」
具体例(改善例)
スケジュール:
1. 承認後2週間以内:ベンダー選定完了
2. 6月中旬:契約締結
3. 7月1日〜31日:システム構築
4. 8月1日〜15日:テスト運用
5. 8月16日:本稼働開始
間違いやすいポイント
- 具体的な日程がない
- 準備期間や移行期間が考慮されていない
稟議書の体裁と形式
稟議書の体裁や形式も、印象に大きく影響します。
フォーマットの統一
- 会社指定の稟議書テンプレートがある場合は必ず使用する
- 独自フォーマットの場合も、項目や順序は一貫性を持たせる
- フォントサイズや行間は読みやすいものにする
視覚的な工夫
- 重要な数字や効果は太字にする
- 表やグラフを効果的に使用する
- 見出しを明確にし、階層構造を分かりやすくする
具体例(視覚的工夫の例)
【現状】
処理時間:1件あたり平均15分
処理ミス:月間約20件(3%)
顧客満足度:68点/100点
【導入後予測】
処理時間:1件あたり平均8分(▲47%)
処理ミス:月間約5件(0.7%)(▲75%)
顧客満足度:85点/100点(+17点)
間違いやすいポイント
- 文字だけの説明で視覚的工夫がない
- 数値の変化が分かりにくい表現
稟議書提出後のフォローアップ
稟議書を提出したら終わりではありません。
承認までのフォローと、承認後の実施管理も重要です。
承認までのフォロー方法
稟議書の承認を円滑に進めるためのフォロー方法を解説します。
稟議書のステータス管理
- 稟議書の現在位置(誰の決裁待ちか)を把握する
- 長期間滞っている場合は、適切に確認する
- 差し戻しや質問には迅速に対応する
補足説明の準備
- 想定される質問への回答を事前に準備
- 詳細データや補足資料をすぐに提示できるようにしておく
- 必要に応じて説明の機会を設ける
具体例(想定質問リストの例)
Q1: なぜこのタイミングでの実施が必要か?
A1: 現行システムの保守期限が9月末で切れるため、それまでに切り替えを完了する必要があります。また、下半期の繁忙期前に安定稼働させるためです。
Q2: 代替案は検討したか?
A2: 以下3案を検討しました。
- 現行システムの延長利用:保守費用が年間100万円増加
- 他社製品A:機能は充実しているが、導入コストが30%高い
- 自社開発:開発期間12か月必要で間に合わない
間違いやすいポイント
- フォローが不足し、承認が遅れる
- 質問への回答準備が不十分
承認後の報告と実施管理
稟議書が承認された後も、適切な実施管理と報告が重要です。
計画通りに進めるためのポイントを解説します。
進捗報告の重要性
- 定期的な進捗報告で関係者との信頼関係を構築
- 問題発生時は早期に報告し、対策を講じる
- 当初計画からの変更がある場合は、適切に共有する
効果測定と検証
- 稟議書で示した効果指標を測定する
- 予測と実績の差異を分析
- 次回の稟議に活かせるよう記録を残す
具体例(進捗報告の例)
【システム導入プロジェクト進捗報告】
報告日:2023年7月15日
1. 全体進捗状況:予定通り進行中(進捗率65%)
2. 完了したマイルストーン
- ベンダー選定(6月15日完了)
- 契約締結(6月30日完了)
- 基本設計(7月10日完了)
3. 現在の作業状況
- 詳細設計進行中(完了予定:7月25日)
4. 発生した課題
- データ移行の対象範囲拡大(追加工数:3人日)→予備日を使用し対応済み
5. 今後の予定
- 7月26日〜8月5日:開発・カスタマイズ
- 8月6日〜15日:テスト実施
間違いやすいポイント
- 報告が不定期または形骸化している
- 問題の報告が遅れ、対応が後手に回る
まとめ:効果的な稟議書作成のために
稟議書は単なる申請文書ではなく、ビジネス提案の重要なツールです。
効果的な稟議書を作成するためのポイントをまとめます。
承認率を高める3つの重要ポイント
- 数値化と具体性
- 抽象的な表現ではなく、具体的な数値で効果を示す
- ビジネスインパクトを明確に表現する
- 費用対効果の明確化
- 投資に対するリターンを具体的に示す
- ROIや回収期間を明示する
- リスク対策の提示
- 想定されるリスクを事前に洗い出す
- 具体的な対応策を示し、信頼性を高める
稟議書作成のプロセス改善
- 過去の稟議書で承認されたものを参考にする
- 決裁者のニーズや視点を理解する
- フィードバックを次回に活かす仕組みを作る
稟議書作成は経験を重ねることで上達します。
本記事で紹介したポイントを実践し、説得力のある稟議書を作成してください。
効果的な稟議書は、あなたのビジネスアイデアを実現する強力なツールとなるでしょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 稟議書と決裁書の違いは何ですか?
A1: 稟議書は提案者が作成する申請書類であり、決裁書はその申請に対する承認を記録する書類です。
多くの企業では稟議書に決裁欄を設け、一体型として運用しています。
Q2: 稟議書の金額に応じて決裁者が変わることがありますか?
A2: はい、多くの企業では決裁権限規程を設けており、申請金額によって決裁者のレベルが変わります。
例えば、10万円未満は部長決裁、100万円未満は本部長決裁、それ以上は役員決裁といった具合です。
事前に自社の規程を確認しましょう。
Q3: 稟議書が否決された場合、どのように対応すべきですか?
A3: まず否決理由を正確に把握し、以下の対応を検討します。
- 提案内容を見直し、指摘された問題点を解決する
- 規模を縮小するなど、リスクを低減した代替案を用意する
- より詳細な分析や検証結果を追加する
- 必要に応じて関係者と事前調整を行ってから再提出する
Q4: 電子稟議システムを使用する際の注意点はありますか?
A4: 電子稟議システムを使用する際は、以下の点に注意しましょう。
- 添付ファイルの容量制限を確認する
- システム上で表示が崩れないようにフォーマットを工夫する
- 決裁ルートを事前に確認し、適切に設定する
- 承認状況を定期的に確認し、必要に応じてリマインドする
Q5: 緊急で承認が必要な場合、どのように対応すべきですか?
A5: 緊急時の対応方法は以下の通りです。
- 稟議書に「緊急」と明記し、理由を明確に記載する
- 事前に決裁者に口頭で状況を説明し、協力を仰ぐ
- 緊急決裁のための社内ルール(代理決裁など)を確認する
- 承認後でも正式な手続きは必ず完了させる
企業によっては、一定金額以下の緊急案件に対応する「事後稟議」の仕組みを設けている場合もあります。