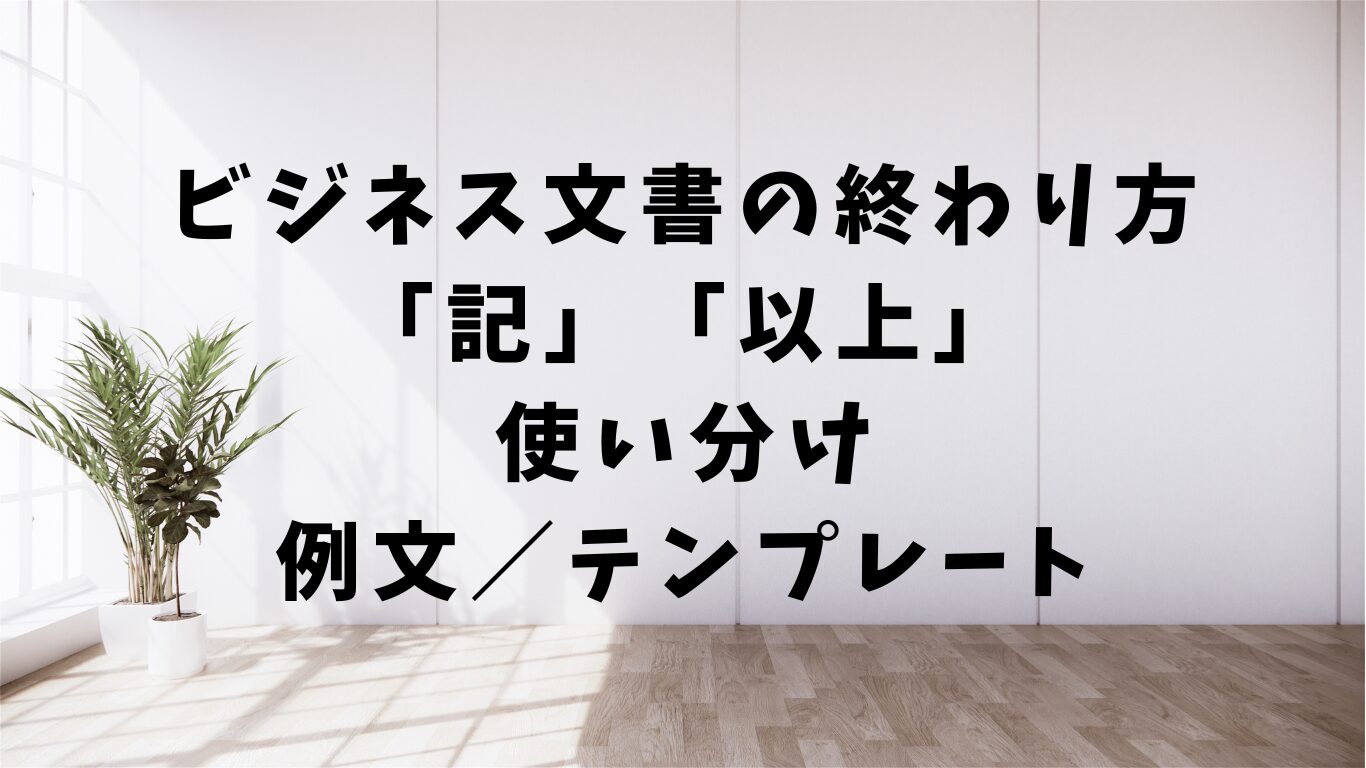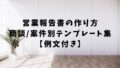ビジネス文書の締めくくり方は、文書全体の印象を左右する重要な要素です。
特に「記」と「以上」という日本の伝統的な締めくくり表現は、使い方を誤ると非常に不自然な印象を与えかねません。
実は、これらの表現には明確な使い分けのルールが存在し、適切に活用することで文書の品格を高めることができます。
本記事では、「記」「以上」の使い分けから、シーン別の具体的な例文、そしてすぐに使えるテンプレートまで、実践的なノウハウをご紹介します。
この記事でわかること
- 「記」と「以上」の正しい使い分けの基準
- 業種・文書別の具体的な使用例とテンプレート
- ビジネスシーン別の効果的な文書の締めくくり方
- よくある間違いと具体的な改善方法
- 電子メールなど新しいビジネス文書での活用法
ビジネスの現場ですぐに活用できる例文とテンプレートを用意しました。
文書作成の効率を上げながら、プロフェッショナルな印象を与える文書作りにお役立てください。
すぐに使える!シーン別テンプレート集
ビジネス文書の締めくくり方は、文書の種類や用途によって大きく異なります。
ここでは、すぐに実務で活用できる具体的なテンプレートを、シーン別にご紹介します。
これらのテンプレートを基本として、状況に応じてアレンジしていただければ、効率的な文書作成が可能になります。
基本的なテンプレートと活用シーン
文書の基本となる申請書や稟議書には、「記」を使用した明確な書式があります。
ここでは、最も一般的な形式と、実際の活用シーンについて解説します。
各テンプレートは、コピー&ペーストですぐに使える形式で用意しました。
【基本形式のポイント】
- 用紙の中央より少し上に「記」を配置
- 項目は1行空けて配置
- 番号付けは漢数字を使用
- 最終項目の後は「以上」不要
📝 申請書・届出書の基本テンプレート
記
1.申請内容:○○○○○○○○
2.申請理由:○○○○○○○○
3.希望期日:○○○○○○○○
4.備考 :○○○○○○○○電子申請システムを使用する場合は、文字数制限や改行位置に注意が必要です。
また、添付書類がある場合は、ファイル形式や容量制限についても事前確認が推奨されます。
📋 稟議書の基本テンプレート
記
1.案件名称:○○○○○○○○
2.決裁金額:○○○○○○○○
3.実施時期:○○○○○○○○
4.詳細内容:○○○○○○○○
5.検討事項:○○○○○○○○長期的なプロジェクトや大規模な予算を伴う案件の場合は、想定されるリスクと対策についても別途詳細な資料を用意すると、より充実した稟議書となります。
ビジネスメール向けの効果的な締めくくりテンプレート
電子メールは現代のビジネスコミュニケーションの中心です。
従来の形式的な文書とは異なる、適切な締めくくり方が求められます。
状況や目的に応じた効果的な締めくくり方を、具体例とともに解説します。
【メール締めくくりのポイント】
- 依頼の軽重に応じて表現を選択
- 相手の立場に合わせて丁寧さを調整
- 返信期限がある場合は明記
- 箇条書きの場合は「記」を使用
- 続きがない場合は「以上」を活用
📧 一般的な依頼メールテンプレート
ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。 以上
一方、重要案件の相談メールテンプレートでは、「記」で箇条書きを使用しているため、「以上」は不要です。
むしろ使用すると二重の締めくくりになってしまい、不自然な印象を与えてしまいます。
📧 重要案件の相談メールテンプレート
記 1.ご相談事項:○○○○○○○○ 2.現状の課題:○○○○○○○○ 3.改善案 :○○○○○○○○ 4.ご相談したい点 ・○○○○について ・○○○○の方向性 ・○○○○の進め方 ご多忙のところ恐縮ですが、ご検討いただけますと幸いです。 ○○株式会社 ○○部 ○○○○
このように、「記」で始まる箇条書きの場合は、「以上」を付けずに、そのまま結びの言葉と署名に移行する形が正しいです。
これは本文中のFAQでも説明している通り、「記」による箇条書き形式自体が完結した形となるためです。
報告書・議事録での締めくくり方
報告書や議事録は、情報を正確に記録し伝達する重要な文書です。
関連記事
形式的な要件を満たしながら、内容を分かりやすく整理することが求められます。
ここでは、実務で即活用できる形式的なテンプレートをご紹介します。
【報告書作成のポイント】
- 報告内容を明確に区分
- 時系列や優先順位を意識
- 結論や要望を明確に記載
- 必要に応じて添付資料を明記
- 文責を示す場合は末尾に記載
📋 業務報告書テンプレート
記 1.報告期間:○○○○年○月○日~○月○日 2.実施内容 (1)○○○○○○○○ (2)○○○○○○○○ 3.達成状況 4.今後の課題 5.添付資料 文責:○○部○○課 ○○○○
文書の電子化に対応する場合は、表やグラフなどの視覚資料を効果的に活用することで、さらに分かりやすい報告書となります。
「記」の正しい使い方と実践例
「記」は日本の伝統的なビジネス文書で使用される重要な表現です。
適切に使用することで、文書の形式美を保ちながら、内容を明確に伝えることができます。
ここでは、「記」の基本的な使い方から応用まで、実践的な例を交えて解説します。
「記」を使用する基本的な考え方
「記」は、これから箇条書きで項目を列挙することを示す際に使用される伝統的な表現です。
文書の格式を高めながら、内容を整理して伝えるための重要な役割を果たします。
特に公式文書では、この「記」の使用が適切さを示すポイントとなります。
【「記」使用の5つのポイント】
- 文書の中央より少し上に配置する
- 前文があっても必ず1行空ける
- 項目は漢数字で番号付けする
- 各項目の説明は「:」の後に記載
- 項目間は1行空けて見やすく
🎯 「記」の基本的な使用例
○○○○について、下記の通りご報告申し上げます。 記 1.件 名:○○○○○○ 2.日 時:○○○○年○月○日 3.場 所:○○○○○○ 4.内 容:○○○○○○
組織によっては独自の書式規定がある場合もあるため、事前に適用すべき規定の有無を確認することが推奨されます。
効果的な「記」の活用シーン
「記」は様々なビジネス文書で活用できますが、特に効果を発揮するシーンがあります。
ここでは、実務で特によく使用される場面と、その具体的な活用方法についてご説明します。
【「記」が効果的な文書の種類と特徴】
- 申請書:正式な手続きを示す
- 報告書:内容を整理して伝える
- 通知文:重要事項を明確に示す
- 企画書:提案内容を体系的に説明
- 議事録:決定事項を箇条書きで記録
📝 通知文書での活用例
部門異動について、下記の通りお知らせいたします。 記 1.異動日時:○○○○年○月○日付 2.対象者 :○○部 ○○ ○○ 3.異動先 :○○部○○課 4.業務内容:○○○○○○ 5.引継期間:○○○○年○月○日まで
重要度の高い通知の場合は、受領確認の仕組みを組み込むことで、確実な情報伝達が実現できます。
関連記事
「以上」の効果的な活用法
「以上」は文書の終わりを示す重要な表現です。
しかし、使用するタイミングや場面を誤ると、かえって不自然な印象を与えてしまいます。
ここでは、「以上」の効果的な使い方について、具体例を交えながら解説します。
「以上」を使用する基本ルール
「以上」は文書の終わりを明確に示す表現ですが、使用には一定のルールがあります。
適切な使用により、文書の完結性を高め、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
【「以上」使用の5つの基本ルール】
- 本文が完結した後に使用
- 箇条書きの後には原則不要
- 電子メールでは署名前に配置
- 前後は1行空ける
- 中央揃えにしない
📋 「以上」の基本的な使用例(報告メール)
○月○日の会議の結果について報告いたします。 開催日時:○月○日○時 出席者 :○○、○○、○○ 決定事項:○○○○について承認 以上 ○○株式会社 ○○部 ○○○○
署名が自動設定されている場合でも、本文と署名の区切りとして「以上」を入れることで、文書の完結性が高まります。
「以上」の効果的な省略パターン
「以上」は使用すべき場面と、むしろ省略した方が自然な場面があります。
ここでは、「以上」を省略できる、あるいは省略すべき状況について解説します。
【「以上」を省略できる5つの場面】
- 署名や連絡先が続く場合
- 短い定型的な通知の場合
- 「記」を使用した箇条書きの後
- 非公式な社内メールの場合
- 依頼文で結ぶ場合
🔍 「以上」省略の適切な例
○月○日のミーティングについて出欠を確認させていただきます。 日時:○月○日 15:00~16:00 場所:会議室A 議題:○○○○について ご都合をご返信ください。 ○○部 ○○○○
社内の簡易なコミュニケーションでは、結びの言葉で自然に締めくくることで、より柔軟な文書作成が可能です。
状況別の使い分けガイド
ビジネス文書は、状況や目的によって適切な締めくくり方が異なります。
ここでは、具体的なシーンごとに、「記」「以上」の使い分けと、その他の効果的な締めくくり方をご紹介します。
社内向け文書の締めくくり方
社内文書は、形式にとらわれすぎず、効率的なコミュニケーションを重視します。
ただし、重要度や文書の性質に応じて、適切な形式を選ぶ必要があります。
【社内文書での締めくくり方5つのポイント】
- 用件の重要度に応じて形式を選択
- 簡潔で分かりやすい表現を心がける
- 必要以上に形式的にならない
- 伝達事項は明確に区分する
- フォローアップの方法を示す
📝 社内通達文書の例
【社内回覧】 記 1.件 名:夏季休暇取得について 2.対 象:全社員 3.期 間:○月○日~○月○日 4.連絡先:総務部○○(内線:××××) ※ 部署ごとの調整後、○月○日までに総務部まで 取得予定日を報告ください。
電子掲示板やグループウェアでの掲示を想定する場合は、見出しに検索用キーワードを含めることで、後からの参照性を高められます。
取引先への文書の締めくくり方
取引先への文書は、社内文書と比べてより慎重な対応が必要です。
適切な敬語を使用し、明確な形式を守ることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
【取引先向け文書の5つの重要ポイント】
- 適切な敬語表現を使用する
- 文書の格式を意識する
- 明確な締めくくりを心がける
- 連絡先情報を明記する
- フォローアップ方法を具体的に示す
📋 取引先への案内文書テンプレート
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、下記の件につきまして、ご案内申し上げます。 記 1.件 名:○○○○○○○○ 2.日 時:○○○○年○月○日 3.場 所:○○○○○○○○ 4.内 容:○○○○○○○○ ご多用中誠に恐縮ではございますが、○月○日までに 同封の返信用紙にてご回答いただけますよう、 お願い申し上げます。 敬具 ○○○○年○月○日 ○○株式会社 ○○部 ○○○○ TEL:○○-○○○○-○○○○
海外取引先が含まれる場合は、日本語特有の表現を避け、より簡潔な文体を心がけることが効果的です。
電子メールでの活用ポイント
現代のビジネスコミュニケーションの中心となっている電子メール。
従来の紙の文書とは異なる特性を理解し、適切な締めくくり方を選択することが重要です。
メールの種類別締めくくりパターン
目的や重要度によってメールの締めくくり方を使い分けることで、より効果的なコミュニケーションが可能になります。
【メール種類別の締めくくり方】
- 通知メール
- 依頼メール
- 報告メール
- お詫びメール
- お礼メール
📧 メールの種類別テンプレート集
【通知メール】 以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。 【依頼メール】 ご多用中恐れ入りますが、ご検討いただけますと幸いです。 【報告メール】 記 1.実施内容:○○○○○○ 2.結果概要:○○○○○○ 3.今後の予定:○○○○○○ 【お詫びメール】 今後このようなことがないよう、十分注意いたします。 何卒ご容赦くださいますよう、お願い申し上げます。 【お礼メール】 今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。
テンプレートの文言は、社内の文化や慣習に合わせて適宜カスタマイズすることで、より自然なコミュニケーションが実現できます。
取引先への文書の締めくくり方
取引先への文書は、社内文書と比べてより慎重な対応が必要です。
適切な敬語を使用し、明確な形式を守ることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
【取引先向け文書の5つの重要ポイント】
- 適切な敬語表現を使用する
- 文書の格式を意識する
- 明確な締めくくりを心がける
- 連絡先情報を明記する
- フォローアップ方法を具体的に示す
📋 取引先への案内文書テンプレート
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、下記の件につきまして、ご案内申し上げます。 記 1.件 名:○○○○○○○○ 2.日 時:○○○○年○月○日 3.場 所:○○○○○○○○ 4.内 容:○○○○○○○○ ご多用中誠に恐縮ではございますが、○月○日までに 同封の返信用紙にてご回答いただけますよう、 お願い申し上げます。 敬具 ○○○○年○月○日 ○○株式会社 ○○部 ○○○○ TEL:○○-○○○○-○○○○
電子メールでの送付を想定する場合は、フォーマットの崩れを防ぐため、PDFなどの形式での添付も検討することが望ましいです。
また、重要な案内の場合は、受領確認の方法についても明記しておくと確実です。
メール文書特有の注意点
電子メールは従来の紙の文書とは異なる特性があり、独自の注意点があります。
ここでは、メールでの「記」「以上」の使用時における重要なポイントを解説します。
【メールでの締めくくり5つの注意点】
- 画面サイズによる見え方の違いを考慮
- 署名との位置関係を意識
- 返信や転送時の体裁崩れに注意
- モバイル端末での表示を考慮
- 文字化けリスクを避ける
⚠️ メールでの体裁維持のコツ
■画面幅に左右されない記の書き方 記 1.○○○○ 2.○○○○ ※中央寄せではなく、半角スペース8個で インデントを作る方が安全です
モバイル端末での閲覧を考慮し、複雑な書式や特殊文字の使用は最小限に抑えることが望ましいです。
書類の種類別テンプレート
様々なビジネス文書で求められる適切な締めくくり方を、書類の種類別にまとめました。
それぞれの書類の特性を理解し、最適な形式を選択することが重要です。
社内稟議書・申請書の作成
稟議書や申請書は、組織内での正式な手続きを行うための重要な文書です。
明確な形式と構造を持つことで、スムーズな承認プロセスを実現します。
【稟議書・申請書作成の5つのポイント】
- 承認フローを意識した構成
- 必要情報の漏れがないか確認
- 金額や日付は明確に記載
- 添付資料の有無を明記
- 担当者の連絡先を記載
📑 稟議書標準テンプレート
記 1.件 名:○○○○について 2.申請金額:○○○○円 3.支払時期:○○○○年○月 4.目 的: (1)○○○○ (2)○○○○ 5.効 果: (1)○○○○ (2)○○○○ 6.添付資料: ・○○○○ ・○○○○ 担当:○○部 ○○○○(内線:XXXX)
電子決裁システムを使用する場合は、添付資料の保存形式や容量制限にも注意を払う必要があります。
議事録・報告書の作成
議事録や報告書は、情報を正確に記録し共有するための重要な文書です。
内容を分かりやすく整理し、必要な情報を漏れなく記載することが求められます。
【議事録・報告書作成の5つのポイント】
- 時系列や項目を明確に区分
- 決定事項を明確に記載
- 担当者と期限を明記
- 次回予定を記載
- 配布先を明確にする
📊 議事録標準テンプレート
記 1.会議名:○○○○会議 2.日 時:○○○○年○月○日 ○○:○○~○○:○○ 3.場 所:○○会議室 4.出席者:○○部 ○○○○ ○○部 ○○○○ 5.議 題: (1)○○○○について →決定事項:○○○○ →担当者:○○○○ →期 限:○○○○年○月○日 6.次回予定:○○○○年○月○日 ○○:○○~ 配布先:○○○○、○○○○ 作成者:○○部 ○○○○(内線:XXXX)
オンライン会議の場合は、録画データの保存場所や参照方法についても記載すると、より充実した議事録となります。
関連記事
- 議事録の書き方|テンプレートと例文【3分で作成できるコツ完全版】
- オンライン会議の議事録作成完全ガイド|テンプレート20選とZoom/Teams活用法
- 報告書の書き方|すぐ使えるテンプレート付き【現場で使える完全版】
よくあるミスと対処法
ビジネス文書の締めくくりでは、些細なミスが文書全体の印象を損ねることがあります。
ここでは、特によく見られるミスとその対処法について解説します。
致命的な間違いとその回避方法
文書の締めくくりにおける重大なミスは、文書の信頼性に関わる問題となります。
以下に主な間違いとその対処法をまとめました。
【よくある5つの重大なミス】
- 「記」と「以上」の重複使用
- 箇条書き後の不適切な「以上」
- 電子メールでの中央揃えレイアウト崩れ
- 敬語と略語の不適切な混在
- 署名位置の誤り
❌ 悪い例と⭕️ 良い例
【悪い例】 記 1.○○○○ 2.○○○○ 以上 ←「記」の後に「以上」は不要 【良い例】 記 1.○○○○ 2.○○○○ 担当:○○部 ○○○○
組織の文書規定によっては、これらの例とは異なる形式が求められる場合もあるため、適用する際は規定の確認が必要です。
まとめ
「記」と「以上」の適切な使い分けは、ビジネス文書の品質を大きく左右します。
本記事で解説した基本ルールとテンプレートを活用することで、より効果的なビジネスコミュニケーションを実現できます。
特に重要なポイントを改めて確認しましょう:
- 「記」は箇条書きの導入に使用し、その後の「以上」は不要
- 文書の種類と目的に応じて適切な形式を選択
- 電子メールでは画面表示を考慮した対応が必要
- 社内・社外で適切な形式を使い分ける
- テンプレートは状況に応じてカスタマイズする
ビジネス文書は、組織や業界によって求められる形式が異なる場合もあります。
本記事で紹介したテンプレートを基本としながら、必要に応じて調整を加えることで、より効果的な文書作成が可能になります。
よくある質問(FAQ):ビジネス文書の締めくくりQ&A
ビジネス文書の締めくくりについて、実務でよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。
基本的なルールから実践的な応用まで、具体的な事例とともに解説します。
【よくある質問の主なポイント】
- 基本的な使い分けのルール
- 特殊なケースでの対応方法
- 電子メールでの活用方法
- 業界特有の慣習への対応
- 海外取引での注意点
Q1:「記」を使用した後に「以上」は必要ですか?
A1:「記」を使用した箇条書きの場合、「以上」は不要です。
「記」で始まる箇条書きは、それ自体が完結した形式となります。
むしろ「以上」を付けることで不自然な印象を与えてしまいます。
Q2:メールの場合、「以上」と署名はどちらが先ですか?
A2:基本的には「以上」を先に記載し、その後に署名を入れます。
ただし、署名が自動設定されている場合は、「以上」を省略しても問題ありません。
Q3:報告書で箇条書きを使う場合、必ず「記」が必要ですか?
A3:正式な報告書の場合は「記」を使用することを推奨します。
ただし、社内の軽微な報告や日常的なメールなどでは、箇条書きを「記」なしで使用しても問題ありません。
Q4:英文レターを含む文書の場合、どう締めくくればよいですか?
A4:日本語部分と英語部分は別々に考えます。
日本語部分は通常の形式で、英語部分は”Sincerely yours,”などの一般的な英文レターの形式に従います。
Q5:「記」を使用する際の項目番号は、必ず漢数字ですか?
A5:漢数字が一般的ですが、組織の規定や文書の性質によっては、丸数字(①②③)やアルファベット(A,B,C)なども使用できます。
重要なのは、文書内での一貫性です。
Q6:電子メールで長文の場合の締めくくり方は?
A6:内容が箇条書きできる場合は「記」を使用し、文章が連続する場合は最後に「以上」を入れます。
特に重要な報告や依頼の場合は、「記」を使用することで、内容を整理しやすくなります。
Q7:カジュアルなビジネスメールでも「以上」は必要ですか?
A7:カジュアルなメールでは「以上」を省略しても問題ありません。
特に、短いメールや日常的なやりとりでは、「よろしくお願いします」などの一般的な締めくくりで十分です。
Q8:「記」の後の箇条書きで、項目が1つだけの場合はどうすればよいですか?
A8:項目が1つでも「記」を使用できますが、その場合は箇条書きを使用せず、通常の文章形式で記載することを推奨します。